
仕事のパフォーマンスを上げる「戦略的睡眠」のススメ
優れた睡眠はいうまでもなく健康の基本だ。とくにビジネスパーソンは睡眠不足によ……

優れた睡眠はいうまでもなく健康の基本だ。とくにビジネスパーソンは睡眠不足によ……

人材の採用、登用の困難性の高まりから、「多様性:Divers……

日本企業の株価が上昇し、34年ぶりに高値を更新した。世間では30年にわたるデ……
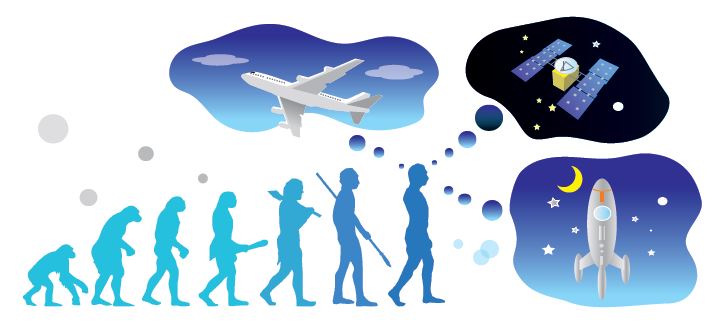
いまのアナタに足りないのは妄想する力かもしれない―。 妄想する力が注……

2024年の正月に起こった能登半島地震。半島という土地の特性や高齢化……

ネットやAIが進化すると人間の営業はだんだん要らなくなる……。多くの人はそう……
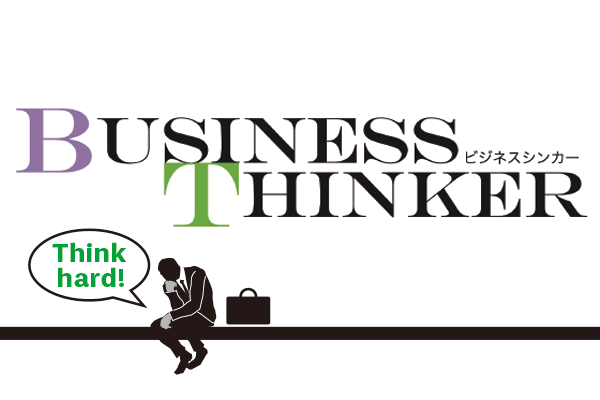
世界には個人の名前、あるいは兄弟、一族の名を冠した大企業がたくさんある。いわ……

AIやデジタル化がどんどん進化すれば、仕事や生活がどんどん楽になると思っていた……
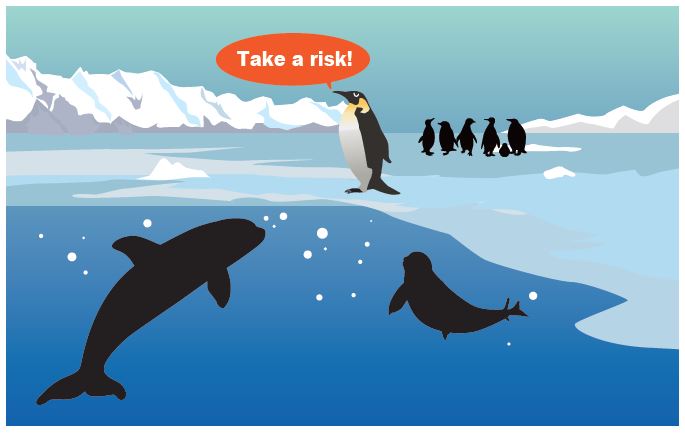
ファーストペンギンという言葉を聞いて、「それ何?」という人は余りいな……

コラボレーション。略してコラボはもはや普通名詞化している。しかし、企業のトレ……

世界を襲ったパンデミックが小康状態となったと思ったら、ロシアとウクライナの戦……

バニラは速くて、レモンは遅い―。いったいぜんたい、なんのこっちゃ?? と思う……