「枕投げ」から“ ハゲ頭” 賛美、地吹雪ツアー……まだまだやれることはある!!イマドキの地域活性化事情
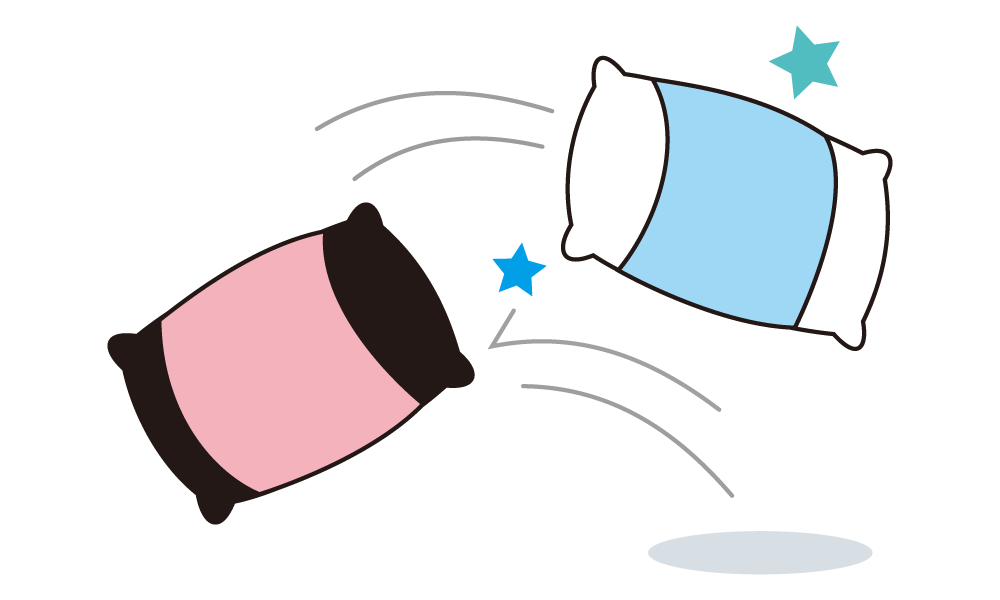
目次
■修学旅行の定番「枕投げ」を競技化。高校生が温泉街に若者を呼び込む
伊東市というと熱海市と並ぶ静岡県を代表する温泉地の1つだ。ただ人口が減り続ける日本においては、有名温泉地というだけで人を集めることは難しくなっている。伊東市も例外ではない。バブル経済前の1970年代から80年代までは、首都圏からの団体旅行・社員旅行などの観光客で賑わっていたが、バブル経済崩壊や団体旅行から個人旅行へのシフト、目的地の海外シフトなどにより、徐々に衰退していった。むろん手をこまねいていたわけではなく、地元の各産業などと連携し、イベントなどを手掛けてきた。先の東京オリンピックでは自転車競技の開催地となっている。しかしながら、温泉街にかつてほどの賑わいが戻ってくることはなかった。
そこで立ち上がったのが地元の高校生である。伊東市にある伊東高校城ヶ崎分校の生徒たちが、山形県にある芸術系大学、「東北芸術工科大学」が主催する高校生を対象にした問題解決・提案型のアイデアコンテストに、温泉街の活性化案として、修学旅行で定番化している枕投げの競技化を「枕投げのすすめ」として提案。見事準優勝を果たし、事業化が図られたのである。高校生たちは伊東市、観光協会と共に「厳密なルール」、「選手のポジション」、「競技としてのゲーム性」について議論を重ね、第1弾のルールを設計。2013年2月に晴れて「全日本まくら投げ大会」の第一回大会が開催されたのである。
できあがった「厳密なルール」は、8人1チームで、40畳のフィールドを舞台に枕を投げ合い、相手選手に枕を当てて就寝させる「ガチまくら投げ競技」で、試合時間は2分1セットの3セットマッチ。時間内により多くの選手にまくらを当てて「就寝」させるか、相手チームの大将を就寝させたチームの勝利となる。リーダーとなる「大将」、掛け布団でガードする「リベロ」、相手を就寝に追いやる「アタッカー」、自陣に枕を運び入れる「サポーター」という4つのポジションがあり、緻密な戦略と連携が勝利の鍵となる。
参加メンバーは全員浴衣着用。試合をよりドラマチックにする一発逆転の要素を持つ「先生が来たぞ〜コール」も導入されるなど、かなりゲーム性が高い。
ルールも一気に確定させたのではなく、当初は認知度アップも兼ねて首都圏の大学に声をかけて42名の大学生にモニター参加してもらい、競技としてのルールをブラッシュアップさせた。その上で第2回、第3回大会でもルールに修正をかけていった。
全日本まくら投げ大会は現在までに13回が開催され、全国から48チームが集まるほどの人気競技となっている。
高校や中学の修学旅行における夜の伝統行事が、まさか全国大会まで開かれる公式のチームスポーツになるとは……高校生のアイデアに感服である。
■温泉定番の「スリッパ卓球」が世界へ飛躍
こうした修学旅行や社員旅行といった共通体験を起点とした競技化は他にもある。伊東市のような温泉旅館街で体験できるレクリエーションの1つに卓球がある。家族連れや社員旅行の社員たちが、浴衣姿でピンポン玉を打ち合う光景はある種日本の定番風景とも言えるが、日本の文化は奥深いもので、温泉旅館ではなぜか通常の卓球ではなく、ラケットの代わりにスリッパで打ち合うという「スリッパ卓球」が各地で誕生していった。そのルーツは定かではないが、おそらく団体旅行全盛時代に、酒勢を借りたおじさんたちが、動きにくいスリッパを脱いで、なかなか思い通りに打てないラケットの代わりに持ち替えて、たまたまスマッシュが決まった、というあたりだと勝手に推測する。あるいは、ダブルスで対戦するにあたってラケットが足りないため、急遽「スリッパでいいんじゃね?」となった可能性もある。そのあたり、いろいろと想像できるのが、日本の温泉地文化の奥深いところでもある。
Wikipedia情報によると「スリッパ卓球」が本格的に世の中に知られるようになったのは、山形県河北町で1997年に催された「第1回全国スリッパ卓球大会」からとされる。同町はスリッパの生産量が全国一で、もともとはスリッパの認知・普及を目的として考案された。同町のスリッパ卓球は、使用する卓球台は卓球と同じだが、球は一回り大きく、またスリッパも持ちやすいようラケット形式の持ち手がついているものを使用する。大会は毎年行われ、2004年からは「世界スリッパ卓球大会」と銘打ち、一気にグローバル展開が図られたが、2012年を最後に途絶えていた。しかし去年河北町の町制70周年を記念し、12年ぶりに復活。7歳から79歳までの60名が参加した。同大会は今年、11月1日にも開催予定だ。温泉地発祥のスリッパ卓球大会としては、北海道の真狩村が2007年2月に開催した「まっかり温泉スリッパ卓球大会」のほうが古い。また第17回大会は、「全国スリッパ卓球大会」の第12回との併催となった。

このほかにも2012年からは山口県の湯田温泉で「湯田温泉スリッパ卓球大会」がスタート。今年3月にはめでたく第10回大会が開催された。また2010年からは佐賀県の嬉野温泉で「スリッパ温泉卓球大会」が始まっている。ただ残念ながらこの大会は新型コロナによる影響もあり、2018年の春を最後に終了している。
いずれも一般のスリッパをラケットに見立てて試合を行う、“純スリッパ卓球大会”だが、たとえば嬉野温泉の場合は、なべぶた(長崎・雲仙温泉)や温泉手形(熊本・黒川温泉)など、スリッパ以外のラケットを使った他の地域のオリジナル温泉卓球とコラボした、ご当地温泉卓球の大会も開催している。
スリッパ卓球は温泉地以外でも発生している。神奈川県では商店街を活性化しようとの目的でオール神奈川で「全かなスリッパ卓球選手権大会」が開催された。もともとは2015年に横浜市の和田町商店街が「第38回ベッピンマーケット」と一緒に開催したのが始まりで、翌2016年には横浜市の保土ケ谷区内の商店街が参加する「全ほどスリッパ卓球選手権大会」に拡大。さらに2018年には全横浜市の商店街を対象とした「全はまスリッパ卓球選手権大会」に発展、2024年には神奈川県すべてを対象とした「全かなスリッパ卓球選手権大会」にまで広がったのである。ひなびた温泉街のレクリエーションのイメージがあるスリッパ卓球だが、首都圏屈指のおしゃれ度を誇る神奈川県が最も盛んな都道府県となっているのである。今後も全国でスリッパ卓球の愛好家がじわじわと増えていくと思われる。
■「ハゲ頭を集めて暗い世の中を明るく」―驚きのスローガンとユニークイベントで話題の青森県鶴田町
「笑う門には 福来る
禿の光は 平和の光
くらい世の中 明るく照らす
日本も光る 世界も光る」
この自虐的ともとれるユニークな言葉は青森県の鶴田町のある会のスローガンである。剥き出しのエゴが世界中をきな臭くさせている現代に、実にマッチした言葉だと思うが、この言葉が誕生したのは、今から35年以上前の平成元年(1989年)のこと。同町の竹浪正造さんが、自身と同様に髪の薄い知人らに「どうせなら、もっとハゲ頭を集めて暗い世の中を明るく照らそうじゃないか」と呼びかけ「ツル多はげます会」を結成、その際に誕生したのがこのスローガンだ。

同会では、2月22日を「ツルツルの日」と制定し、この日と中秋の名月の日の年2度、その名も「有多毛(うたげ=宴)」と称する例会を行っている。中秋の名月のときには掛け軸画の満月に見立てた穴に会員が頭を入れて、その“名月”が誰かを当てる「名月当てクイズ」や各人の“磨き上げた”おでこに、綱のついた吸盤をつけて引き合う「吸盤綱引き」などが催されて話題となってきた。ほかにも目隠しをした人が禿げ頭に触れて、誰の頭かを当てるクイズや冷却ジェルシートを禿げ頭に向かってダーツよろしく投げて得点を競う「ハゲピタダーツ」などの競技がある。とくに「吸盤綱引き」はメディアで盛んに取り上げられたことから2015年には「吸盤綱引き全国大会」が開催され、以後毎年続けられている。2018年には「ツル多はげます会」が特定非営利活動法人(NPO)として認証された。さらに勢いを増した同会で2020年、同町の鶴田八幡宮に「2020(ツルツル)神社」を建てようとクラウドファンディングにも挑戦している。2020年の春の例会(有多毛)では、青森県内のほか、宮城県、山形県、富山県などから総勢40名弱が参加した。
■もはや農業界隈では常識!「田植え合コン」「稲刈り合コン」
今年は米価格の急激な上昇や野菜の不作などから農業問題が話題となった。さまざまな問題が絡む農業問題で一番の課題となっているのは担い手不足である。その対策として現在各地で農業体験や就農支援、二拠点居住の推進などの対策が行われている。こうしたなか注目されているのが、田植えや稲刈りのタイミングで行われる「田植え合コン」「稲刈り合コン」である。

群馬県高崎市倉渕町では2014年から、26歳から45歳までを対象とした「田舎DE婚活」というアウトドア型婚活イベントプログラムを実施している。地元の農家に教えてもらいながら稲刈りや稲架(はざ)掛け体験ができる「コメ婚」と、地元の人と一緒に山登りを楽しむ「山コン」、地元の食材を使ってピザやカレーづくりなどを楽しむ「カレー婚」などがあり、これまで700人ほどが参加し、約60組のカップルが成立し、6組が入籍している。
米どころの代表である新潟県の新潟市南区では、田植えを中心とした「農コン」を開催。参加者に田植え体験と交流プログラムを実施している。ほかにも熊本県では阿蘇市が地元JA協力のもと、阿蘇の雄大な自然の中で田植え体験とBBQを組み合わせたイベント「たんぼで恋活」を、長野県のJA、「松本ハイランド」では「みどりの風プロジェクト」と銘打った農業体験の婚活イベントを開催、2007年の開始以来23組のカップルが成立している。米農家以外でも野菜や果樹園農家を主体とした「農婚」は全国各地で展開されており、農業への若者、とくに女性の関心が高まっている。
最近ではこうしたイベントのほか、農家に特化したマッチングアプリも登場している。婚活アドバイザー機能のある「あぐりマッチ」や遠隔地同士のマッチングのためのオンラインデート機能がついた「Omiai」、農家に実際に嫁いだ女性が運営する「Raitai(ライタイ)」などが活用されている。
かつて都会に住む若い女性が結婚相手に求めるのは「3高」、すなわち高学歴、高収入、高身長と言われた時代において、農家、とりわけ収入の少ない米農家に嫁いで農業をする、のみならず夫の両親と同居というとそもそもNGという風潮があったが、時代は確実に変わっているようだ。とくに昨年から今年にかけての米不足や異常高温などが、その意識をさらに変えようとしているのかもしれない。
■個人宅や店、学校の水槽をネットワーク化した「まちなみ水族館」
テレビ東京の長寿人気番組「開運!なんでも鑑定団」。毎回、絵画や彫刻、書、陶器、磁器、刀剣、おもちゃなど多種多様な「お宝」が現れて視聴者を楽しませているが、1つの共通ジャンルのアイテムを集めるという行為は人種を問わない、人類固有の特性なのかもしれない。この「共通ジャンルのアイテムが集積」している地域は、地域に新しい経済効果を生み出す可能性がある。
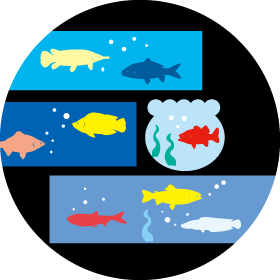
「伊予の小京都」と称される愛媛県大洲市にある県立長浜高校には、日本で唯一の、高校が部活動で運営する「長浜高校水族館」がある。この水族館はもともとあった旧長浜町立の水族館が1986年に閉館したことを機に湧き上がった「水族館再興」の思いを受けて、1999年に誕生した。この年、この町にはもう1つ水族館が生まれた。町中の個人宅や事業所にある魚の入った水槽をまとめて1つの水族館とした、その名も「まちなみ水族館」。もともとこの地域では家庭で魚を飼う文化があり、住民の7割の家庭に水槽があるという。また長浜高校の生徒の9割が入学前になんらかの魚を飼育した経験を持つ。それらの特殊事情も重なってこのユニークな水族館が誕生したのだ。観覧可能な水槽を持つ家々には「まちなみ水族館」の幟が立ち、観覧者は街なかを探索しながら個人宅の玄関や店先におかれている水族館を巡る。鮮魚店や料亭のいけすも「まちなみ水族館」の水槽の1つとなっており、店では旬の魚を積極的に展示している。食用魚の鮮度を保つためのいけすが鑑賞のための水槽となるのは、いささか抵抗を感じる人もいるかもしれないが、海洋資源に恵まれた日本ならではの「食育」としても優れている。
■全国唯一の水族館部がある愛媛県立長浜高校は、県外からの入学者がうなぎのぼり
一方長浜高校の水族館部では、毎月第三土曜日が「まちなみ水族館」の公開日となっており、毎回生徒が手塩にかけて育てている150種2000匹の魚を、部員たちが丁寧に紹介する。その取り組みが話題となって、近年は予約制にもかかわらず年間1万人もの来館者があるほどの人気スポットになっている。それだけでなく、令和に入ってからは同校への入学希望者が増加している。そのほとんどが水族館部を希望。実に全校生徒の半数以上が水族館部員で、同校の水族館部に入りたいがために、遠く北海道や東京、沖縄などから入学する生徒もいる。令和3年に2名だった県外からの入学者は令和4年が11名、5年が18名、6年が21名、7年が25名とうなぎのぼり。いかに人気でもそれだけ部員数が増えると、することがなくなる生徒もいるのではと不安にもなるが、水族館部がすべき活動は多く、水族館オープン日の案内のほか、日頃からの魚の世話、水槽のメンテナンス、生態研究、繁殖などがあり、部内にはイベント班、繁殖班、研究班、デザイン班が置かれ、それぞれ役割を担っている。
2024年春には、25周年を機に手狭になった部室から校外の長浜保健センターに移設され、スペースが3倍に広がっている。
■店頭に金魚が並ぶ大和郡山「やなぎまち商店街〜金魚ストリート〜」店舗の古い写真を展示する「前橋まちなか博物館」
大洲市の町なか点在型モデルは、ほかの自治体でも展開されており、たとえば金魚の町として知られる奈良県大和郡山市の柳町商店街では、誘客と地域活性化の一環として店頭に金魚の水槽を置いて、「やなぎまち商店街〜金魚ストリート〜」として整備、訪れる観光客を楽しませている。
また群馬県前橋市では、「前橋まちなか博物館」を2011年より展開。商店街に参加する約40店舗が古い写真をそれぞれの店頭に展示している。
棟方志功などの世界的版画家を排出した青森県青森市では、毎年同市で行われている「棟方志功版画展」に応募した小学生たちの作品を商店街のウインドウに掲示する「版画の街・あおもり 街中が版画ギャラリー」を開催している。
「昭和の町」として知られる東京都青梅市は、市内の8商店街180店舗が参加して、市内に残る昭和レトロな建造物と、それらが作る町並みを堪能できる「おうめまるごと博物館」を展開している。同市ははやくから「昭和の町」を謳い、景観を整備してきたが、集客力の高まりに乗じたイベントなども行われるようになり、さらなる活性化を目指してスタートさせた。博物館と銘打っているように、参加店舗は店の主人が学芸員としての役割も担っている。さらにこのような中で、JR東日本では、青梅駅をレトロ化する「レトロステーション」事業を実施し、JR青梅線一帯を1つのホテルに見立てた事業「沿線まるごとホテル」を展開している。沿線に点在する空き家をホテル客室に改修し、グルメや自然散策、リフレッシュなどを目的とした観光客の誘客を図っている。
いまでこそ「昭和」は全国でまちづくりのキーワードとして使われているが、その先駆けとなった大分県の豊後高田市は、もともと古いつくりの店舗が建ち並ぶ地方都市だった。商店街には人気は少なく、人より野良猫のほうが多いと揶揄されるほど寂れた状態だったが、都市部から移り住んだ玩具店主が「昭和」と「レトロ」をキーワードに町並みを残すことを提案。地元の商店街からは反発を受けたが、徐々に観光客が増え始めると協力者が増え、人口9000人ほどの市に毎年30万人が訪れるまでになった。
■過酷な地吹雪を体験する「地吹雪ツアー」に12000人
このように地元住民にとってはネガティブな遺産や環境も、観光という視点ならポジティブに捉えられる。
その代表事例の1つが1988年から青森県津軽地方で毎年行われている「地吹雪ツアー」だ。地吹雪とは、地面に積もった雪が強風で舞い上がり、辺り一面が真っ白になる雪国独特の自然現象で、とくに冬場に強風が吹く津軽地方では頻繁に起こる。ツアー参加者は角巻と呼ばれる津軽の女性の伝統的な防寒着ともんぺ、かんじきの3点セットをまとって、強風で視界がホワイトアウト状態のなか、ガイドに先導され1時間30分歩く。地吹雪は地元の人にとってはやっかいこの上ない気象であるが、地吹雪を知らない都市部の人にとっては貴重な価値ある体験となるようで、累計で約12000人が体験している。

ほかにもこうしたネガティブ、あるいはマイナスの環境や遺産などを観光資源として活用し、地域の活性化に繋いでいる例はまだある。
炭鉱閉山後の無人島となった廃墟として知られる長崎県の「軍艦島」は世界文化遺産に登録後、「廃墟ツーリズム」の代表として人気を博すようになったのはご存知の方も多いだろう。
■ダムなどのインフラツアー参加者が急増
各地のダムも注目を集めている。もともとダムマニアなどコアなファンがいるダムだが、とくに秘境ダムは人気が高まっている。代表的ダムは映画にもなった富山県黒部市の黒部第四ダムで、観光シーズンが限られているにもかかわらず、年間100万人が訪れている。黒部第四ダムほどではないものの、福島県と新潟県にある秘境ダム「奥只見ダム」には、毎年約60万人が訪れている。
こうした秘境ダムは一帯の景観の素晴らしさが人気の背景にあるが、アクセスの不便さや完成までが難工事の連続であったことなども要因の1つとなっている(黒部第四ダム、奥只見ダムの工事では多くの作業者が犠牲となっている)。
またダムやトンネル、橋梁などインフラを巡るインフラツーリズムについては、国交省や自治体などの支援策や民間業者によりコンテンツ化が進んだこともあり、民間業者が手掛けるツアーだけでも2016年に32件だったものが2019年には140件に激増している。
地域活性化というと、おしゃれグルメや大きなイベントに目が向きがちだが、一見知られたくない、ネガティブな環境やできごとも、視点を変えれば十分な観光資源、地域活性化の種になる。まずは日常の風景や慣習を別視点で見ることから始めるといいだろう。まだまだやれることはあるはずだ。
参考
【参考レポート】●経済産業省「街元気・まちづくり事例集 -新たな雇用と投資の喚起をめざして-」 ●国土交通省「インフラツーリズム」 ●レポート「長高水族館」を核とした総合的な理科教育の展開(愛媛県立長浜高等学校 松本浩司)ほか
【Web】●中小企業庁 ●サイネックスマガジン ●デザセン ●卓球王国 ●北海道ファンマガジン ●真狩村 ●鶴田村 ●公式 ツル多はげます会 ●メデタイ・ツルタ ● UAJAPANRECORDS ●湯田温泉公式サイト ● https://www.slipper.yokohama/ ●上毛新聞電子版 ●自治労公式サイト ● Value Press ●社団法人セブン- イレブン記念財団 ●地域NEWS 号外NET ピックアップ! 青森 ●群馬県 ● https://tierzine.com ●超えて、行こう 地域みらい留学 ●愛媛県生涯学習センター ●大洲市●愛媛県立長浜高等学校 ● PR EDGE ●郡山柳町商店街協同組合 ほか
ビジネスシンカーとは:日常生活の中で、ふと入ってきて耳や頭から離れなくなった言葉や現象、ずっと抱いてきた疑問などについて、50種以上のメディアに関わってきたライターが、多角的視点で解き明かすビジネスコラム