「修理することは現代人の権利だ!」AI、デジタル化時代に広がる「リペアエコノミー」とは?
スマートフォンのバッテリーが劣化しても自分で交換できない。農機具が故障しても、メーカー認定の修理業者しか直せない―そんな不満から生まれた「修理する権利(Right to Repair)」運動が、いま世界中で熱を帯びている。新たな消費者保護運動か、それとも懐古主義の一環か―その背景にあるのが循環経済の要として注目される「リペアエコノミー」だ。その最前線では、地域コミュニティが主導する「リペアカフェ」から、自動車や電子機器の修理権利を認める法律の制定や、企業が戦略転換を迫られるなど、多様な変革が進行中だ。この新しく、かつ大きなうねりは、グローバル企業がデジタル支配を強めるなか、所有と使用の概念を問い直している。
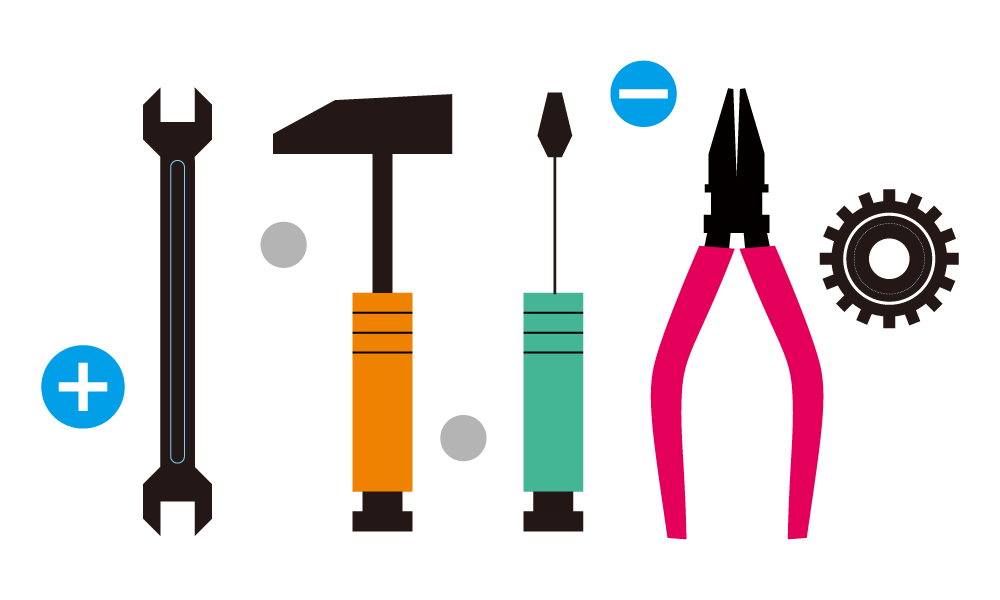
目次
■アメリカ農民の反乱から始まった「修理する権利」
アメリカ中西部の広大な農地では、ある問題が深刻化していた。最新鋭の農業機械は高度にデジタル化され、故障してもメーカー以外が修理できないことになってしまったことだ。農家は不満を募らせた。メーカーに連絡しても、認定修理業者が何百kmも離れているため、すぐやってこない。場合によって到着するまで数日から数週間もかかることもある。収穫期に機械が止まれば、農家は莫大な損失を被ってしまうが、ブラックボックス化した機械は下手にいじれば、さらなる故障を招きかねず、保証から外れる可能性もある。自分で購入した自分のための農業機械なのに、自分で修理することもできない。なぜだ─。
■「自分で買った機械なのに、自分で直せない」
この矛盾に立ち上がったのが、世界最大の農機具メーカー、「ジョン・ディア」のトラクターを所有する農民たちだった。2010年代後半から、彼らは修理マニュアルの公開と診断ツールへのアクセスを求めて声を上げ始めた。メーカーが対応を渋ると怒りはヒートアップ、東欧で違法に流通する「脱獄」ソフトウェアを使ってトラクターの制御システムをハッキングするという、異例の事態にまで発展したのだ。
やがてこの動きは「Right to Repair」、すなわち「修理する権利」運動として全米に広がり、2025年には全米50州でこの関連法案が提出されるまでとなった。既に2025年半ばまでに5州で6つの異なる法案が可決されている。
コロラド州は最も州政府の反応が早く、2023年に全米で初めて農業機器の修理権を法制化した。するとこれを皮切りに、カリフォルニア州、ニューヨーク州など複数の州が、農機具のみならず、スマートフォンからノートパソコン、家電製品まで幅広い製品を対象とした法律を制定したのだ。

この運動の背景にあるのは、製品の「デジタル化」と「ブラックボックス化」だ。現代の製品は複雑なソフトウェアで制御されており、メーカーは修理に必要な診断ツールや技術情報を独占することで、修理市場を囲い込んできた。消費者や独立系修理業者には、修理の「物理的な能力」があっても、「法的・技術的なアクセス権」が与えられていなかったのだ。
■4,630億ドルの巨大市場、リペアエコノミー
アメリカの「修理する権利運動」の高まりは消費者たちの怒りが突き動かしたわけだが、背後には、巨大な経済圏に対する主導権問題が存在する。
カナダの調査会社Precedence Researchによれば、世界の循環経済市場は2024年に4,630億ドルに達し、2025年には5,178億ドルへと成長する見込みだ。この中で、修理・リペアは中核的な位置を占める。
電子機器修理市場だけでも、2024年時点で1,426億ドルの規模があり、2030年までに2,189億ドルに達すると予測されている。年平均成長率は7.4%。スマートフォン、タブレット、ノートPCといった身近な製品から、産業用機器まで、あらゆるデバイスが修理の対象となる。
さらに注目すべきは、「予測メンテナンス(Predictive Maintenance)」市場の急拡大だ。AIとIoTを駆使して機器の故障を事前に予測し、最適なタイミングで修理・交換する技術である。この市場は2024年の106億ドルから、2029年には478億ドルへと、年平均35.1%という驚異的な成長が見込まれている。
さらにアパレル産業では、「アップサイクリング」や「リペアファッション」が新たな潮流となっている。アップサイクリングファッション市場は2024年の82億ドルから、2032年には167億ドルへと倍増する見通しだ。
こうした修理の関わるマーケットは「リペアエコノミー(Repair Economy)=修理経済」と呼ばれ、これらの数字が示すように単なるニッチ市場ではなく、サステナビリティと経済合理性が交差する巨大なビジネスマーケットとなっている。消費者は環境意識の高まりから修理を選択し、企業は長期的な顧客関係構築とコスト削減のために修理サービスを強化する。法規制と市場原理が、修理経済の成長を後押ししているのだ。
■地域が紡ぐ修理のコミュニティ─オランダ発「リペアカフェ」
リペアエコノミーを語る上で欠かせないのが、「リペアカフェ」という草の根の動きだ。
2009年、オランダのアムステルダムでジャーナリストのマルティーネ・ポストマさんが始めたこの取り組みは、壊れた物を持ち寄り、ボランティアの修理職人と一緒に直す無料のコミュニティイベントだ。彼女の「捨てる前に、直してみよう」という単純だが力強いメッセージは、瞬く間に世界中に広がり、現在、リペアカフェは世界40カ国以上、約3,275カ所で運営されている。発祥の地オランダには500カ所以上が存在し、国民の間に修理文化が根付いている。2024年だけで、世界中のリペアカフェで記録された修理件数は37,000件を超えている。
興味深いのは、その「成功率」。リペアカフェで持ち込まれた製品の修理成功率は、過去15年間の平均で約53%。低く思えるかもしれないが、これは「もう捨てるしかない」と諦めかけた製品の半分以上が蘇るということを意味する。修理できなかったケースでも、参加者は故障の原因を学び、次回の購入時により修理しやすい製品を選ぶ知識を得られる。つまりリペアカフェの魅力は、単なる「修理サービス」ではなく、「学びと交流の場」であることだ。参加者は修理職人の技術を間近で見て、自らも手を動かす。世代を超えた知識の伝承が自然に起こり、地域のつながりが生まれる。高齢者の修理職人にとっては、長年培った技術を活かせる「役割」の場でもある。
オランダ政府は、このリペアカフェを循環経済政策の一環として積極的に支援している。自治体が会場を提供し、企業が工具や部品を寄付する。修理を通じて、廃棄物を削減し、資源効率を高める。国家戦略と草の根活動の見事な融合である。
■日本の静かな変革、広がり始めたリペア文化

一方、日本。実は日本には、世界に誇る「修理文化」の伝統がある。その1つが「金継ぎ」だ。割れた陶器を漆で接着し、金粉で装飾する修復技法は、破損を隠すのではなく、むしろ美として昇華させる日本独特の美意識の体現として、日本を訪れる外国人観光客にも人気となっている。包丁研ぎ、畳の表替え、着物の仕立て直しなど、金継ぎに限らず、「長く使い、手入れし、直す」という価値観は、かつての日本人の生活に深く根付いていた。
だが高度経済成長期以降、大量生産・大量消費の波の中で、こうした文化は急速に衰退してしまった。「直すより買った方が安い」という経済合理性が、職人の技術継承を困難にし、「修理インフラ」を縮小させた。
ところが近年、この流れに変化が現れている。インバウンドの拡大によって金継ぎをはじめとした日本の修理文化が世界中から注目されるようになったほか、日本でもリペアカフェの動きが広がりつつあるのだ。
京都府亀岡市、茨城県水戸市、東京都内の複数の地域で、定期的にリペアカフェが開催されている。2024年12月には日本経済新聞が「『お直し文化』令和に復活の兆し」と題する記事で、日本各地で修理イベントが大盛況となっている様子を報じている。またテレビでも、テレビ東京系が、壊れて直すことを諦めた者を腕利き職人が“お直し”をしていく「お直しJAPAN」、それを世界で展開する「世界!職人ワゴン」などを放送している。YouTubeにも相当数のリペア動画が投稿されており、さらに2025年9月27日には、大阪・関西万博会場で開催された「サーキュラーエコノミー研究所」イベントにおいて、オランダのリペアカフェを取材したドキュメンタリー映画『The Repair Cafe』が上映された。
日本の企業も動き始めている。パタゴニアは東京・渋谷に修理専門店「Worn Wear」を開設し、自社製品の無償修理サービスを提供。無印良品は衣類の刺繍や染め直しサービスを展開し、「愛着のある服を長く着る」文化を提案している。
■文化の違いが生む、修理への「距離感」
着実に広がりを見せるリペアカフェだが、欧米と日本では、大きな違いがある。日本の場合、オランダのような「DIY精神」よりも、「職人の技に学ぶ」という姿勢が強い。参加者は修理職人の手さばきを敬意を持って見守り、「こんなに丁寧に直してもらって申し訳ない」と恐縮する。これは、日本人の「職人文化」への尊敬と、「自分でやるより専門家に任せる」という意識の表れだ。
この意識の差はアメリカの修理する権利運動からも読み取れる。アメリカはヨーロッパからの移民が「開拓」の名のもとに国家形成されていった歴史があるため、極めて「個人主義的」な国家文化を持つ。「自分の所有物は、自分で好きに扱う権利がある」という、所有権の絶対性が根底にある。農民がトラクターをハッキングするのも、「俺の機械だ。メーカーに指図される筋合いはない」という強い自己主張の表れの1つだ。
またオランダのリペアカフェも、「自立」と「自己効力感」を重視している。参加者は修理職人に教わりながら、自分の手で物を直す。その経験を通じて、「自分にもできる」という自信を得る。個人の能力とエンパワーメントを重視する、北欧的な価値観と言える。
一方、日本のリペアカフェは、より「共同体志向」だ。修理職人は「地域の知恵袋」として尊敬され、参加者は「助けてもらう」関係性を受け入れる。そこには、「自分ですべてを解決する必要はない。困ったら助け合う」というコミュニティの相互扶助の精神がある。
この違いは、製品設計にも影響する。アメリカやヨーロッパでは、「修理しやすさ(Repairability)」が製品評価の重要な指標となりつつある。フランスでは2021年から、電子機器に「修理のしやすさ」を10点満点で表示する制度が導入された。消費者は購入時に、修理コストや修理の難易度を考慮できるのである。
対して日本では、「故障しない高品質」が製品価値の中心だ。その代表が自動車や家電製品である。また過酷な条件のもとでもパフォーマンスを維持する重機や工作機械も同様だ。日本企業は「壊れない物を作る」ことに心血を注いできた。修理は、いわば「敗北」の印であり、メーカーとしては避けたい事態なのだ。
この文化的な違いは、今後のリペアエコノミーの展開に大きな影響を与えそうだ。欧米型の「個人がDIYで修理する」モデルと、日本型の「職人が修理サービスを提供する」モデル。どちらが優れているというわけではなく、それぞれの社会に根付いた価値観に基づいた形がある。
■「おもてなし」と「DIY」―2つの修理哲学
日本企業の修理サービスを考えるとき、その特徴は「おもてなし」文化が色濃く反映されている点に表れる。
例えば、日本の「アップルストア」の修理カウンター、「Genius Bar(ジニアス・バー)」を訪れると、スタッフは懇切丁寧に故障の原因を説明し、修理オプションを提示してくれる。これは海外のジニアス・バーにはない対応だ。海外でも対応はきめ細やかだが、日本のような「おもてなし文化」に則した接客は見られない。顧客は「お客様」として扱われ、修理作業は専門家に一任する。この「任せる」関係性は、日本人にとって心地よい。「自分で分解して直す」よりも、「プロに任せて安心」という価値観だ。
一方、対照的なのがアメリカの修理コミュニティサイト「iFixit」だ。「誰でも修理できる」ことを謳うiFixitでは、スマートフォンからノートPCまで、あらゆる製品の詳細な修理ガイドが無料で公開されている。ユーザーは自分で部品を購入し、動画を見ながら修理に挑戦する。失敗しても、それは学びの一部となる。
この対比は、製品やサービスの発想の違いを浮き彫りにする。とくに特徴的なのが日本の製造業で、「垂直統合」と「すり合わせ」を得意とし、部品から完成品まで一貫して設計し、最適化する。その結果高性能だが、分解・修理が困難な製品が生まれる。対して、アメリカ企業は「モジュール化」と「標準化」を好む。部品を交換可能にし、ユーザーが自由に組み替えられる設計にするのだ。
どちらが「正しい」かではなく、どちらが社会に受け入れられるかだ。ただグローバル市場では、「修理可能性」が新たな競争軸になりつつあることは間違いない。
既にパナソニックは2022年、欧州向け家電製品に「修理しやすさスコア」を導入した。部品の入手性、分解の容易さ、修理マニュアルの充実度などを評価し、消費者に開示する。これは、EUの規制対応でもあるが、同時に「長く使える価値」を訴求する戦略でもある。
またダイソンは、掃除機の修理サービスを充実させることで、顧客との長期的な関係を構築している。修理時には最新モデルの試用を提案し、アップグレードの機会を創出する。修理は、単なるコストではなく、顧客接点としての価値を持つ。
トヨタは、コネクテッドカーから収集する走行データと修理履歴を統合し、故障予兆を検知するシステムを開発している。データを抱え込むのではなく、ユーザーに開放し、事前に部品交換を促すことで、突然の故障を防ぎ、安全性と顧客満足度の向上につなげている。

■AI時代の「所有」と「使用」を問い直す
リペアエコノミーは、私たちに根本的な問いを投げかけている。
「所有する」とは何か。「使用する」とは何か。そして、「捨てる」とはどういうことか。
デジタル時代、私たちは「所有」しているようで、「使用権」を買っているだけかもしれない。スマートフォンのソフトウェアは自動更新され、クラウドサービスの規約は一方的に変更される。自分の「物」であるはずなのに、自分の意思で完全にコントロールできない――これは、所有概念の根本的な変容だ。
修理する権利運動はこの変容に対する抵抗だ。
一方で、AIの進化は、修理のあり方そのものを変えつつある。膨大な修理データから最適な修理手順を導き出し、AR(拡張現実)グラスを装着すれば遠隔地の専門家が、映像を通じて修理をサポートすることも可能となる。専門知識がなくても、誰もが高度な修理に挑戦できる時代が来るかもしれない。あるいは、AIロボットが自動で修理する未来もあり得る。
だがリペアカフェの広がりが示唆しているのは、修理は単なる「機能回復」ではないということである。それは、物との対話であり、世代間の知識伝承であり、地域コミュニティの絆でもある。壊れた時計を直す過程で、祖父の思い出がよみがえる。ほころびたセーターを繕いながら、子供に「大切に使う」ことを教える。
修理とは、物の寿命を延ばすだけでなく、私たち自身の「時間感覚」を取り戻す行為なのかもしれない。大量生産・大量消費の時代、私たちは「新しいものを買う」サイクルに巻き込まれ、物との関係が希薄になった。修理は、その関係性を再構築する。
リペアエコノミーは、環境問題への解答であり、経済的な合理性であり、そして何より、人間と物との関係を見つめ直す文化運動でもある。
日本には、「もったいない」という美しい言葉がある。それは単なる節約精神ではなく、物に宿る価値や、それを作った人の労力への敬意だ。この精神が、現代の修理文化と結びつくとき、日本独自のリペアエコノミーが花開くだろう。
参考
● Farm Action「Right to Repair Campaign」● NBC News「The right-to-repair movement is growing」● Repair Café International ● Forbes Japan「リペアカフェ」●日本経済新聞「お直し文化令和に復活」● AMP Catch the business inspirations. ● MarketsandMarkets「Predictive Maintenance Market」● McKinsey「Circular Economy」● ifixit ● precedence research ●欧州委員会「Right to Repair 指令」●経済産業省「循環経済政策」 ほか
ビジネスシンカーとは:日常生活の中で、ふと入ってきて耳や頭から離れなくなった言葉や現象、ずっと抱いてきた疑問などについて、50種以上のメディアに関わってきたライターが、多角的視点で解き明かすビジネスコラム