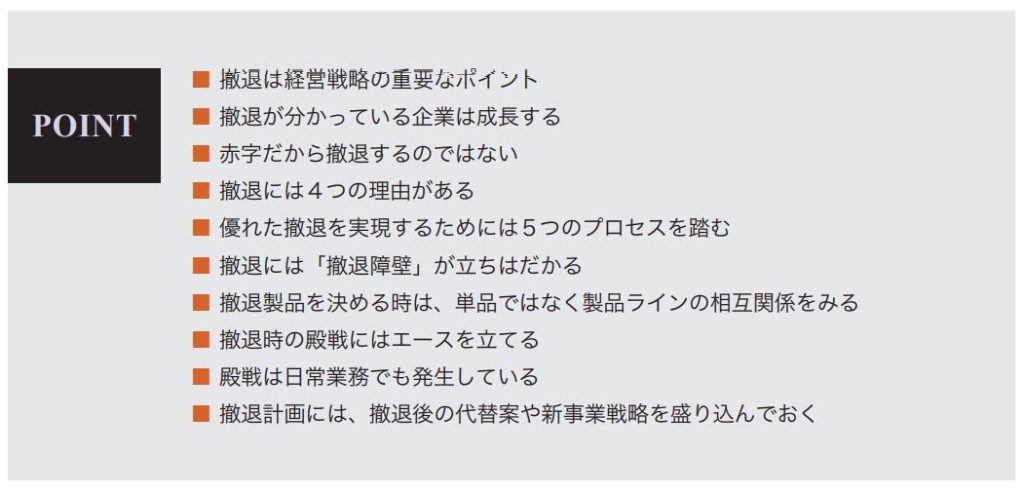撤退と殿戦(しんがりせん)の研究
コロナ禍やロシアのウクライナ侵攻、カーボンニュートラル対策、急激に伸張するメタバース市場、止まらない円安、各国の利上げなど、目まぐるしく変化するビジネス環境に柔軟に適合していくには、製品や事業の可能性を見極め、柔軟なプランを描く必要がある。しかしプラン通り行かないのが昨今のビジネスだ。時に大胆な撤退も必要となる。しかも俊敏に。
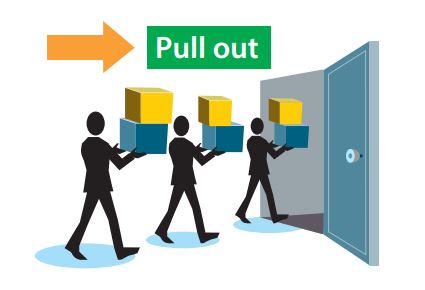
ビジネスでの撤退は難しい。よくビジネスは戦争にたとえられるが、実際の戦いにおいて最も難しいのが撤退の見極めと決断だとされる。
もとより、動物は本能的に戦うべき相手を読み取り、無駄な戦いをしなかった。相手が手ごわいと認めたら、まず逃走して自己の生命を守り、捲土重来を期する。
実際歴史上の名知将や参謀と呼ばれる人々の多くは、無駄な戦いを避け、適切な撤退を実践してきた。ところが現代の人間は、負けを認めたり、逃げることは格好悪い、恥ずべきことと教え込まれているせいか、戦況が悪化しても踏みとどまり、壊滅してしまうことも少なくない。個人の戦いならいざ知らず、企業の場合は、その判断を誤ると会社そのものが消えかねない。
『戦略的事業撤退』を著したコンサルタントの日沖健さんによれば、「企業が発展していくためには、撤退は避けられない」という。
「多くの企業では事業を始めて何年、何十年と経つうちに事業環境が変わる」ので、当初想定した状況からかけ離れていく。基盤となる技術が陳腐化したり、顧客の嗜好が変わったり、法律や業界のルールが変更されたり、強力なライバルが現れるなどして顧客が離れ、設立した目的や使命は色あせてしまう。
日沖さんによれば、この際に企業が取る選択肢は2つあるという。
1つは企業を解散させること。もう1つは新たな事業分野を見つけ出して、新たな目的、使命を掲げて事業を続けることだ。現実的には1つの事業が立ちいかなくなったからといって、企業を解散させることは難しい。多くの企業は後者を選択することになるが、解散するにせよ、新たな事業分野を見つけるにせよ、既存事業の撤退は避けて通れない。
長寿企業の多くの企業はこの撤退と参入を繰り返しながら成長発展を続けてきた。
日沖さんは「一流であり続けるには、伝統ある事業であっても聖域なく、撤退の対象になる。不要な事業からの撤退によって、事業ドメインを明確にし、世界的に競争力のある分野に資源を集中させている」と語っている。
日本においてはバブル経済の崩壊までは、撤退を考える必要はなかった。市場が黙っていても成長し続けていたからだ。しかし日本はだいぶ前に人口減少社会に入り、国内市場だけではパイは広がってかない。日本全体の国際競争力も下がり続け、消費者のライフスタイルも変わってしまった。めまぐるしく変わる経営環境の変化に対応するためには、的確な撤退を判断し、そこで得た、あるいは守った資源を新たな分野に回すことが極めて重要になる。
では適切な撤退はどのように判断し、実行するべきなのか。その前に撤退にはどのようなケースがあるのだろうか。
目次
撤退を決定づける4つの理由
日沖さんによれば撤退は4つの理由で行われるという。
1.需要減退による撤退。
2. 競争に敗れての撤退。
3. 事業ドメイン構築のための戦略的撤退。
4. 事業使命の終了などによる撤退。
1つ目の需要減退はメーカーにはつきものだ。というのも製品にはライフサイクル、すなわち寿命があるからだ。一般に製品は、導入から成長し、成熟期でピークを迎えて、衰退する。しかしこの山は一様ではない。産業や製品によって違う。パソコンや携帯電話、録音機器などのハイテク機器はサイクルが短く、しかもピークを迎えた後の衰退が早い。場合によっては成熟期がなく終わってしまうこともある。これに対してたとえば生活必需品などの場合は成熟期が長く、いわゆるロングセラーなどを生み出すケースが多い。このライフサイクルの波をどう読むかが撤退のポイントになってくる。
2つ目の競争に敗れての撤退は、文字通り、競合相手にシェアなどで優位に立てずに撤退するパターンだ。一般に1つの市場ではシェア42%が安定目標値とされ、強者の立場を維持できると言われている。しかし近年さまざまな分野での規制緩和や自由化が進んだことで、外資や異業種などの「想定外」の敵が現れ、市場をかく乱、シェアを奪われたりする。
やっかいなのは事業参入したはいいものの、長年利益が出ずに、じわじわとシェアを後退させているパターン。過去の投資や投入した人材と時間が重荷となり、なかなか撤退できずにいるケースがよく見られる。またなまじ事業部門の人間が少しでも収益を上げようと懸命に努力する姿を見てしまっているので、あっさりと撤退とは言いだせない経営者もいるだろう。もちろん将来状況が好転する可能性があるのなら別だが。
日沖さんによれば、勝ちパターンになるキーファクター(KSF=KeySuccess Factor)が維持できるか、あるいは将来獲得できることが撤退の大きな判断材料となるという。ということは「逆に赤字でも、将来KSFが獲得できる見込みの高い事業であれば、簡単に撤退してはならない」(日沖さん)のだ。
3つ目の事業ドメイン構築のための戦略的撤退は、自社の存在意義にかんがみての撤退。欧米の企業では需要があり、一定の競争力がある事業でも、自社の事業ドメインから外れたものであれば、撤退を決断するときがある。あるいは企業理念になじまない事業を撤退させる時がある。たとえ収益が上がっていたとしても、だ。
戦略的撤退を実践し、業績を飛躍させた武田薬品、キヤノン
従来事業ドメインを意識した撤退のあり方は日本企業では少なかったが、近年戦略的に撤退する企業も増えている。
たとえば武田薬品工業。同社は2007年に調味料などの食品素材事業をキリンビールに約100億円で売却している。機能性食品やサプリメントなどの市場性を考えれば今後十分成長できる要素をもっていたが、製薬会社としての事業ドメインに集中するべく、売却を決めたとされている。
撤退の見事さでは、キヤノンが有名だ。
キヤノンは会長と社長を務める御手洗富士夫さんが、一度目の社長に就任して間もない1997年、当時の事業の柱であり、IT社会の担い手になるパソコン事業からの撤退を表明したのだ。すでにパソコン事業は20年にわたる実績があり、社内からの反発はすさまじいものがあった。
当時はゼロックスの特許で付け入る隙のないほど抑えられていたコピー事業に参入し、ゼロックスの特許に抵触しない独自技術でコピー市場を制覇した矢先。社員の誰もが自社の独自技術に酔っていた頃だった。その判断に多くの社員が抵抗したのも無理からぬこと。幹部や技術者のなかには、「命を賭けてやってきた」と涙ながらに訴える者もいたという。しかし御手洗さんは、ITは進化発展することは重々承知の上で、いずれパソコンは単なる箱となり、コンテンツや通信が主戦場となるだろうと踏んでいた。米国生活の長い御手洗さんならではの先見性と判断だと言えばそれまでだが、こうした判断はグローバル企業に限らず、ドメスティックな中小企業にも求められてくる。
4つ目は、事業そのものの使命が終わったことや、オーナーが事業継承の意欲をなくしたりするケースだ。近年は目的事業会社や協同組合など、ある目的のための時限的な事業主体が現れているが、これらもこの4つ目の撤退事由に含まれる。
GEのジャック・ウエルチは、「選択と集中」ではなく「峻別と撤退」を行った
いずれにしても、これからの企業経営者はこの4つの理由を使い分けながら、撤退を図っていかなければならない。ではどのように撤退すべき事業を決めればよいのだろうか。
近年経営戦略については、資本を集中させるべき事業と、そうでない事業を分ける「選択と集中」という考え方が浸透してきた。選択と集中では、アメリカのゼネラルエレクトリック (GE) のCEOだったジャック・ウエルチの取った策が有名だ。発明王エジソンを創業者に持つGEは、1世紀以上もの歴史のなかで、事業を拡大し続け、家電から原子力、金融まであらゆる事業を展開する巨大コングロマリットになったが、高い収益を上げている事業はなく、無駄が蔓延していた。
ウエルチが示した選択基準は明快だった。その市場において1位か2位でなければ、その事業を撤退させるというもの。この基準で彼は200以上の不採算部門を撤退させている。日沖さんは著書のなかで「これからは選択と集中ではなく、峻別と撤退の時代だ」と述べているが、ウエルチが行った大胆な策こそ、峻別と撤退だと言えるだろう。
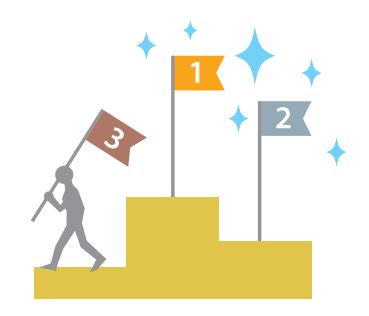
今を分析して将来を予測しない
ただ日沖さんは、現在だけを見て儲かっていないから撤退するというのは、間違いだという。実はウエルチも、その時点での判断だけでなく、一定の改善策を講じたのちに判断している。
また近年経営戦略の指標として取り入れられているポートフォリオで事業の撤退を判断すべきではないと言っている。ポートフォリオは、事業を成長性と市場占有率からゾーン分けをして事業判断するツールで、ボストンコンサルティングが作り出したものが有名だ。このポートフォリオのゾーニングで市場シェアの低い、成長率の低いゾーンにいる事業は「負け犬」なので、いち早く撤退すべきという判断がなされる例が多いようだ。
あるいは事業計画の段階で営業利益が3年連続赤字だから、シェア10%を切ったら撤退などと自社基準を決めているところもあるだろう。
市場が低成長だから撤退せよ、自社のシェアが低いから撤退せよというコンサルタントがいるが、事業の撤退か継続かはそれほど簡単なものではないというのが、日沖さんの主張だ。では何を基準にしていけばいいのだろうか。
日沖さんが挙げているポイントは「未来」だ。つまり成長性である。ポートフォリオにも成長性という軸はある。しかしここで表現されている成長性とは、過去のデータから導きだされたもの。参考にするのはいいが、そのまま結論を出すと自社の未来を歪めかねない。
最近ではEVA(税引き後営業利益=経済的付加価値)という投資した金額に対しての付加価値を年度ごとに測る方式がよく経営指標で用いられるようだが、この方法だと初期の段階はマイナスが続く可能性が高いので、成長性が期待できないとされて、新規事業が育たなくなってしまう。逆にEVAの数値がよくても、過去の数値が良かったために見せかけの数字がよく見えてしまうだけで、実体は優良事業でない場合もある。
そこでEVAを数年度分足し合わせたMVA(市場付加価値)という計算式で将来の市場価値を図る方法
もある。M&Aに用いられるデューデリジェンスとして知られるが、ただ先が読みにくい環境においては、プラスで予想しても環境変化によりマイナスになる可能性がある。
最適な撤退を実現する5つのプロセスポイント
未来の成長性は、誰も正確に見極めることはできない。と言ってしまうと元も子もない。でも絶対的なものではないものの、未来を測って撤退を判断する手法はある。日沖さんはおよそ次のようなプロセスを挙げている。
1) 事業評価 ―自社の経営資源、ライバルの動向を現状評価し、何もなかった場合自社の事業がどうなるかを予測する。
2) 企業理念・経営ビジョンの策定・見直し―事業評価に基づいて、自社の企業理念・経営ビジョンを見直す。
3) 定性的な選別=事業ドメインの仮説構築 ―1)と2) に基づいて事業ドメインを仮説構築し、事業ドメインに入る事業と外れる事業を選別する。
a) 企業理念・経営ビジョンによる選別 ―目標とする企業理念・企業ビジョンと合う事業、合わない事業を選別する。
b) ケイパビリティ( 競争力のある組織能力) による選別。
c) シナジーによる選別 ― 事業ドメイン全体のまとまり、事業間のシナジーという観点から、事業ドメインに合う事業と合わない事業とを選別する。
4) 定量的な選別=コストベネフィット分析―撤退に伴うキャッシュフローの変化を定量的に推計し、事業ドメインの仮説を検証する。キャッシュフローを最大化するよう選別する。
5) 撤退事業の決定―1)~4)の整合性を検証して、撤退する事業と残して育てる事業を決定する。
ちょっと概念的で難しい感じがするが、ポイントは手をこまねいたままだったらどうなってしまうかを可能な限り予測すること。仮説力が問われるところだ。そして、撤退した場合と撤退しなかった場合の、市場や自社の財務、社員のモチベーション、技術資産などを細かく比較検討することである。
マーケティングの神様、コトラーの製品撤退論
一方、個々の製品のマーケティングについては、かのマーケティングの神様、フィリップ・コトラーがだいぶ前に「撤退のマーケティング戦略」について語っている。
コトラーは、製品の撤退がなぜ重要なのかについて、企業の経営者は既存製品の撤退より、新製品の追加のほうがたやすいと考えがちであることを挙げ、その結果、経営陣が考えるべき問題の範囲が“幾何級数的に”拡大し、対応が回らなくなると述べる。製品数が増えても資源の拡大が十分でなくなることが多いからだ。とくに製品数が増えれば、その維持管理コストは増えていく。とりわけ在庫はいかに適正にしたとしても場所は取るし、精緻な予測を立てても、今回のコロナ禍のようにマーケット変化が激しい場合は、その管理は予想通りとはいかない。
実際今回のコロナ禍では、製品や事業の撤退、業態変更、倒産が相次いだ。
コトラーは、撤退すべき製品を抽出し、速やかに実行するための「撤退プログラム」を描いている。
データ・シートで製品の峻別をし、製品評価フォームで継続指数を出す
コトラーの撤退プログラムは、どの製品を撤退させるかの手順の「構築段階」と構築したプログラムを運用する「運用段階」から成る。
構築段階では、まず製品再検討委員会を設置する。そして製品の取捨選択の基準、生産を止めた場合の影響、余剰となった資源の再配置などを考えていく。委員会のメンバーは会社の各部門から参加させるが、内々では客観的な判断が難しくなるため、外部のコンサルタントなどを参加させる。
運用段階では、まず取捨選択のための製品ごとの「データ・シート」をつくる。データ・シートには、例えば以下のような項目が立てられる。
①業界平均の売上高
②当社の売上高
③単位あたり総コスト
④販売量
⑤価格
⑥単位あたりの変動費
⑦間接費負担率
直近数カ月の在庫量やシェア、ベンチマークとなるライバル製品のシェアや販売量、単位あたりコスト(社員数や原料などから想定)など独自項目を立てて、より精緻化するといい。
このデータ・シートでの判断は2段階とし、いきなり取捨選択をするのではなく、最初は再検討すべき製品を選び出し、その上で製造を中止するものを選ぶ。コトラーによれば、データ・シートの目的は「強い製品」と「弱い製品」を分けることにあるとする。
そして分けた「弱い製品」を判断チャートで分けていく。判断は次のようなポイントで分けられる。
① 当該製品は総売上において一定(K)期間以上シェアが下がっているか。
② 季節変動を調整した後、一定(K)期間以上シェアが下がっているか。
③ 市場シェアは一定(K)期間以上、連続してシェアが下がっているか。
④ 粗利益率は一定(K)期間連続で下がっているか。
⑤ 間接費負担率は一定(K)%より少ないか。
いずれもK(定数)が決まれば、機械にYes / Noで判断できるので、プログラム化しやすいし、エクセルなどでも組める。
撤退候補は、こういった比較的単純な振り分けができるが最終的に撤退すべきかの判断には、個々の製品の評価が必要となる。企業の製品はすべてが等しく重要ではない。したがって評価については製品ごとに加重することが必要になってくるのだ。
コトラーはそのために「製品評価フォーム」なるものを提案している。製品評価フォームにはいくつか評価項目を設定するが、コトラーが推奨するのが次の7つだ。
①製品のポテンシャル
② 製品の改良によって得られる利益
③ マーケティング修正によって得られる利益
④撤退がもたらす経営陣の時間
⑤ 代替品によって得られるチャンス
⑥ 製品の直接費負担を超える貢献度
⑦他製品への売上貢献度
これらの項目について、最大1として、0から0.1刻みで評価を記入していく。A商品のポテンシャルは、0.8だが、B商品は0.5といった具合に。いずれも担当者や経営陣らの個々の感覚値に頼る部分があるが、複数の記入者が関わることでより公平な判断につながる。これらの項目では④が出色だろう。最大資源である時間、しかも経営を左右する経営陣の時間をどれだけ取れるかは、企業の未来を大きく左右することだ。製品評価フォームの各項目を足し合わせて出た数値が「継続指数」となる。最高は7。つまり最高7ポイントで1しかない製品はその製品の将来性は極めて暗いとなる。もちろんこの継続指数の項目は5つでも20個でもいい。項目数が多ければその分だけ評価は精緻化するが、作業は煩雑になる。
継続指数は、明快で撤退の判断基準となるが、コトラーはこれをもって撤退の判断とすべきではないとしている。
製品ラインの相互関係をみていく
一般的に1つの製品は、製品ラインのなかで需要や原材料、技術などで相互に連関しており、個別の継続指数だけで判断すると一連の製品ラインごと撤退すべきという判断もあり得る。
その場合は、自社製品の市場でのポジションを著しく弱めることにもなる。また残った設備が遊休状態になるためかえってコストがかかってしまうこともある。したがってその製品との相関を検討する必要がある。
よってある製品が撤退の対象になった時には、そのカテゴリは残す方向で製品の組み合わせを考えなければならない。また発売間もない製品である場合は、仮に撤退したとしても、アフターサポートや交換部品の在庫期間を設定する必要もある。一気に撤退ではなく、段階的な撤退計画も必要だ。
したがって撤退には、こういった点を考慮する必要がある。
コトラーは以下のポイントを示している。
・ 完成品および、在庫水準はどのくらいか
・ 顧客にどのような保証や賠償を提供するべきか
・ 製造中止の影響を受ける社員をどの能力を考慮した上で別の場所に異動させるにはどのくらいの時間が要るのか
・ 機器の価値、半製品の価値はどのくらいか。または廃止の時期を遅らせた場合、利益に預かることができるのか
・ 製造中止が流通企業や顧客に与える影響はどのくらいか
市場には「参入障壁」があるように「撤退障壁」がある
製品の撤退は以上のような見地から段階的に進めていく。もちろんこうした撤退には、さまざまな障壁が立ちはだかる。想像がつくのが、前述のキヤノンに見られるように、関わる社員の抵抗だ。単品製品ならまだしも、製品カテゴリ、事業、あるいは地域からの撤退となれば関わる人も多く、規模が大きい場合は行政を交えた判断になることもある。
前出の日沖さんによれば、市場の参入時に参入障壁があるように、製品や事業の撤退時には「撤退障壁」があるとし、この対応を考慮する必要があるという。撤退障壁には次のようなものがある。
1) 労働者への補償、設備撤去費用、契約解除のペナルティ、能力維持費用などの撤退コスト。
2) 工場や造船ドッグなど耐久性のある専門化した資産。特殊なのでなかなか売却が難しい。
3) 戦略的要因。撤退にともなうマイナスイメージ、資本市場へのアクセス、共用資産など、ほかの事業部門との関係が強い場合は、撤退によって企業全体の競争力(仕入れ価格や取引先との力関係)が落ちてしまう場合がある。
4) 情報要因。他の部門との関係が深かったり、取引先との関係が深いと撤退に求められる情報が集めにくくなり、正しい判断がしにくい。
5) 心理的要因。日本では撤退じたいを恥とする文化が底流にあるため、トップをはじめ社員が撤退そのものにネガティブになる。心理的要因にはいわゆるそれまで投入した埋没コストへの未練も含まれてくる。
6) 行政や地域の成約。地域社会との関係が深い場合は、撤退により雇用をはじめ社会的経済的影響が大きく、行政がそれをよしとしない場合もある。場合によっては撤退に対して行政から補てんを求められる場合もある。
これらの障壁にあえて加えると、「責任者の障壁」がある。「誰が撤退責任者になるか」問題だ。撤退は事業の失敗であるという意識が強い日本の企業社会では、撤退した事業の責任者は「失敗者」「失格者」の烙印を押されかねないため、ピラミッド型組織では、上司が部下に責任を押し付ける、問題を隠蔽することはまだまだ横行している。撤退の評価は時間が経たないと定まらないことが多いが、投資家の圧力の強いアメリカ企業では、事業の撤退が発表されると株価が上がるケースが多い。懸念や不安材料が払拭されるからだ。
商品サイクルや事業サイクルが短くなっていくなかでは、撤退は当たり前化しつつある。勇気ある適切な撤退を評価する文化を醸成することも、解決すべき企業の大きな課題であろう。
撤退のカギを握る殿戦
撤退を決断したら、できるだけ速やかにかつ余力をもって行うことだ。
撤退時には、そのタイミングもさることながら、どのように撤退するかもポイントになる。昔から戦においては、「殿戦」と呼ばれる撤退時の戦いがあった。殿戦とは撤退時に主君と仲間を先に逃がしながら、自らは部隊の最後に位置して迫りくる追っ手と戦いながら逃げる過酷な戦だ。劣勢のなかでいかに相手を食い止め、自軍の犠牲を少なくする知恵と度胸が試されるため、殿を務める将は相当の実力者でなければ務まらないとされていた。戦国時代においては織田信長に仕えた豊臣秀吉や徳川家康がそうだった。彼らは殿を務めることでその実力を伸ばしていったとされている。
有名な殿戦は、信長が北陸の朝倉義景を金ヶ崎城に討ちに行った際、人質を交換していた浅井長政に謀反され、兵站線を閉ざされてしまった時の撤退だ。これは信長にとって最大のピンチであったが、秀吉(当時は木下藤吉郎)が殿戦を務め、無事信長軍は安全地帯である京までたどり着くことができた。
この時藤吉郎は手勢1200名ほどを率いて、織田の本陣がそこに残っているように見せかけるために、信長の馬票や旗指物など数百旈を林立させて、約200挺の鉄砲で威嚇し、5時間を稼いだ。藤吉郎はこの時、主力が十分に撤退できるためには4時間が必要だと考えていたので、5時間は十分な時間だった。
当時6、7000名を擁していた朝倉軍は約1200名の藤吉郎軍に手が出せず、そこから動けなかった。そして一定時間稼いだと判断した藤吉郎は撤退を指令、追う朝倉軍に50挺ごとに交互に射撃を行って、安全地帯に部隊を戻したのだ。さすがに無傷というわけにはいかず、途中半数の600名ほどが命を落としている。それでも奇跡に近い成果だった。戦国時代は逃げ延びるためには、他の領国を通過しなければならない。その軍勢が弱ければ、一気にたたみかけてくる可能性もある。しかし幸いにも撤退時の領土を持つ朽木信濃守元綱が協力的で、京までの道案内を買ってまでしてくれた。
信長はその後捲土重来を期し、3年余りの月日をかけて朝倉、浅井を討ち、天下統一に大きく近付いたのだ。
信長は桶狭間や長篠の戦いなど数々の名勝負をしてきた武将だが、敵が敗走しても深追いはしなかったと言われている。これは信長が常に「天下布武」すなわち、天下統一という大目標を持っていたため、大局的見地から戦いをデザインしていったからと考えられている。個別の戦いで時間を取られるより、戦況が変わったら的確に撤退して、捲土重来を期し、より有効な戦略と戦術で敵に向かうほうが、大目標に近づくことを本能として知っていたのだ。さらに信長はその戦略的重心を京においていたとされている。撤退先を京にしていたのは、そのあたりを知っていたからではとも言われている。現代の経営戦略で言えば、事業ドメインの核に当たる部分だろう。事業撤退を決定し、その事業を売却するような時、どこまで切り離すかの線をしっかり引いておくことも、経営戦略においては重要になる。

通常の仕事でも殿戦の発想は活かせる!
このように撤退行為は敗戦処理ではない。トップが経営ビジョンの実現のために新規事業戦略と同様に陣頭に立ち、責任を持ってこれに当たるべきことがらだ。そしてその実務のトップは社内でもエース級を据えるべきだ。
造船技術を生かしながら建築界のさまざまな賞を受賞している宮城県の工務店、高橋工業の高橋和志さんは、殿戦を重視した経営をしている一人。
高橋さんのいう殿戦は、「手間がかかり、単価の低い、あまりモチベーションの上がらない仕事」だ。通常こういった仕事には、新人やまだ技術が十分でない人間をつけがちだが、そうではないという。高橋工業では、こういった殿戦には社内でも仕事ができる人間をつけるのだそうだ。「そういう仕事こそ早く終えて、「大事な時間をかけるべき重要な仕事に向かうことが必要なのだ」と。
高橋工業はもともと「高橋造船鉄工所」という代々造船業だった。しかし200海里規制や度重なるオイルショックなどから高橋さんが入社後間もなく廃業。高橋さん自身が事業の撤退を経験しているのだ。高橋さんが大学院まで行って学んだ造船業
は活かせずじまいとなった。しかしその資源を今度は陸の上の事業である建設業に活かしたのだ。なかでも熱や水を加えながら、鋼板を自在に変形させる鐃鉄(ぎょうてつ)と呼ばれる技術は従来の建設業で使われたことがなく、そのユニークな技法に新進の建築家や有名ブランドが注目。美術館や高級ブランドのメゾンなどにその技術が使われていった。
撤退は苦渋の決断であり、その実行には痛みを伴う。だからこそ早めの決断が大事であり、決断後は素早い撤退が鍵を握る。さらに言えば撤退後のプランも重要だ。高橋さんの場合は、事業撤退後どうするかをしっかり練っていた。自社の特徴をどこで活かすべきか、戦う場所をしっかり見定めそこに資源とエネルギーを集中させたのだ。
いわゆる「ランチェスター戦略」である。元はイギリスの航空工学者ランチェスターが第一次世界大戦の際に提唱した兵力と火器などを組み合わせた必勝法で、局地戦の第一法則と広域戦の第二法則から成り、局地戦では「武器効率×兵力」で勝る方が勝つ。この法則を経営戦略に応用したもの。とくに第一法則が知られ、ニッチ分野や地域に強い中小企業や地方企業が取る戦略として知られる。
また最近の事業撤退は、撤退という形をとらなくなっている。事業の売却や譲渡、スピンアウト、カーブアウトといった形だ。撤退という言葉が持つマイナスの響きが、そういう形を選ばせているとも言えるが、撤退にせよ、事業売却にせよ出口プランを描いておくことは、現代ビジネスの基本でもある。
大切な経営資源を活かすためにも、撤退から、新たな事業展開までの時間はできるだけ短いほうがいい。そしてしっかりしたビジョンとグランドデザインと布陣で新たな事業にスピーディに取り組む。
あなたの事業の戦略には「撤退」は組み込まれているだろうか。また殿戦の戦術は十分だろうか。 一度じっくり考えてみるのはどうだろう。事業の戦略が変わってくるかもしれない。
参考
●『戦略的事業撤退』日沖 健 [NTT 出版]●『撤退の研究』森田 松太郎・杉之尾 信生[日本経済新聞出版社]●『週刊文春』[文芸春秋]●『撤退のマーケティング戦略』[DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー]●『戦国武将と名参謀』菊池 道人[学研M 文庫]●「web ティエラ」 日立建機ビジネスサイト[日立建機]ほか。