知ると知らずじゃ大違い!現代ビジネスパーソンが知るべき物理学が解き明かす経済の新法則「エコノフィジックス(経済物理学)」とは?
「なぜ専門家の株価予測は、当たらないのか?」「なぜあれほど盤石に見えた大企業が、一夜にして危機に陥るのか?」「なぜ金融危機やパンデミックは、いつも“想定外”の出来事として突然現れるのか?」
ビジネスの現場は常に無数の「なぜ?」に満ちている。私たちは日々、膨大なデータに基づき、合理的な意思決定を下そうと努力を重ねている。だがその懸命な努力をあざ笑うかのように、市場は私たちの予測を軽々と裏切り、練り上げた計画を根底から覆す──。
こうしたビジネスパーソンの根源的な問いに、全く新しい角度から光を当てようとしている学問がある。それが「エコノフィジックス(経済物理学)」である。物理学の法則や分析手法を用いて、人間社会の複雑怪奇な経済現象の背後にある、普遍的なパターンや構造を解き明かそうという野心的な試みだ。
「物理学」と聞いただけで、敬遠してしまう文系ビジネスパーソンも多いかもしれない。だが、エコノフィジックスが光を当てようとしているのは、世界を捉えるための新しい「ものの見方」であり、思考のOS(オペレーティング・システム)のアップデートである。その刺激的な内容を紐解いてみる。
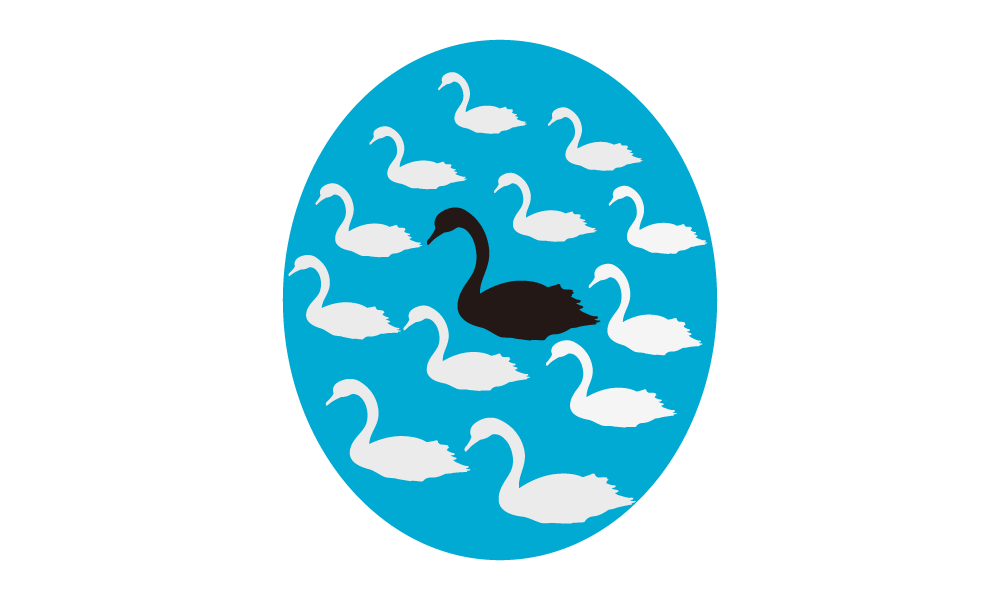
目次
■「平均」という幻想を捨てる ― 「べき乗則」が暴く富と価値の集中
ビジネスの世界で長年語られてきた「パレートの法則(80対20の法則)」という経験則はご存じだろう。「全売上の8割は、2割の優良顧客が生み出している」「仕事の成果の8割は、費やした時間の2割から生まれる」といった具合に、多くのビジネスパーソンが自身の経験として実感しているのではないだろうか。
エコノフィジックスは、パレートの法則に代表されるような経済・経営学的な法則をさらに深く掘り下げ、社会や自然界の様々な場面で観察される物理学的法則からより普遍的なパターンを導き出す学問だ。パレートの法則は、エコノフィジックスにおいては、ごく一部の「極端なもの」が全体のほとんどを支配するという、極めて不均衡な構造を示す理論で、無数にある「べき乗則」の現れ方の一つの姿に過ぎない。
従来のビジネス分析やマーケティングでは、つい「平均的な顧客」や「平均的な売上」といった「平均値」に注目しがちだ。しかし、「べき乗則」が支配する世界では、この「平均」という概念はほとんど意味を持たない。なぜなら、平均値の周辺にはほとんどデータが存在せず、現実のデータはごく一部の巨大な値と、その他大勢の小さな値に大きく偏っているものだからである。ビジネスで注目すべきは、グラフの遥か端に位置する、桁外れの数値を示す「極端な顧客」「極端なヒット商品」「極端なスター社員」なのだ。
Amazonの創業者ジェフ・ベゾスは、この法則を誰よりも深く理解し、経営に活かした天才経営者の一人である。創業当初のAmazonは、膨大な種類の書籍を扱う「ロングテール戦略」で知られていた。これは、実店舗では棚スペースの制約から置くことのできないニッチな商品(テールの部分)も、インターネット上なら無限に陳列でき、その売上を合計すればベストセラー(ヘッドの部分)に匹敵するという考え方だ。しかし、ベゾスが本当に見据えていたのは、その中でも特にロイヤリティが高く、購買頻度も金額も桁外れな「極端な顧客」だった。彼らがもたらす圧倒的な売上と、周囲に与える強力な口コミ効果こそが、Amazon帝国を築き上げた真の原動力となったのである。送料無料や翌日配送、動画・音楽配信サービスまで提供する「プライム会員」という仕組みは、まさにこの「極端な顧客」を徹底的に囲い込み、彼らをさらに熱狂的なファンへと育てるための戦略と言えるのだ。
この「べき乗則」は、動画配信サービスの巨人、Netflixの戦略にも色濃く反映されている。Netflixの強みは、個人の視聴履歴を詳細に分析し、次に見るべき作品を的確に推薦するレコメンドエンジンにある。彼らは、全ユーザーの「平均的」な好みではなく、視聴データの中に存在する「べき乗則」に着目した。つまり、ほとんどのユーザーは少数の大ヒット作品を視聴する一方で、一部の「極端なユーザー」は、特定のジャンルや監督の作品を深く、大量に視聴するというパターンである。Netflixは、この「極端なユーザー」の行動パターンを分析することで、ニッチな作品とそれを求めるユーザーを的確に結びつけ、同時に次に制作すべきオリジナル作品のジャンルやテーマを見出すヒントとして活用しているのだ。
この法則は、「お金」そのものの価値の生まれ方にも当てはまる。たとえば、1万人がそれぞれ1万円を持っている状態(合計1億円)と、一人の人間が1億円を持っている状態を比較してみよう。前者の場合、そのお金の多くは日々の小さな消費に使われ、経済全体へのインパクトは限定的だが、後者の場合、その1億円は新しい事業への投資や、スタートアップ企業へのエンジェル投資、あるいは影響力の大きな株式取得などに使われる可能性がある。それは新たな雇用を生み出し、イノベーションを加速させ、経済全体にダイナミックな変化をもたらすかもしれない。つまり、お金は細かく分散しているよりも、ある程度まとまって集中させることで、より大きな価値や変化を生み出す起爆剤となる性質を持っているのである。
この「極端値重視」の発想は、あらゆるビジネスパーソンが応用すべき思考法でエコノフィジックスの大きな柱となっている。たとえば次のような展開が考えられる。
●顧客管理 : 全ての顧客を平等に扱うという「平均」の思想を捨てる。売上全体の半分を稼ぎ出すかもしれないトップ1%のVIP顧客が誰なのかを特定し、彼らの離反を防ぐために最大のリソースを投入する。
●商品戦略 : 「そこそこの商品」を10個作るより、市場を席巻する可能性を秘めた「極端なヒット商品」を1つ生み出すことに全力を注ぐ。
●人事評価 : チームの平均的なパフォーマンス向上を目指すより、一人のスター社員が生み出す圧倒的な貢献度を正しく評価し、その能力を最大限に活かせる環境を整える。
この「べき乗則」においては、ユニクロを展開するファーストリテイリングの柳井正氏の自伝『一勝九敗』が物語っている。彼は9回の失敗は許容できるという。なぜなら、たった1回の「極端な成功」が、すべての失敗を補って余りある利益をもたらすことを、身をもって知っているからだ。「べき乗則」が支配する世界では、凡庸な平均を目指すのではなく、極端な成功を狙う勇気と、そのためのリソース集中こそが企業の運命を左右する。
■「滑らかな世界」は存在しない ― フラクタルとブラック・ショールズの限界
従来の経済学や金融工学は、株価や為替といった市場の価格変動を、なだらかで予測可能な線として捉えようとしてきた。それは、古代ギリシャの幾何学の祖、ユークリッドの名を冠した「ユークリッド幾何学」的な世界観である。時間と共に価格が滑らかに変化し、その動きはある程度、正規分布のような美しい釣鐘型の数式で近似できると想定されていた。
この思想を象徴するのが、金融工学の世界に革命をもたらし、ノーベル経済学賞の対象ともなった「ブラック・ショールズ方程式」だ。この方程式は、デリバティブ(金融派生商品)の価格を理論的に算出する画期的なモデルとして、ウォール街で瞬く間に普及した。しかし、その理論の根幹には、「株価の変動率は一定で、その変動はランダムかつ正規分布に従う」という仮定があった。
しかし、現実の市場チャートを少しでも眺めたことがある人なら誰でも気づくはずだ。そこに滑らかな曲線など、どこにも存在しないということに。私たちが見ているのは、常に不規則で、激しく上下動を繰り返す「ギザギザ」の線だけだ。そして、数学者ブノワ・マンデルブロが発見したように、このチャートを1日単位で見ても、1週間単位、1年単位で見ても、不思議なことに、常に同じようなギザギザのパターンが現れる。部分をどれだけ拡大しても、そこにまた全体と似たような形が繰り返される——。これこそが「フラクタル」の持つ「自己相似性」という重要な特徴である。
エコノフィジックスは、「市場の価格変動が本質的にフラクタルであること」を明らかにした。これは、巨大な暴落や暴騰といった「極端な事象(ブラックスワン)」が、正規分布のモデルが予測するよりも遥かに高い頻度で発生することを意味している。1998年の大手ヘッジファンドLTCMの破綻や、2008年のリーマンショックといった歴史的な金融危機は、まさにこのブラック・ショールズ方程式の前提(正規分布)が、フラクタルな現実の前ではいかに無力であるかを証明した。「100年に一度」のはずの危機が、わずか10年で再び起きたのである。
この視点は、私たちに市場に対する根源的な謙虚さと用心の重要性を示唆する。完璧な予測は原理的に不可能であり、滑らかな右肩上がりを夢見るのではなく、常に予期せぬ巨大な変動(ギザギザ)が起こることを前提とした戦略、すなわちレジリエンス(しなやかな強さ)を重視する必要がある。
■豹変する市場の予兆を掴む ― 「相転移」と「バタフライ効果」
「相転移」は物理学では重要な現象だ。この「相転移」は、ビジネスのさまざまな業界で繰り返されてきている。相転移とはどのような物理現象かというと、ある閾値(しきいち)を超えると、それまでの連続的な変化が、不連続で質的な変化へと転換する現象をいう。たとえばやかんで水を熱していくと、温度は徐々に上昇する。98℃でも99℃でも、水は依然として液体のままである。しかし、100℃という臨界点に達した瞬間、水は沸騰し、水蒸気という全く異なる状態に劇的に変化する。この現象が相転移である。それはビジネスにおいても起こっているのだ。いくつか事例を挙げてみよう。
たとえば写真業界。フィルムからデジタルへの相転移が起きている。20世紀の大半、写真市場は銀塩フィルムが支配する安定した世界だった。しかし、デジタルカメラの性能、特に画素数と価格という2つの要素が臨界点を超えた瞬間、業界は激変した。初期のデジカメは画質が悪く高価だったが、技術革新により画質がフィルムに迫り、価格が手頃になると、消費者は一斉にデジタルへと移行した。フィルムの現像という手間やコストから解放されるという利便性が、長年続いた市場をわずか数年で消滅させた。

音楽業界では、物理メディアからストリーミングへの相転移が起きている。レコードからCDへの変化も一つの相転移だが、より劇的だったのはブロードバンド通信の普及とMP3圧縮技術の進化が臨界点に達した時の変化だ。これにより、物理的なメディアを所有する必要がなくなり、月額定額制で無限の楽曲にアクセスできるストリーミングサービスが主流となった。かつて業界の収益の柱だったCDの売上は激減し、アーティストの収益構造も根底から覆された。

また携帯電話業界ではガラケーからスマートフォンへ相転移した。2007年にiPhoneが登場するまで、携帯電話市場は通話とメールが中心の「ガラケー」が支配していたが、静電容量式タッチパネルの操作性とアプリケーション・エコシステムという革新が臨界点となり、市場は「電話」から「手のひらサイズのコンピュータ」へと相転移を遂げた。人々が携帯電話に求める価値そのものが変化し、対応できなかった多くのメーカーが市場からの撤退を余儀なくされた。

小売業界では店舗からEコマースへの相転移が知られる。上述したようにAmazonの台頭は、小売業界に地殻変動をもたらした。消費者のインターネット利用率とオンライン決済への信頼がある閾値を超えた時、「店舗で買う」という常識は覆された。物流網の整備が進むにつれ、消費者は価格比較の容易さ、品揃えの豊富さ、自宅に届く利便性を求め、Eコマースへと雪崩を打った。これにより、多くの実店舗が閉店に追い込まれ、ビジネスの主戦場は「立地」から「物流とデータ」へと移った。
自動車業界において起きているのがガソリン車から電気自動車への相転移だ。バッテリーのエネルギー密度とコスト、そして充電インフラの普及が臨界点に近づいている。これらの条件が満たされた時、消費者の選択は急速にガソリン車からEVへとシフトする可能性がある。環境規制という外部からの圧力も相まって、100年以上続いた内燃機関の時代が終わりを告げ、業界のサプライチェーンや雇用構造全体が劇的に変化する岐路に立っている。
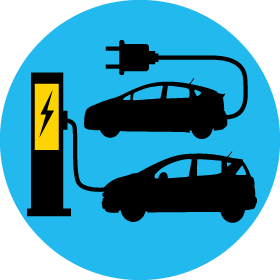
広告業界ではマスメディアから運用型広告への相転移が起こった。かつて広告の主役はテレビや新聞のマスメディアだった。しかし、個人のデータ収集・分析技術とアルゴリズムが進化し、広告をリアルタイムで最適化できる「運用型広告」が登場すると、状況は一変した。広告主は不特定多数に届けるマス広告よりも、費用対効果を精密に測定できるデジタル広告に予算をシフト。これにより、伝統的なメディア企業の収益モデルは大きく揺らいでいる。
相転移の恐ろしいところは、「ある日突然やってくる」ように見えることだ。しかし、物理現象と同様、経済の相転移にも必ず「予兆」がある。ビジネスにおける予兆とは、顧客の口から漏れる小さな不満の声、現場で生まれる些細な違和感、競合他社の不可解な動きといった、目に見えない微細なサインである。優れた経営者は、この予兆を捉える「気づき力」に長けている。
一方で、現代のグローバル経済においては、物理学の「バタフライ効果」も日常的に発生している。バタフライ効果とは、力学系のある状態にわずかな変化を与えると、そのわずかな変化が無かった場合とは、その後の系の状態が大きく異なってしまうという現象のこと。この名称は、気象学者のエドワード・ローレンツが発した「蝶が羽ばたく程度の非常に小さい撹乱でも遠くの気象に影響を与えるか」という問いに由来する。一般的には「ブラジルの蝶の羽ばたきがテキサスで竜巻を起こす」という表現で知られる。バタフライ効果事例には次のような事象がある。
リーマンショック(2008年): 元をたどれば、アメリカの一部の低所得者向け住宅ローン(サブプライムローン)という「小さな信用不安」が全ての始まりだった。このローンが証券化という金融工学によって複雑な金融商品に組み込まれ、世界中の金融機関に販売された。結果、アメリカの一地方の住宅価格の下落という蝶の羽ばたきが、世界経済全体を揺るがす金融危機という巨大な竜巻を起こしたのだ。
コロナ禍の半導体不足(2020年〜): 中国・武漢での一都市におけるウイルス発生という初期事象が、世界的なパンデミックへと発展。各国がロックダウンを実施したことで、当初は自動車の需要が減少し、自動車メーカーは半導体の発注をキャンセルした。しかし、巣ごもり需要でPCやゲーム機の需要が急増。その後、予想より早く自動車需要が回復した時には、半導体メーカーの生産ラインは既にPC向けなどで埋まっており、世界的な自動車の減産を引き起こすという連鎖反応につながった。
スエズ運河座礁事故(2021年): 一隻の巨大コンテナ船が運河で座礁したという単独の事故が、世界の海上物流の主要動脈を6日間にわたって完全に麻痺させた。この影響で、1日あたり約1兆円の経済的損失が発生したとされ、原油価格の上昇や世界中のサプライチェーンの遅延を引き起こした。グローバル貿易がいかに脆弱な一本の線に依存しているかを露呈した事件である。
タイの洪水とハードディスク供給網の混乱(2011年): タイで発生した大規模な洪水は、当時世界のハードディスク(HDD)生産の約4割を占めていた同国の工業団地に壊滅的な被害を与えた。これにより、世界のHDD供給量が激減し、PCの価格が高騰。遠く離れた国のIT企業や消費者にまで深刻な影響が及んだ。特定の地域に生産拠点が集中することのリスクを浮き彫りにした。
アイスランドの火山噴火と欧州航空網の麻痺(2010年): アイスランドの一つの火山の噴火によって放出された大量の火山灰が、ジェットエンジンの故障を引き起こす可能性があるとして、ヨーロッパ全域の空港が数日間にわたり閉鎖された。これにより、1000万人以上の足に影響が出たほか、空輸される生鮮食品や医薬品の物流もストップし、甚大な経済的損失につながった。
ウクライナ侵攻と世界的な食料・エネルギー価格の高騰(2022年〜): ロシアによるウクライナへの軍事侵攻という国間の紛争が、世界有数の穀倉地帯である両国からの小麦やトウモロコシの輸出を滞らせ、世界的な食料価格の高騰と食糧危機への懸念を引き起こした。同時に、ロシアからの天然ガスの供給不安がエネルギー価格を押し上げ、世界中の企業活動や家計に大きな打撃を与えている。
これらの事例が示すように、現代のサプライチェーンは極めて複雑で、予測不能なリスクに満ちている。では、こうしたバタフライ効果に満ちた世界で、企業はどうすれば生き残れるのか。その答えの一つとして、生物の進化のメカニズムを模倣した「遺伝的アルゴリズム」という考え方が注目されている。
これは、複雑な問題に対して、最適に近い解を効率的に見つけ出すための計算手法だ。生物が「選択」「交叉」「突然変異」を繰り返して環境に適応していくように、多数の解の候補(個体)を用意し、それらを交配させたり、ランダムに変化させたりしながら、より優れた解(環境に適応した個体)を残していく。このプロセスを何世代も繰り返すことで、人間では思いつかないような優れた解を発見することができる。
この遺伝的アルゴリズムは、まさに現代の複雑なサプライチェーン管理に応用されている。次のような例だ。
●最適ルートの探索 : 何百もの配送先をどのような順番で回れば総移動距離が最短になるか、という「巡回セールスマン問題」は、組み合わせが天文学的になり、従来の手法では解くのが難しい。遺伝的アルゴリズムは、こうした問題に対し、極めて効率的に最適に近い配送ルートを算出する。
●在庫管理の最適化 : 需要の変動やリードタイムの不確実性を考慮しながら、どの倉庫にどれだけの在庫を配置すれば、欠品リスクと在庫コストを最小化できるか、という複雑な問題を解くのに役立つ。
●リアルタイムなリスク対応 : 災害や事故で特定の輸送ルートが寸断された場合、遺伝的アルゴリズムは瞬時に代替ルートや輸送手段を再計算し、サプライチェーン全体のダメージを最小限に抑えるための新たな最適解を提示する。
私たちは、顧客や市場というミクロな変化の予兆だけでなく、世界のどこかで起きた小さな出来事が自社のビジネスを根底から揺るがしかねないという、マクロなリスクにも常にアンテナを張りながら、エコノフィジックスの理論を応用しながら日々のビジネスを進めていく必要がある。
■インフレという「臨界現象」 ― ハイパーインフレの教訓と金融政策の危うさ
相転移の概念は、国家レベルの経済政策、特にインフレのコントロールがいかに難しいかを理解する上でも極めて重要である。近年の主要国の中央銀行では、一定のインフレ率(例えば年2%)を目標に掲げて金融政策を行う「インフレ・ターゲティング」が注目されている。これは、経済を緩やかに温め続けることで、デフレを回避し、安定的な経済成長を目指すという考え方だ。
しかし、歴史はこの手法が内包する深刻な危険性、すなわち一度暴走を始めたインフレのコントロールがいかに困難であるかを、私たちに教えている。その最も悲劇的な実例が、第二次世界大戦後のハンガリーで発生した、通貨「ペンゴ」の天文学的なハイパーインフレーションだ。
その始まりは比較的緩やかに見えた。当初、インフレは1ヶ月に4倍から6倍という、異常ながらもまだ理解可能なペースで半年ほど続いた。しかし、これだけで物価は半年で1000倍以上に跳ね上がり、従来の紙幣ではもはや発行が追いつかなくなる。政府はゼロの数を増やした高額紙幣を乱発したが、これが国民の焦りと通貨への不信を決定的にした。
人々の心理は、物理学でいう「正のフィードバックループ」に陥った。物価が2倍になるのに最初は1ヵ月かかっていたものが、次は2週間、そして1週間、しまいには3日で2倍になるのではないか—。そんな恐怖と不安が社会全体に伝染し、誰もが給料を受け取った瞬間にモノに換えようと店に殺到した。このパニック的な購買行動が、さらに物価を押し上げるという悪循環を加速させ、政府の金融コントロールは完全に機能を失ったのだ。
ここで特筆すべきは、この歴史的なインフレが、深刻なモノ不足によって引き起こされたわけではないという点である。市場には商品は流通していた。問題は、誰もがその対価として、日に日に価値を失うペンコ゚紙幣を受け取る代わりに店頭のモノを求めたことにある。これは、通貨という社会の血液に対する人々の「信頼」が、ある臨界点を超えて完全に崩壊した「相転移」そのものであった。
一度この状態に陥ると、金融緩和の縮小といった小手先の政策では、もはやインフレを止めることはできない。結局、ハンガリー政府は終戦から1年後、新しい通貨「フォリント」を実に10の29乗ペンゴ(1兆の1兆倍のさらに10万倍)という、まさに天文学的交換レートで導入するという荒療治に踏み切るしかなかった。すると、あれほどのインフレが嘘のようにピタッと収まったのである。
この事例は、インフレがいったん人々の心理を巻き込んで暴走し始めると、従来の経済理論ではコントロール不能な「臨界現象」に突入する可能性を私たちに強く警告している。緩やかなインフレを目指す現代の金融政策は、常にこのハイパーインフレという崖っぷちを歩いているような、極めて危ういバランスの上に成り立っているのかもしれない。
■「お金」という粒子の奇妙な振る舞い ― 変わりゆく貨幣の正体
私たちは日々、当たり前のようにお金を使っているが、その性質自体が時代と共に大きく変化していることを意識する人は少ないかもしれない。エコノフィジックスは、この「お金」という、経済システムの根幹をなす存在そのものにも、物理学的な鋭いメスを入れる。
第一に、お金の価値や人間が感じる効用は、必ずしもその金額に比例するわけではない、非線形性を持っているということだ。物理学の「フックの法則」では、バネの伸びは一定の範囲内ではかけた力に比例する。これと同様に、たとえば年収500万円が1000万円になれば、生活は劇的に豊かになり、幸福度も大きく増すだろう。しかし、年収が10億円から20億円になっても、あるいは1兆円になったとしても、その人の生活や幸福度が金額に比例して向上するわけではない。現実の世界では、それほど巨額のお金を使い切る場は存在しないからである。つまり、お金の価値には、ある金額を超えると人間が感じる効用が飽和するという、非線形な性質があるのだ。
第二に、現代におけるお金の機能の根本的な変化である。本来、お金は価値の交換(決済)や保存の手段であった。しかし、特にグローバル化とデジタル化が極度に進んだ現代の金融市場において、お金はそれ自体が利益を生むための、純粋な投資や投機の対象と化している。
実際に世界でモノやサービスを動かす実体経済の取引額を遥かに上回る、天文学的な金額の「電子的なお金」が、コンマ数秒の間にコンピュータのアルゴリズムによって取引されている(高頻度取引:HFT)。そこでは、企業のファンダメンタルズや実体経済の動向とは全くかけ離れた、純粋な数字のゲームとしてのマネーが自己増殖的に動き回っている。
このようにお金が「実体」から遊離し、純粋な情報としての性格を強めたことで、その動きはますます予測不能で不安定になっている。私たちは、自社の製品やサービスの価値だけを真面目に考えるだけでは不十分なのだ。その背景にある、巨大で複雑なマネーゲームのルールが、いつ、どのように変わろうとしているのか。その変化が、いつ自社のビジネスに津波のように押し寄せてくるのか。その可能性を常に視野に入れておく必要がある。
■「ブラックスワン」と共に生きる ― 予測不能な危機への科学的アプローチ
2001年のアメリカ同時多発テロ、2008年のリーマンショック、2011年の東日本大震災、そして2020年のコロナ・パンデミック——。これらはすべて、思想家ナシム・ニコラス・タレブが提唱した「ブラックスワン」と呼ばれる出来事である。すなわち、「①それまで誰も予想しておらず、②発生したときの影響が甚大で、③後になってから『あれは予測可能だった』と誰もがもっともらしく説明する」という3つの特徴を持つ、極めて稀な事象を指す。
従来のリスク管理は、過去のデータに基づいて、起こりうる確率の高い事象に備えることを主眼としてきた。そのため、「100年に一度」「1000年に一度」と言われるブラックスワンは、「めったに起こらないこと」として、その備えが軽視されがちだった。
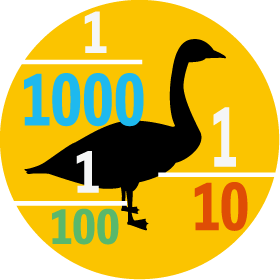
しかし、エコノフィジックスの研究は、衝撃的な事実を明らかにした。それは、「ブラックスワンは、私たちが正規分布モデルで考えているよりも、はるかに頻繁に発生している」という事実だ。金融市場のデータなどを物理学的手法で分析すると、巨大な暴落や暴騰といった「極端な異常値」は、正規分布が予測する確率よりも、圧倒的に高い頻度で出現することが判明している。
では、予測不能なブラックスワンに、私たちはどう立ち向かえば良いのか。エコノフィジックス的思考は、従来の「予測と予防」から、「備えと適応」への発想の根本的な転換を促している。
失敗しないこと、危機を完璧に回避することは不可能だ。いま求められているのは、たとえ大きなダメージを受けても、そこから素早く立ち直り、むしろその経験を糧にして、より強くなる「レジリエンス(回復力、復元力)」である。
経営コンサルタントの冨山和彦氏は、日本航空(JAL)の再建など、数々の修羅場をくぐり抜けてきた経験から、若いうちに敢えて「ダメな組織」や「理不尽な環境」に身を置くことの重要性を説く。そうした厳しい環境で挫折や失敗を経験し、それを乗り越えることでこそ、その後幾度となく巡ってくる危機から立ち直るための「レジリエンス」が鍛えられるというのだ。
さらに上述したタレブは、単にダメージから回復するレジリエンスの一歩先を行く概念として「反脆弱性(アンチフラジャイリティ)」を提唱している。反脆弱性は、ガラスのように衝撃で壊れる「脆弱な」ものでもなく、ゴムボールのように衝撃を受けても元に戻る「頑健な(レジリエントな)」ものでもなく、むしろ衝撃やストレス、不確実性といった外部からの揺さぶりを与えられれば与えられるほど、かえってパフォーマンスが向上し、強くなる性質である。
ブラックスワンが頻発する現代において私たちが目指すべきは、この「反脆弱性」を備えた組織やキャリアを構築することだろう。それは特定の事業やスキルに過度に依存するのではなく、常に複数の選択肢を持ち、失敗を許容し、そこから学ぶサイクルを高速で回し続けることだ。
■「平均」の呪縛が生む悲劇 ― 偏差値が日本の才能を殺す
エコノフィジックスが投げかける「平均への疑い」は、金融市場やビジネスの世界だけに留まらない。たとえば多くの人々が優れた指標として信じている「偏差値」。とりわけ教育業界においては絶対的な意味を持っている。
周知のように偏差値は、ある集団の中で自分がどの位置にいるかを示すための指標である。その計算の根底にあるのは、これまで何度も指摘してきた正規分布、すなわち「平均的な学力を持つ人が最も多く、そこから離れるほど人数が少なくなる」という釣鐘型のモデルである。
しかしエコノフィジックスは、このモデルの硬直性に警鐘を鳴らす。たとえば数学の試験結果の場合、その得点分布は、理論を完全に理解した高得点層と、途中でつまずいてしまった低得点層に分かれる「二極化」の傾向を示す。中央に山ができる美しい正規分布とは異なる形になることの方が多いのだ。
これが実際の市場であれば、現実のデータ(結果)がモデルと異なれば、そのモデルは修正されたり、捨てられたりする。しかし、教育の世界では現実の学力分布がどうであれ、「偏差値」という正規分布を前提としたものさしが、絶対的な評価基準として何十年も使われ続けている。教育現場の改革や改善は、数年、数十年という非常に長い単位で行われる(学習指導要領の大幅改定は約10年に一度)。この硬直性が、大きな悲劇を生む可能性がある。

それは、創造性に富んだ若い才能が、画一的なものさしによって埋もれてしまうという悲劇である。「べき乗則」の世界で説明したように、社会に大きな変革をもたらすのは、平均的な能力を持つ人々ではなく、ある特定の分野で突出した能力を持つ「極端な」才能だ。しかし偏差値は、すべての教科をそつなくこなす「平均的」な優等生を高く評価する一方で、特定の分野に異様なほどの情熱と才能を注ぎ込むような、正規分布の枠からはみ出した「ギザギザの才能」を正しく評価することができない。
よってこれからの時代、本当に優れた人材を企業が求めるのであれば、まずこの偏差値が持つ意味とその限界を深く理解する必要がある。そして、偏差値という「平均」の呪縛から自らを解き放ち、面接やポートフォリオ評価、インターンシップでの実績など、企業独自の独創的な視点で、次世代を担うべき才能を採用し、育成していくことが不可欠となる。もちろん、これは大学における選抜においても同様のことが言える。
■明日からできるエコノフィジックス的思考法
エコノフィジックスは、決して物理学者やデータサイエンティストだけのものではない。その「ものの見方」のエッセンスは、日々のビジネス判断にすぐに取り入れ、実践することができる。難しい計算は専門家やAIに任せ、私たちは以下の「新しい思考習慣」を、自らのOSとしてインストールすることを目指すべきだ。
1.「平均」ではなく「両極端」に注目する習慣
月次の売上報告を見るとき、平均売上高だけでなく、「最も売れた日」と「最も売れなかった日」に何が起きたのかを徹底的に分析してみるとよい。顧客リストを眺めるとき、「平均的な顧客像」を思い浮かべるのではなく、「最も熱心なファン」と「最も辛辣なクレーム客」の顔を具体的に思い浮かべる。ビジネスを動かす本質的なヒントは、常にこの両極端に隠されている。
2. 小さな変化を「物語の始まり」として解釈する習慣
「顧客満足度が0.5ポイント低下した」という単なるデータとして処理するのではなく、「なぜ、わずかとはいえ顧客の心は私たちから離れ始めたのか?」という、壮大な物語の始まりとして捉えてみる。競合他社が発表した小さなプレスリリースを、「単なる新商品情報」ではなく、「彼らがこれから仕掛けようとしている大きな戦略転換の第一歩(=相転移の予兆)かもしれない」という仮説を持って読んでみる。バタフライ効果が支配する世界では、小さな変化こそが最も重要な戦略情報なのだ。
3. 常に「最悪のシナリオ」をシミュレーションする習慣
四半期ごとに行われる戦略会議で、ぜひこんな問いを立ててみよう。「もし、明日、主力事業の売上が半分になったら?」「もし、最大の取引先が倒産したら?」「もし、予期せぬパンデミックや災害で、サプライチェーンが寸断されたら?」。こうした極端なシナリオをあらかじめシミュレーションしておくこと。それが、いつか必ずやってくるブラックスワンの襲来を生き延びるための、最も科学的な防災訓練となる。
私たちは今、歴史的な転換期に生きている。このような時代に求められるのは、既存の知識の量ではなく、複雑で不確実な世界を捉え直すための、しなやかで強靭な思考のフレームワークである。エコノフィジックスは、そのための最も強力な武器の一つに違いない。その視点を取り入れることで、変化の激しい時代を勝ち抜くための新たな羅針盤が手に入るはずだ。
参考
【書籍】●『経済物理学の発見』高安秀樹[ 光文社] ●『エコノフィジックス市場に潜む物理法則』高安秀樹/高安美佐子[日本経済新聞社]●『反脆弱性―不確実な世界を生き延びる唯一の考え方』ナシム・ニコラス・タレブ[ ダイヤモンド社] ●『ブラックスワン』ナシム・ニコラス・タレブ[ ダイヤモンド社] ●『挫折力─ 一流になれる 50 の思考・行動術』冨山和彦[PHP ビジネス新書] ●『一勝九敗』柳井正[ 新潮文庫] ●『鈴木敏文の統計心理学』勝見明[プレジデント社]
【WEB】●独立行政法人経済産業研究所 ●Science Porta「l 第5回「経済物理学へ─社会の動きへの挑戦」 ●日本経済新聞社 ●日経ビジネス ●東洋経済オンライン ● Harvard Business Review ほか
POINT
■「エコノフィジックス(経済物理学)」は、物理学の手法で複雑な経済現象を解き明かす新しい学問分野。
■ 従来の経済学が前提とする「平均」は、現実のビジネスではほとんど意味をなさない。
■ 事業の成否を握るのは、ごく一部の「極端な顧客」やヒット商品である。
■ ビジネスで馴染みのある「80対20の法則」は、一部の極端なものが全体を支配する「べき乗則」の例に過ぎない。
■ 市場の価格変動は、滑らかな線で表せる(ユークリッド的)と想定されてきたが、実際はどの時間スケールで見ても同じようにギザギザな「フラクタル」構造を持つ。
■ 金融工学のブラック・ショールズ方程式は、市場が正規分布に従うと仮定しているため、フラクタルな現実の前ではしばしば機能不全に陥る。
■ 水が100℃で沸騰するように、ある閾値を超えると市場構造が劇的に変化する「相転移」がビジネスでも起こる。
■ グローバル経済では、一見無関係な遠い場所の小さな出来事が全体に甚大な影響を及ぼす「バタフライ効果」が日常的に発生する。
■ サプライチェーンはバタフライ効果に対して脆弱だが、生物の進化を模倣した「遺伝的アルゴリズム」を用いることで、変化に強い最適ルートの探索やリスク対応が可能になる。
■ インフレは一度人々の心理を巻き込んで暴走し始めると、コントロール不能な「臨界現象」に突入する危険性がある。
■ めったに起こらないが甚大な影響を及ぼす「ブラックスワン」は、従来の想定より頻繁に発生しており、これに備える必要がある。
■ 現代の「お金」は、実体経済から遊離し、それ自体が投機対象となっているため、その動きはより予測不能になっている。
■ 教育現場で絶対視される「偏差値」は、正規分布を前提としており、現実の多様な学力分布や「極端な才能」を正しく評価できない問題を抱えている。
■ 企業や大学は偏差値の限界を理解し、独自の視点で次世代の独創的な人材を採用・育成する必要がある。
■ 予測不能な時代に重要なのは、危機を乗り越え、むしろより強くなる「レジリエンス(回復力)」や「反脆弱性」である。
■ エコノフィジックス的思考とは、数式を覚えることではなく、「平均より極端に注目する」「小さな変化の予兆を探す」といった「ものの見方の革命」である。
ビジネスシンカーとは:日常生活の中で、ふと入ってきて耳や頭から離れなくなった言葉や現象、ずっと抱いてきた疑問などについて、50種以上のメディアに関わってきたライターが、多角的視点で解き明かすビジネスコラム