便利だからこそ曖昧に使っていないか?!マネジメントのキラーワード「人間力」の解像度を上げる
ビジネス現場で便利に使われる「人間力」。しかし、これほど曖昧で、明確に説明されにくい言葉もないだろう。多くの場合、それは議論を終わらせるための便利なキラーワードとして使われがちだ。AIが知的労働を代替し始めた今、この曖昧な言葉に頼ることは、思考停止を招く危険がある。しかし、この「人間力」の解像度を高めれば、ビジネスや人間関係がクリアに見え、現代における人間の定義さえ見えてくるかもしれない。「人間力」について、深く考えてみよう。

目次
■「人間力」とは何か―内閣府による公式定義の3層構造
驚くかもしれないが、実は「人間力」は“公的”に定義されている。2003年、内閣府「人間力戦略研究会」の報告書は、「人間力」を「社会を構成し運営するとともに、自立した一人の人間として力強く生きていくための総合的な力」と定義した。報告書はこれをさらに3つの層に分解している。
第1層:知的能力的要素─基礎学力、専門的知識、論理的思考力、創造力など。いわば「頭の良さ」に関わる部分だ。ビジネスでは、専門知識、データ分析力、問題解決能力などが該当する。
第2層:社会・対人関係力的要素─コミュニケーションスキル、リーダーシップ、公共心、他者を尊重する力など。「人との関わり方」に関する能力だ。チームワーク、交渉力、部下育成力などが含まれる。
第3層:自己制御的要素─意欲、忍耐力、自分らしい生き方を追求する力など。「自分自身をどうマネジメントするか」という内面的な力だ。目標達成へのコミットメント、ストレス耐性、自己研鑽の習慣などが該当する。
内閣府の定義では、この三層が相互に影響し、統合されたものが「人間力」だとされる。つまり、知識、対人関係力、意欲が総合的に機能して初めて「人間力が高い」と評価されるというわけだ。
一見、明快だが、この三層構造は人間の「ほぼすべての能力」を包含している。知力、社会性、自己管理のすべてを兼ね備えるのは、まるでスーパーマンになれと言わんばかりだ。この定義を知っても、「明日から何をすればいいか」という具体的な指針は得にくいのが実情である。
この定義は全体像の地図としては有用だが、実際の航海図にはなり得ない。では、具体的な航海図はどこにあるのだろうか。参考になるのが、人材育成を経営の礎とした経営者たちの行動指針である。
■トヨタが求める「人間力」―徹底した「現地現物」の習慣
トヨタ自動車の強さの源泉「トヨタ生産方式(TPS)」や「カイゼン」。これらを支える根幹に、トヨタ独自の「人間力」観がある。トヨタでは、「人間力」を特別な才能とは捉えず、日々の習慣と徹底した現場主義によって培われる実践的な能力と位置づけている。象徴的なのが「現地現物」だ。問題が起きたら、会議室ではなく現場に行き、自分の目で現物を見て、現場の声を聞く。データや報告書だけでなく、五感で事実を確認する習慣こそが、トヨタの「人間力」の基盤である。
具体的には、以下のような行動パターンとして現れる。
①「なぜ」を5回繰り返す思考習慣、「なぜなぜ5回」
問題の表面的な原因に満足せず、「なぜ」を5回繰り返し真因に到達する。この思考訓練が、物事の本質を見抜く洞察力を養う。例えば、不良品が出た場合、「なぜ出た?」「機械の設定ミス」「なぜミスした?」「手順書が古いままだった」……と掘り下げることで、表面的な対症療法ではない根本解決につなげる。
②自分の仮説を現場で検証する姿勢
「こうすればうまくいくはずだ」という仮説は、必ず現場で試す。失敗を恐れず、小さく試し、学び、改善するサイクルを高速で回す能力が、トヨタの「人間力」である。どんな優れたアイデアも、現場で実証されるまでは「仮説」に過ぎない。
③現場の知恵を引き出す傾聴力
現場の作業者は、問題の本質を最もよく知っている。彼らの声に耳を傾け、「衆知を集める」ことができるかが、管理職の「人間力」を測る指標となる。管理職は現場に足を運び、「やりにくくないですか?」といった問いかけから、改善のヒントを拾い上げる。
④改善を継続する持久力
一度の改善で満足せず、さらなる改善の余地を探し続ける。この「終わりなき改善」を支えるのが、意欲や忍耐力といった内面的な力である。トヨタの「カイゼン」は日常業務に組み込まれた継続的な活動であり、この地道な積み重ねが長期的な競争力を生む。
トヨタの「人間力」は、「現場に密着し、事実に基づいて考え、実行し、学び続ける力」と言えるだろう。これは内閣府の定義の三層(知的能力、対人関係力、自己制御)が統合された姿だ。しかしトヨタの定義が優れているのは、「現地現物」「5回のなぜ」「カイゼン」という具体的な行動様式に落とし込まれている点である。「人間力を磨け」ではなく、「現場に行け」「なぜを5回繰り返せ」という明確な指示が出せる。これこそが、抽象を具体に翻訳するということだ。
■松下幸之助さんの「人間力」は「素直な心」と「衆知を集める力」
「経営の神様」松下幸之助さんが生涯重視したのが、「素直な心」である。松下さんにとって「人間力」とは、特別な才能ではなく、「素直な心」を持ち、「衆知を集める」ことができる力だった。
松下さんの言う「素直な心」とは、従順さではなく、私心にとらわれず物事をありのままに見る心である。具体的には、以下のような姿勢を意味する。
・第1に、先入観を脇に置き、事実を虚心坦懐に受け止めること。「こうあるべきだ」という思い込みが正しい判断を妨げる。
・第2に、失敗を認め、他者の指摘を受け入れる謙虚さ。プライドや見栄が成長を阻む。
・第3に、成功しても驕らず、常に学び続ける姿勢。環境の変化に応じて自分を変えていく柔軟性が求められる。
・第4に、目先の利益ではなく、長期的・全体的な視点で判断すること。私利私欲は長期的な信頼を失わせる。松下さんは、「素直な心」があれば自然と正しい判断ができ、逆に私心(私利私欲、保身、見栄など)が判断を曇らせると説いた。
もう一つの核心が「衆知を集める経営」である。一人の天才に頼るのではなく、組織全体の知恵を結集して最善の答えを導き出すという経営哲学だ。これを実現するには、以下の行動が必要である。
・部下の意見に真摯に耳を傾け、本気で学ぼうとすること。
・地位や年齢に関係なく、良い意見は採用すること。
・異なる視点や反対意見を歓迎すること。
・心理的安全性を確保し、誰もが安心して発言できる環境を作ること。本音が語られない組織は衰退する。
松下さんの「人間力」を測る指標は、「どれだけ素直な心で事実を見られるか」「どれだけ多くの人の知恵を引き出し、活かせるか」の2点である。
これを現代ビジネスに当てはめれば、次のような行動になる。
・会議で自分の間違いを認め、より良い案に方向転換できる。
・若手社員の提案に真剣に耳を傾け、実行に移せる。
・批判的な意見にも感情的にならず、建設的に議論できる。
・失敗を隠さず、そこから学びを引き出し共有する。
■稲盛和夫さんが説く「人間力」は「利他の心」と「哲学を持つこと」
京セラとKDDIを創業し、JALを再建したカリスマ経営者の一人、稲盛和夫さんは、「人間として正しいかどうか」を判断基準とした。稲盛さんにとっての「人間力」とは、「利他の心」と「自分なりの哲学を持つこと」に集約される。
■「利他の心」―自分の利益より、他者の幸せを考える
仏門で得度した経験を持つ稲盛さんは、ビジネス成功の鍵は「利他の心」にあると説いた。自分だけが得をする「利己」ではなく、顧客、取引先、従業員、社会全体の幸せを考える「利他」の視点(現代のマルチステークホルダーの視点)が、長期的な成功をもたらすと確信していた。「利他の心」は、次のような行動として現れる。
・短期的な利益より、顧客の長期的な満足を優先する。
・部下の成長を心から願い、時間をかけて育成する。
・取引先とは搾取ではなく、共存共栄の関係を築く。
・困難な決断の際、「人間として正しいか」を自問し、道義に反する行為は避ける。
稲盛さんは、こうした「利他の心」が結果的に自分にも返ってくると説いた。信頼の蓄積が、長期的な成功の基盤となる。さらに現代ビジネスにおいては、たとえ利害が反する相手であっても、社会全体の発展という「利他」の視点で対話し、理解や妥協点を探る姿勢も含まれるだろう。
■「哲学を持つ」―自分の判断基準を明確にする
稲盛さんはまた、リーダーに最も必要なのは「哲学」だと語った。これは難解な学問ではなく、「自分は何を大切にして生きるのか」という人生の指針である。哲学を持つとは、以下の問いに自分なりの答えを持つことだ。
・何が正しくて、何が間違っているのか。判断に迷ったとき、確固たる基準があるか。
・何のために働くのか。単なる生活のためか、社会貢献のためか。仕事の意義を語れるか。
・どういう人間になりたいのか。理想像を持っているか。
こうした根本的な答えを持ち、日々の判断基準とすること。これが「哲学を持つ」ということだ。稲盛氏は京セラで「フィロソフィ教育」を徹底し、理念の共有と実践が組織全体の「人間力」を高めると考えた。
■ビジネス現場で乱用される「人間力」―5つのパターンと誤解
公的な定義や経営者の「人間力」観とは裏腹に、実際の現場では、この言葉は曖昧かつ都合よく使われがちだ。その典型が次の5パターンである。
パターン①:評価面談での逃げ道として
「君は業績は悪くないが、人間力がもう少しあればね」。こう言われた部下は、具体的に何を改善すべきか分からない。評価者が「人間力」という言葉を使うとき、それは具体的なフィードバックを避ける逃げ道になっていることがある。「プレゼンの論理構成が弱い」と具体的に指摘すれば説明責任が生じるが、「人間力が足りない」と言えば逃れられるからだ。
パターン②:採用面接での印象論として
「この候補者、スキルは十分だが、人間力がちょっと…」。わずか1時間の面接で、何を基準に判断しているのだろうか。笑顔や受け答え、あるいは単なる相性かもしれない。結局、「人間力」という言葉が、面接官の主観的な好き嫌いを正当化する道具になっている。
パターン③:研修での美辞麗句として
「これからのビジネスパーソンには人間力が求められます」。しかし、研修の中身が「挨拶をしっかり」「感謝を忘れず」といった一般論に終始することも少なくない。どんな行動が「人間力の向上」なのか、どう成長を測定するのか、実践的な指針が示されなければ、受講者は「ためになった気がする」という曖昧な満足感しか得られない。
パターン④:昇進審査での恣意的判断として
「彼は業績もあるが、部長にするには人間力が…」。ここでの「人間力」とは、社内政治力なのか、それとも「まだ昇進させたくない」という結論ありきの理由づけだろうか。明確な基準がないまま使われることで、昇進判断は恣意的になり、組織への不信感を招く。
パターン⑤:経営者の訓示での精神論として
「社員にはもっと人間力を磨いてほしい。それが競争力につながる」。社員は「具体的に何をすればいいのか?」と思っている。具体策が示されないまま精神論だけが繰り返され、「人間力」は「頑張れ」といった空虚なスローガンになってしまう。
これら5パターンに共通するのは、「人間力」が思考停止と責任回避の道具になっている点だ。具体的な行動を指し示すことなく曖昧な言葉で済ませては、誰も成長しない。
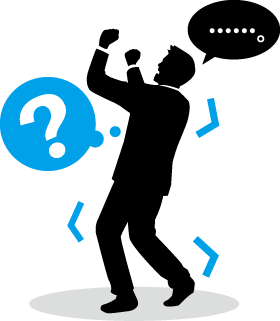
■「人間力」を具体的行動に翻訳。測定可能な指標へと落とし込む
どうすればいいか。答えは明快だ。「人間力」という言葉を使うときは、必ず具体的な行動と測定可能な指標に翻訳するのである。
たとえば内閣府の3層構造をビジネス現場で再構成すると、「人間力」は主に以下の5つの要素に分解できる。
すなわち
①コミュニケーション力
―相手に伝わる言葉を選び、理解を確認する力
②リーダーシップ
―目標を示し、人を動かし、結果を出す力
③問題解決力
―課題の本質を見抜き、実行可能な解決策を導く力
④自己成長力
―自分の弱みを認識し、継続的に学び改善する力
⑤倫理観と誠実さ
―短期的利益より長期的信頼を優先する判断力
これらをさらに具体的な行動レベルに落とし込むのだ。
①コミュニケーション力→具体的行動
・会議で発言する前に、「この発言は誰にどんな価値を与えるか」を3秒考える
・指示を出した後、「今の説明で理解できた点と不明な点を教えて」と確認する
・メール送信前に、「この文章は相手にどう読まれるか」を一度読み直す
・月に1回、他者から自分のコミュニケーションについてフィードバックをもらう
〈測定可能な指標例〉
部下からの「指示が明確だった」というフィードバック率、会議での発言に対する「わかりやすい」という評価回数、メールの往復回数(少ないほど良い)
②リーダーシップ→プロジェクトの目的を明確に伝える
・プロジェクト開始時に、「なぜこの仕事をするのか」を全員が説明できるまで対話する
・週次ミーティングで、メンバーの貢献を具体的に言語化して承認する
・意思決定の際、「私はこう考えるが、異論がある人は?」と必ず問いかける
・チームの目標達成後、「次はどんな挑戦をしたいか」をメンバーに尋ねる
〈測定可能な指標例〉
プロジェクトの期限内完了率、メンバーの自発的な改善提案の件数、チーム内での心理的安全性スコアなど
③問題解決力→トヨタの「5回のなぜ」を実践する
・問題が起きたら、最低5回「なぜ?」を繰り返して真因を探る
・解決策を考える前に、「この問題の本質は何か」を一言で表現する
・複数の解決策を比較し、「最悪の場合どうなるか」をシミュレーションする
・実行した解決策の結果を振り返り、「次はどう改善するか」を記録する
〈測定可能な指標例〉
同じ問題の再発率(低いほど良い)、問題発見から解決までのリードタイム、解決策の実行成功率
④自己成長力→定期的な振り返りと学習習慣
・週末に15分、「今週の失敗」と「そこから学んだこと」を書き出す
・四半期に1回、信頼できる同僚や上司に「私の弱みは何か」を率直に聞く
・読んだ本や記事の内容を、翌週の仕事で最低1つ実践してみる
・年に1回、「3年後の自分はどうなっていたいか」を具体的に言語化する
〈測定可能な指標例〉
学習時間(週あたり)、新しいスキルの習得数(年間)、過去に指摘された弱みの改善度(360度評価)
⑤倫理観と誠実さ→短期的利益より長期的信頼
・判断に迷ったとき、「この選択を5年後に誇れるか」を自問する
・不都合な事実も隠さず、早めに関係者に報告する習慣をつける
・部下のミスを自分の責任として上司に報告する
・「楽な選択肢」と「正しい選択肢」が異なるとき、あえて正しい方を選ぶ
〈測定可能な指標例〉
部下やチームからの信頼度(匿名アンケート)、重要な問題の報告スピード、コンプライアンスの実践
■「○○力」の迷宮に迷い込まない。自分なりに優先順位をつける
ここまで「人間力」を分解してきたが、「こんなに多くの能力をすべて高めるのは不可能だ」と感じたかもしれない。その通りである。実際、「人間力」を構成する要素は人によって様々である。
ミュージシャンで東日本国際大学の東洋思想研究所の客員教授も務める西宮佑騎氏は、次の18の力を挙げている。「生命力、行動力、智力、決断力、体力、吸収力、遠心力、瞬発力、気力、破壊力、忍耐力、突破力、集中力、記憶力、説得力、包容力、経済力、指導力」。この中で遠心力はビジネス界隈では耳馴染みのない言葉だが、西宮氏の説明によると、「遠いところまで自分の心を伝える力」と解説している。
また歯学博士と経営学博士を持ち、独自哲学、「ライフコンパス」を作り上げ、全国で講演活動を行っている歯科医の井上裕之氏は、人間力を「社会で価値ある人生を生きるための総合力」と定義して、その総合力を高めていくための7つの習慣、すなわち、「素直さ、学び、自責、礼儀礼節、立ち直る(失敗)、自愛、成長」の習慣の重要性を訴えている。個別の◯◯力という要素より、それらを獲得していくための姿勢に重きをおいている。
無数の「○○力」に溺れるより、態度や姿勢、習慣こそが人間力のベースになるということは、説得力がある。
■すべてを高める必要はない―戦略的な取捨選択
重要なのは、何もかも高めようとするのではなく、今の自分にとって何が最も重要かを見極め、優先順位をつけ、そのための態度や習慣を決めていくことだ。稲盛さんは「完璧な人間などいない。大切なのは、自分の弱みを知り、それを補う努力をすることだ」と語り、松下さんも「自分の長所を活かし、短所は他者の力を借りて補えばいい」と説いた。時間もエネルギーも有限である以上、選択と集中が不可欠である。
■優先順位をつけるための3つの視点
では、どう優先順位をつければいいのだろうか。3つの視点を提示する。
視点①:今の役割で最も求められる能力は何か
営業職とエンジニア、プレイヤーとマネージャーでは、求められる能力が異なる。
| 営業職 | マネージャー | |
|---|---|---|
| 優先度高 | 傾聴力、提案力、信頼構築力 | 育成力、傾聴力、判断力、ビジョン発信力 |
| 優先度低(今は) | 育成力、組織マネジメント力 まずは目の前の顧客に集中すべきである。 | 専門的技術力、細部の実行力 |
マネージャーはチームを育て、方向性を示すことが最重要であり、プレイヤー時代の細かい作業は手放し、部下に任せるべきである。自分の今の役割で成果を出すために何が重要かを明確にし、そこに集中投資する。
視点②:自分の致命的な弱みは何か
すべての弱みを克服する必要はないが、信頼を失ったり、重大なトラブルを招いたりする「致命的な弱み」は早急に改善すべきである。
致命的な弱みの例:約束を守らない、感情をコントロールできず怒鳴る、ミスを隠蔽・責任転嫁する、報連相をしない、などである。これらは、他の能力がどれほど高くても、それを帳消しにしてしまう。最低限のラインをクリアすることが前提条件だ。一方で、「ちょっと苦手」程度の弱みは、無理に克服するより、合格点を目指すのが現実的である。
視点③:将来のキャリアで必要になる能力は何か
今すぐ必要でなくても、次のキャリアステージで必須となる能力を少しずつ準備しておくことも重要である。
例:プレイヤーからマネージャーを目指す場合、プレイヤーのうちから後輩に仕事を教えたり、小さなチームをまとめたりする経験(傾聴力、フィードバック、目標管理)を積んでおく。そうすれば、管理職になったときにスムーズに移行できる。今の仕事を疎かにせず、余裕のある部分で将来の準備をするバランスが重要である。
トヨタの「カイゼン」が一度に一つずつテーマを絞るように、すべてを同時に改善しようとすれば、結局何も変わらない。松下さんや稲盛さんも、すべてに秀でていたわけではなかった。松下さんは「衆知を集める力」を軸に技術者の知恵を引き出し、稲盛さんは「哲学を貫く力」という信念で強固な組織を作った。「人間力」を高めるとは、すべてを完璧にすることではなく、自分にとって最も重要な能力に集中し、それを具体的な行動として日々実践することなのである。
■ビジネス力の高いリーダーは「◯◯力」の抽象語に逃げない
「人間力」という言葉を安易に使う人は、物事を分解し、具体的に伝える力が弱いかもしれない。ビジネス力の高いリーダーとは、人間力に限らず、「◯◯力」という抽象語に逃げず、具体的な行動指針を示せる人だ。
優れたリーダーは、「君には人間力が足りない」「もっとコミュニケーション力を磨け」とは言わず、「週次報告が遅れがちだ。毎週金曜17時までに、進捗・課題・予定を3行で送ってほしい」「会議で人の話を遮ることが多い。まず最後まで聞いて、要約を返してから自分の意見を述べよう」と言う。
さらに優れたリーダーは、部下の優先順位付けも手伝う。「君には改善すべき点がいくつかあるが、今期はまず『週次報告の徹底』だけに集中してくれ。それができたら次へ進もう。一つずつ、確実に改善していこう」などだ。
「人間力」は悪い言葉ではないものの、曖昧なままでは思考を停止させ、成長を妨げる凶器にもなる。ビジネスパーソンに求められるのは、「人間力」といった抽象語を具体的に翻訳する力である。その中身を解像度高く分解し、誰もが行動できるレベルに落とし込む―この習慣こそが真の「ビジネス力」であり、皮肉にも「人間力」の本質なのかもしれない。
参考
【書籍・資料】●「人間力戦略研究会」報告書[内閣府]●人生100年時代の社会人基礎力について[経済産業省]●「人間力を磨くー東日本国際大学講演集」東日本国際大学東洋思想研究所[昌平黌出版会]●「トヨタ式人間力」若松義人、近藤哲夫[ダイヤモンド社]●「一流の人間力」井上裕之[ディスカバー]●「素直な心になるために」松下幸之助[PHP 文庫]●「道をひらく」松下幸之助[PHP]●「生き方」稲盛和夫[サンマーク出版]●「働き方」稲盛和夫[三笠書房]
【WEB】●内閣府 ● GLOBIS CAREER NOTE ● school for business● The 21online ほか
POINT
■ 実は「人間力」は内閣府によって“公的”に定義されている
■「社会を構成し運営するとともに、自立した一人の人間として力強く生きていくための総合的な力」が内閣府の定義
■ 内閣府の人間力は、知的能力的要素、社会・対人関係力的要素、自己制御的要素の3層に分かれている
■ 人間力は人材育成を経営の礎とした経営者たちの行動指針に倣う
■ トヨタが求める「人間力」は、実は徹底した「現地現物」の習慣
■ 松下幸之助氏の「人間力」は「素直な心」と「衆知を集める力」
■ 稲盛和夫氏が説く「人間力」は「利他の心」と「哲学を持つこと」
■ 優れたビジネスリーダーは「◯◯力」の抽象語に逃げず、自分なりに優先順位をつける
■ 優先順位をつけるための3つの視点、「今の役割で最も求められる能力は何か」「自分の致命的な弱みは何か」「将来のキャリアで必要になる能力は何か 」
■ すべてを高める必要はない。戦略的な取捨選択を取る
■ 人間力を高めるためには、身につけたい力を求めていく姿勢と習慣が重要
ビジネスシンカーとは:日常生活の中で、ふと入ってきて耳や頭から離れなくなった言葉や現象、ずっと抱いてきた疑問などについて、50種以上のメディアに関わってきたライターが、多角的視点で解き明かすビジネスコラム