経営は「執事」が担う時代へ!持続的成長を促すイマドキの経営の中心概念スチュワードシップって何?
2024年、ある数値が話題となった。日本企業の実践的人材育成の要、「OJT」の実施率が調査対象7カ国中最下位の39.8%だったからだ。日本の質の高い人材は「企業内大学」と称賛された実践的で手厚い日本型人材育成システムに支えられてきたが、もはや過去の栄光となりつつある。こうしたなか、今、マネジメント界隈で注目されているのが「スチュワードシップ」というマネジメント概念である。あまり耳馴染みのない言葉かもしれないが、実は失われつつある長期視点に立った日本型人材育成と親和性の高い考え方だ。もしかしたら日本の失われた30年を取り戻すかもしれない、話題のスチュワードシップの中身を紐解く。

目次
■投資の世界における「日本版スチュワードシップ・コード」って何?
スチュワードシップという言葉が、いつ頃日本で広く認知されるようになったかを探ると10年以上時計を戻す必要がある。
2014年2月に金融庁が策定した「日本版スチュワードシップ・コード」である。これは機関投資家が投資先企業との建設的な対話を通じて、企業の持続的成長と中長期的な企業価値向上に貢献する責任を明確化したものである。
2025年6月には改訂版が施行されたが、いわゆるESG投資項目について企業は積極的に資産を振り分け、その投資の取り組みを投資家に開示せよ、という内容を強化せよということだ。とりわけ、スチュワードシップが注目された。
■経営理論としてのスチュワードシップ理論
ずばりスチュワードシップとはなにか。それは「預かったものを大切に管理し、次世代に引き継ぐ責任」という概念である。
実は経営学の分野では2014年よりさらに時代を遡り、1991年にオーストラリアの社会学者のレックス・ドナルドソン教授とアメリカの経営学者ジェームス・デイヴィス教授によって提唱された「スチュワードシップ理論」が始まりだ。この理論は、従来のエージェンシー理論、すなわち「経営者は利己的に行動するため監視が必要とする性悪説」とは対照的に、経営者や従業員は本質的に組織の利益を重視し、責任を果たそうとする存在であるという性善説に立っていることが特徴だ。
監視ではなく、見守り撫育するのが経営者の役割とする。特徴的なのはスチュワードシップ理論では、経営者を「スチュワード(執事、管財人)」と位置づけ、組織を自己の所有物ではなく「預かっているもの」として捉えることだ。つまり、優れた教育機関の校長や理事長があるべき経営者の姿ということである。よって経営者の役割は「短期的な利益の最大化」ではなく、「組織の持続的な繁栄」と次世代への継承となる。
■アレックス・ヒル教授の「センテニアルズ(100年企業)」研究で注目
スチュワードシップを中核とした経営は、企業の持続的成長を促している。英国ロンドン・ビジネススクールのアレックス・ヒル教授は、2010年から13年間にわたり、世界中の100年以上存続し、かつ卓越した成果を上げ続けている組織=「センテニアルズ」を調査した。調査対象は企業だけでなく、大学、病院、軍隊、スポーツクラブ、宗教団体まで多様な組織形態が含まれている。
これらの組織に共通していたのは、短期的な成果よりも長期的な存続と繁栄を重視し、そのために「スチュワード型リーダー」が組織を率いているという点だった。センテニアルズのリーダーは平均10~15年という長期にわたって在職している。これは、一般的なCEOの平均在職期間である4~5年の2倍以上の長さである。
■スチュワードシップを実践するための4つの普遍的原則
ヒル教授は、センテニアルズ研究から、スチュワードシップを実践するための4つの普遍的原則を抽出している。
◆原則1:
「50~70人のコミュニティ単位で組織を運営する」
大規模組織であっても、内部を50~70人の小集団に分割し、それぞれが自律的に運営される。これにより、一人ひとりの顔が見える関係性が維持され、育成責任が明確化される。
◆原則2:
「コミュニティの4分の1をスチュワードとして育てる」
スチュワードは単なる管理職ではなく、人を育てることに情熱を持ち、組織の歴史と価値観を体現し、次世代に継承する使命を自覚している存在である。
◆原則3:
「スチュワードは最低10年以上在職する」
短期的な成果主義では、人材育成の成果は見えにくい。10年以上の在職により、育てた人材が成長し、組織に貢献する姿を見届けることができる。
◆原則4:
「後継者は2年前から準備を始め、80%は内部から登用される」
内部登用を基本とすることで、スチュワードシップの精神が世代を超えて継承される。
■日本企業の歴史的変遷─企業が「大学」だった時代
スチュワードシップは、決して舶来産の概念ではない。むしろ、日本型経営の核となっていた。すくなくとも戦後復興からバブル経済崩壊まではそうだった。
戦後復興から高度成長期、そしてバブル経済期に至るまで、日本企業は世界に冠たる人材育成システムを構築していた。終身雇用と年功序列を前提に、新入社員は徹底したOJTを受け、数年ごとのジョブローテーションを通じて多様な経験を積んだ。
当時の日本企業は、まさにスチュワードシップを体現していた。管理職は部下の育成を最重要任務と認識し、10年、20年という長期スパンで人材を育てることに情熱を注いだ。企業は「人材を預かり、育て、次世代に引き継ぐ」という責任を果たしていたのである。
しかし、1991年のバブル崩壊を境に、状況は一変する。長期低迷の中で、日本企業は米国流の株主資本主義を急速に導入し、短期的な利益とコスト削減を最優先するようになった。
人材育成は「コスト」と見なされ、真っ先に削減対象となった。社内研修は縮小され、OJTの時間は大幅に削減された。成果主義の導入により、管理職は部下育成よりも自らの業績達成に追われるようになった。
さらに深刻だったのは、管理職の在職期間の短縮化である。頻繁な組織再編と短期成果主義により、管理職が同じポジションに留まる期間は3~5年程度となった。これでは、部下を10年単位で育てることなど不可能である。
■2024年の現実─OJT実施率39.8%の衝撃
そして2024年、日本のOJT実施率は39.8%と調査対象7カ国中最下位に沈んだ。かつて日本企業の競争力の源泉だった人材育成システムは、完全に崩壊したと言っても過言ではない。
中小企業の状況はさらに深刻である。約70%の企業が中核人材の不足を訴えているが、人材不足の本質は「採用できない」ことではなく、「育てられない」ことにある。多くの中小企業では、人材育成の仕組みが存在せず、社員は「塩漬け人材」という状態に置かれている。
だからこそ、スチュワードシップが注目されるのである。日本の企業は人材は「使うもの」ではなく「預かり、育て、次世代に引き継ぐもの」という概念を宿すべきなのである。
■世界的潮流の転換。株主第一主義からステークホルダー資本主義へ
世界も一気に動いた。2019年8月、アメリカの経団連とも言われる、主要企業181社のCEOが参加する「ビジネス・ラウンドテーブル」が、画期的な声明を発表した。「企業の目的」を再定義し、株主利益の最大化を最優先とする従来の立場を撤回したのである。
この声明では、企業は株主だけでなく、顧客、従業員、サプライヤー、地域社会といった「すべてのステークホルダーに対して責任を負う」と明言された。注目すべきは、「従業員への投資」が最優先事項の一つとして掲げられたことである。
日本でも、2022年に岸田政権が「人への投資」を経済政策の柱として掲げ、5年間で1兆円規模の予算を投じる方針を打ち出した。さらに2023年3月には、従業員数1000人以上の上場企業に対して人的資本情報の開示が義務化された。
これは、人材を「コスト」ではなく「資本」として捉え、その育成と活用が企業価値に直結するという認識の転換を意味している。
■サーバントリーダーシップとスチュワードシップの関係
ところでスチュワードシップを語る上で欠かせないのが、「サーバントリーダーシップ」という概念だ。サーバントリーダーシップは、1970年にアメリカの実業家、ロバート・K・グリーンリーフ氏によって提唱された。
「まず奉仕者であり、その後にリーダーとなる」という発想に立ち、権威や命令ではなく、支援と育成を通じて人々を導く。グリーンリーフ氏は、サーバントリーダーシップの10の特性の一つとして「スチュワードシップ」を明示的に挙げ、「信頼して重要なことを任せられること」「執事のように周囲に貢献する気質」と定義した。
サーバントリーダーシップとスチュワードシップは、密接に関連しながらも異なる焦点を持つ。
サーバントリーダーシップは、個人のリーダーシップスタイルに焦点を当てる。リーダー自身が奉仕者としての姿勢を持ち、部下の成長を最優先する。これは「どのようにリーダーシップを発揮するか」という行動原理である。
スチュワードシップは、組織全体の育成責任と継承システムに焦点を当てる。組織を「預かっているもの」と捉え、人材育成を制度化・体系化する。これは「何に責任を持つか」という役割定義である。
実践面では両者に重要な違いもある。
サーバントリーダーシップは、リーダー個人の資質や姿勢に依存する側面が強い。個人が宿す傾聴力、共感力、謙虚さといったサーバントリーダーシップの能力は個人の内面的成長によって獲得される。
対してスチュワードシップは、組織の仕組みとして構築できる。つまりヒル教授が提示した4つの原則は、いずれも人事制度や組織設計によって実現可能なのだ。
この違いは中小企業にとって重要な示唆となる。カリスマ的なサーバントリーダーが不在でも、スチュワードシップの仕組みを導入することで、組織全体の育成力を高めることができる。逆に、優れたサーバントリーダーがいても、スチュワードシップの制度がなければ、その人物の退任とともに育成文化が消失してしまうのだ。
つまり両者は補完関係にあり、統合的に実践することで、個人の資質に依存しない持続的な人材育成システムが構築されるのである。
■グローバル企業の先進的実践
ではスチュワードシップを取り入れた企業ではどのような効果が現れているのだろうか。いくつか事例みてみよう。
【事例1】コストコホールセール(アメリカ)─「従業員への投資」が競争力を生む
米国の会員制倉庫型小売チェーン、コストコの離職率はわずか8%(業界平均は60%超)である。平均時給は30.20ドル(2025年)と、競合他社の2倍近い水準。昇進の90%以上が内部登用という人事方針を採用している。
創業者ジム・シネガル氏は、「従業員を大切にすれば、顧客を大切にする。顧客を大切にすれば、株主に報いることができる」という哲学を貫いた。コストコでは、採用から育成まで長期視点で投資する。新入社員には丁寧なOJTが施され、複数の部門を経験させながら適性を見極める。店舗マネージャーの多くは、アルバイトから昇進した内部人材である。
【事例2】サウスウエスト航空(アメリカ)─「従業員第一、顧客第二」の哲学
効率的な経営で知られるアメリカの格安航空会社サウスウエスト航空。同社はあえて「従業員第一、顧客第二」を掲げる。創業者ハーブ・ケレハー氏は、「従業員を大切にすれば、従業員が顧客を大切にする」という信念を持っていた。
新入社員は3週間にわたる集中研修を受け、企業文化、歴史、価値観を学ぶ。管理職候補者には、さらに高度なリーダーシップ研修が用意され、「サーバントリーダーシップ」の実践が求められる。同社は50年以上にわたって黒字経営を続けている。
【事例3】セムコ(ブラジル)─民主的経営とスチュワードシップの融合
南米ブラジルのセムコ社。リカルド・セムラー氏が1980年代に同社の経営を引き継いだ際、従来の権威主義的経営を完全に廃止し、従業員の自律性と参加を最大化する民主的経営モデルを構築した。
従業員が自分の上司を選び、自分の給与を決定し、勤務時間や勤務場所を自由に設定できる。その自由度は多くの企業経営者を驚かせた。その根底にあるのは「人間は本質的に責任感があり、信頼に値する」というスチュワードシップ理論の性善説である。
セムラー氏は、「私たちは会社を所有しているのではなく、一時的に預かっているだけだ。次世代により良い形で引き継ぐことが私たちの責任である」と述べている。この哲学のもと、セムコは過去30年間で売上を30倍に成長させている。
【事例4】ビュートゾルフ(オランダ)─自己管理型組織とスチュワードシップ
オランダの在宅医療組織ビュートゾルフは、管理職をほとんど置かない「自己管理型組織」として世界的に注目されている。看護師たちは10~12人のチームを自律的に運営し、患者ケア、スケジュール調整、予算管理まで自分たちで行う。
創設者のヨス・デ・ブロック氏は、「看護師は専門職であり、彼らを信頼して権限を委譲すれば、最高のケアを提供できる」という信念を持っていた。新入看護師には経験豊富なチームメンバーがメンターとして付き、1年以上かけて育成する。
患者満足度はオランダで最高評価を獲得し、ケアの質を維持しながらコストを従来の医療機関より40%削減している。このビュートゾルフのモデルは、ヒル教授が提唱した「50~70人のコミュニティ単位で組織を運営し、4分の1をスチュワードとして育てる」という原則を見事に実践している。
■日本企業の実践例
日本にもスチュワードシップの実践企業がある。
【事例1】ダイキン工業─デジタル人材育成とスチュワードシップ
空調機器メーカーのダイキン工業は、2019年に「DAIKIN Information & Communications Technology College(DICT)」を設立し、全社員を対象としたデジタルリテラシー向上プログラムを開始した。
DICTの特徴は、単なるIT研修ではなく、デジタル技術を活用して業務変革を実現できる人材を長期的に育成することにある。2024年までに2,000人のデジタル人材を育成するという目標を掲げている。
デジタル人材育成には一人当たり数百万円のコストがかかるが、同社は「人材は使うものではなく、預かって育てるもの」という考えのもと、惜しみなく投資している。こうした取り組みの結果、ダイキン工業は「DX銘柄2024」に選出された。
【事例2】伊那食品工業─「年輪経営」と「百年カレンダー」
長野県駒ヶ根市に本社を置く寒天メーカー、伊那食品工業は、スチュワードシップ経営の日本における代表例だ。その崇高とも呼べる理念型経営は、あのトヨタ幹部も見習ったほど。
同社の基底となる理念が、1958年に破綻状態の同社に社長代行として入社した塚越寛氏がつくった「いい会社をつくりましょう」というシンプルなビジョンと「年輪経営」という独自の経営哲学だ。
年輪経営とは、樹木が一年に一輪ずつ年輪を刻むように、急成長を追わず、着実に成長を積み重ねる経営である。塚越氏は、「会社は社員とその家族の幸せのために存在する」と明言し、人材育成に惜しみなく投資を行った。
同社を訪れた人がまず目を留めるのが、各事務所に掛けられた「100年カレンダー」だ。100年という時間が長いようであっという間であり、その間にできることが限られているという教訓を可視化したもので、この100年カレンダーは新入社員の入社時に配られ、自分のキャリアを長期的に考える機会が与えられる。
伊那食品工業は、売上高を約50年間で100倍以上に成長させながら、一度もリストラを行っていない。同社は「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞を受賞している。
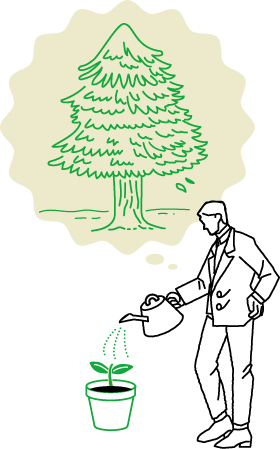
【事例3】サイボウズ─「100通りの働き方」と離職率の劇的改善
グループウェア開発のサイボウズは、かつて離職率28%という深刻な人材流出に悩まされていた。しかし、創業者の青野慶久社長が「会社は社員を預かっている」というスチュワードシップの視点に立ったことで、状況は一変した。
サイボウズが導入したのが、「100通りの働き方」という人事制度である。勤務時間、勤務場所、働き方を社員が自由に選択でき、育児や介護と両立しながらキャリアを継続できる環境を整備した。
さらに、情報共有の徹底により、若手社員でも経営の全体像を理解し、自律的に学習・成長できる環境が実現されている。こうした取り組みの結果、サイボウズの離職率は3%台まで低下した。
【事例4】未来工業─「3ナイ主義」と社員の自律性
岐阜県に本社を置く電気設備資材メーカー、未来工業は、「日本一社員が幸せな会社」として知られている。創業者の山田昭男氏が掲げたのが、「残業ナシ、ノルマナシ、報連相ナシ」という「3ナイ主義」である。
未来工業の年間休日は140日と、日本企業の中でも最高水準である。にもかかわらず、同社は高収益を維持し、「ホワイト企業大賞」を受賞している。その秘密は、社員の自律性と創意工夫を最大限に引き出す経営にある。
人材育成においては、「教えすぎない」ことを重視する。新入社員には基本的な業務を教えた後、自分で考えて行動する機会を与える。未来工業の経営は、スチュワードシップ理論の性善説を体現している。
■現代の魅力ある企業への進化「卒業生」が戻る組織のスチュワードシップ
2024年現在、日本企業は深刻な人材不足に直面している。こうした中で、先進的な企業では「退職」という言葉を使わず、「卒業」という表現を用いるようになった。
「卒業」という表現の背景には、スチュワードシップの本質的な考え方がある。企業は人材を預かり、育成し、次のステージへと送り出す。そして、卒業生が外部で得た経験やスキルを持ち帰り、再び組織に貢献する──。この循環こそが、持続的成長を実現する現代的なスチュワードシップの形なのである。
■アルムナイ制度の拡大
こうした人材観の転換を具体的な制度として実現したのが、「アルムナイ制度」である。アルムナイとは、大学の「卒業生」を意味する言葉だが、企業においては退職者とのつながりを維持し、再雇用の道を開く人事施策を指す。
2024年のリクルートワークス研究所の調査によれば、日本企業の32.8%が退職者の再雇用制度を持ち、実際に再雇用の実績がある。LinkedInの調査では、再雇用された従業員の離職率は、通常の中途採用者よりも約15%低いことが明らかになっている。
アルムナイ制度は、トヨタ自動車、みずほフィナンシャルグループ、三菱UFJ銀行、パナソニック、マクロミル、アクセンチュアなどが先進的に実践している。2024年には「ジャパン・アルムナイ・アワード」が開催され、アルムナイ施策は日本企業の人事戦略の主流となりつつある。

■「預かって育て、卒業させ、また戻る」循環の価値
アルムナイ制度がスチュワードシップと深く結びつく理由は、その根底にある人材観にある。従来の終身雇用モデルでは、退職者は「裏切り者」と見なされたが、アルムナイ制度では、退職者を「卒業生」として尊重し、継続的な関係を維持する。
この転換は、企業にとって多くのメリットをもたらす。再入社する卒業生は、企業文化を理解しており、業務にも精通している上、外部企業で新しいスキルや知識を獲得し、異なる企業文化を経験している。この多様な経験が、組織に新しい視点とイノベーションをもたらすのである。
アルムナイ施策は、スチュワードシップの現代的な進化形である。人材を「預かり、育て、卒業させ、また迎える」─。この循環を実現する組織こそが、長期にわたって持続的に成長し、人材に選ばれる魅力ある企業となるのである。
「預かり育てる責任」─これは単なる経営手法ではなく、企業が社会に対して果たすべき使命である。スチュワードシップ経営の実践は、今日から始めることができる。あなたの組織でも、「人材を預かり、育て、次に引き継ぐ」という一歩を踏み出してみてはどうだろうか。
参考
【書籍・資料】●『センテニアルズ “100 年生きる組織” が価値をつくり続ける12 の習慣』アレックス・ヒル/小山龍夫(監修)/島藤真澄(監訳)/服部聡子(訳)[KADOKAWA] ●金融庁『日本版スチュワードシップ・コード』 ●独立行政法人労働政策研究・研修機構『人材育成と能力開発の現状と課題に関する調査』 ●中小企業庁『中小企業の人材確保と育成に関する調査』 ●経済産業省『人的資本経営の実現に向けた検討会報告書』●週刊東洋経済 ●週刊ダイヤモンド ●日経ビジネス ●『ビジョナリー・カンパニー 時代を超える生存の原則』ジム・コリンズ/山岡洋一(訳)[日経BP]●『知識創造企業』野中郁次郎/竹内弘高/梅本勝博(訳)[東洋経済新報社]●『人的資本経営まるわかり』岩本隆[PHP 新書]●『日本でいちばん大切にしたい会社』坂本光司[あさ出版]●『サーバント・リーダーシップ』ロバート・K・グリーンリーフ/金井壽宏(監訳)[英治出版]●『自主経営組織のはじめ方―現場で決めるチームをつくる』アストリッド・フェルメール/ベンウェンディング/ヨス・デ・ブロック[英治出版]●『The Good Jobs Strategy』ゼイネップ・トン[New Harvest]●『リストラなしの「年輪経営」: いい会社は「遠きをはかり」ゆっくり成長』塚越寛[光文社知恵の森文庫]
【WEB】●日本の人事部 ●日本経済新聞 ●東洋経済オンライン ●日本サーバントリーダーシップ協会 ほか
POINT
■ スチュワードシップとは「預かり育てる責任」である
■ 百年企業に共通する「スチュワード型リーダー」の4原則
■ OJTができない日本企業が続出している
■ 世界的潮流の転換─ステークホルダー資本主義への移行
■ サーバントリーダーシップとスチュワードシップを統合する
■「 従業員への投資」が競争力を生むコストコ
■ 従業員が自分の上司を選び、自分の給与を決定するブラジルのセムコ
■ 2000人のデジタル人材を育成するエアコンのダイキン工業
■ 年輪経営の伊那食品工業と3ナイ主義の未来工業
■ スチュワードシップの進化系アルムナイ施策
■「 預かり育てる責任」が未来を拓く
ビジネスシンカーとは:日常生活の中で、ふと入ってきて耳や頭から離れなくなった言葉や現象、ずっと抱いてきた疑問などについて、50種以上のメディアに関わってきたライターが、多角的視点で解き明かすビジネスコラム