60年ぶりの丙午に振り返る 60年で何がどう変化したのか?
今年は午年。前回から60年目という丙午の年である。江戸時代の「八百屋お七」の故事から、丙午生まれの女性は気性が荒いという迷信が生まれた。前回の1966年は日本中で産み控えが起き、出生数は前年比25%減という異常事態となった。だが皮肉なことに、当のお七が本当に丙午生まれだったかもどうも怪しいという。根拠のない迷信に、国全体が踊らされたのだ。
前回の丙午から、お七の情熱を超える勢いで、時代は大きく変わった。長足の歩みを見せるテクノロジーに支えられ、パソコンやAIロボットをはじめ、インテリジェントビルやEV車、いまや空飛ぶクルマの時代を迎えつつある。こうした「目に見える」変化もさることながら、それまで「当たり前」とされてきた手法やセオリー、慣習も大きく変化している。たとえば営業は「足で稼ぐ」から「選ばれる仕組みづくり」へ、ものづくりは「大量生産」から「継続改善と循環」へ。食は家庭の営みから社会参加の意思表明となり、交通は所有より使い分けが当たり前になった。かつて疑いもなく信じられていた価値はくつがえり、新しい前提が静かに根づいた。未来への羅針盤として世の中の何が変わったのか、この機会に60年を改めて振り返ってみる。

目次
■営業の常識は「訪問」から「共創」へ
かつて営業の基本は「足で稼ぐ」ことだった。新人は電話帳の1ページ目から順に、見知らぬ会社へ飛び込む。断られても、断られても、次の扉を叩く。「100軒回って1件取れれば上出来」。訪問件数こそが成果であり、努力の証だった。しかし、その光景は一変した。顧客と会う前に、すでに半分の勝負が決まってしまう世の中になってしまったからだ。
まず「出会い方」が変わった。「飛び込み」訪問よりも、まずは検索、SNSで情報を得て、次に自社サイトやSNSで発信する。そのうえで関心を持ってもらった顧客にダイレクトメールを送り、サンプルを送り、購買につなげる。つまり営業とは企業が顧客を見つける側から、顧客から見つけてもらう側に変わったと言える。
その「提案の内容」も変化している。製品やサービスの説明は機能やスペックの羅列では足りず、顧客の課題を理解し、その解決方法を描けるかが勝負どころとなった。営業の役割は販売ではなく、顧客の課題解決となった。
さらに営業は「チーム戦の時代」に突入した。商談の裏側ではマーケティングが顧客課題の解決法のシナリオを創出し、カスタマーサクセスがそのシナリオの定着を支え、データ分析が意思決定を補強する。営業は孤立した個ではなく、顧客体験を生みだすチームのハブとなる。属人的スキルで表立った数字を競うことが意味を持たなくなった。

数字は売上の多寡より、そこに至る「信頼獲得のプロセス」で設定されるKPIなどの数字が大きな意味を持つようになった。誠意や根性だけでは不十分で、正確な情報提供、透明性、返答速度など、定量化された信頼の指標の組み合わせで営業が評価されるようになった。
営業はもはや、訪問、会話、契約という直線的な行為ではなく、顧客理解から事業共創へとつながる長いプロセスをデザインする専門スキルとなっている。昭和の「外回り営業」は、令和では「価値案内人」へ姿を変えた。営業とは、カスタマージャーニーという言葉があるように、顧客の成長を支援し、ともに長い旅を歩く役割なのだ。
丙午to丙午 60年の営業変化史
・1960s 訪問営業・飛び込みが主流
・1970s 法人営業部門が拡充、トークスクリプト標準化
・1980s 大量テレアポ時代へ
・1990s CRM黎明、名刺管理・データ化が始まる
・2000s WEB展示会・フォーム経由問い合わせが増加
・2010s インバウンド型営業、SaaSセールス登場
・2020s インサイド+フィールド+CSの連携が必須、営業が事業の入口から出口へ設計
■マーケティングの常識は「告知」から「体験設計」へ
その営業と表裏一体のマーケティングはどう変わったのだろうか。かつてマーケティングは大量につくった商品を不特定多数に売り込むことだった。テレビ、新聞、雑誌は、企業が国民全員に語りかけられる魔法の装置だった。「新発売!」と叫べば、翌日には店頭に行列ができた。一方通行で十分だったのだ。消費者は聞く側、企業は語る側。その役割は明確だった。
しかし現代では、企業の声を届けるだけでは不十分となった。消費者の周りは情報に溢れ、何を買うかより「どんな気持ちになるか」に価値が移っていった。
マーケティングは売る前に耳を澄ます作業に変化した。「感情の理解」が中心軸になったのだ。
顧客は商品によって得られる物語、社会的意味、所属感に注目する。サステナビリティや理念への共感が選択の基準となり、それを語れない企業は選ばれなくなった。さらに「購買後の世界」が重視されるようになった。売って終わりではなく、使い続けてもらうことがブランド価値を高める。マス媒体を使った広告は、認知度、購買意欲を高めることに主眼を置いていたが、コミュニティ形成、サブスクモデル、継続的アップデートなど、企業と顧客の関係は長期契約へと変化している。
マーケティングとは、商品を広める技術から、顧客人生に寄り添う技術へと変わったのだ。
また80年代頃からマーケティングの中核に座るようになったのが、ブランディングである。かつてロゴや広告制作はマーケティングの一部の機能であったが、ロゴや広告を含めた、企業や活動の“存在理由”を示す作業に変わっていった。CM、店頭、パッケージ……消費者は視覚から企業を認識していたが、今は企業が発信する存在理由と消費者がイメージする存在理由と合致させることが重視されるようになった。そのイメージの一致がブランディングの核となっている。

消費者はブランドや企業をアクションや姿勢で判断するようになった。背景にはSNS普及がある。ミスや不誠実な活動は瞬時に広まり、言葉と行動が一致しなければ評価を失う。逆に小さな企業でも、誠実な姿勢で長期的に環境や顧客重視、従業員尊重に取り組んでいけば支持を得るようになった。
こうしてブランディングがマーケティングの中核になると、ブランドは企業単独でつくれなくなった。消費者、社員、パートナー、地域社会、すなわちステークホルダーによって共感され、語り継がれていかなければ、ブランドは成立しなくなったのだ。
丙午to丙午 60年のマーケティング変化史
・1960s TV広告全盛期、マスプロダクトがヒット
・1970s 大型量販店台頭、POSの萌芽
・1980s ブランド論が日本企業へ定着
・1990s インターネット広告が誕生
・2000s SNS登場、双方向マーケティング開始
・2010s 顧客体験(CX)思想普及、口コミとレビューが購買を左右
・2020s サブスク時代へ。マーケティングが顧客生涯価値(LTV)中心に
■ものづくりは「大量生産」から「多様性と継続改善」へ
一方のものづくり。前回の丙午は日本が高度経済成長の最中だった。繊維や精密機械、電子機器、造船などの輸出産業が日本のGNPを押し上げていった。「Made in Japan」の刻印は、世界中で品質保証の証となった。工場は24時間フル稼働。作れば作るだけ売れた。問題は「どう作るか」ではなく「どれだけ速く作るか」だった。しかし時代が変わり、世界が変わり、ものづくりの意味は根本から書き換わった。
まず顧客が求める価値が多様化した。同じ型を大量につくるより、一人ひとりのニーズに応えられる柔軟性が評価される。多品種少量、短納期、カスタマイズ……かつて例外だった領域が、今では主戦場となった。
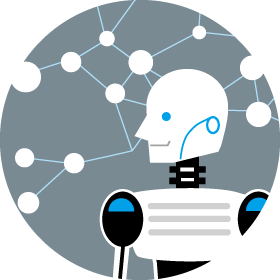
また技術と情報が生産工程を変えた。IoTが機械と工程を可視化し、AIが異常を検知し、ロボットは危険作業を代替する。技能の習熟は必要だが、属人的な勘と経験をデジタルが補完する時代になった。現場は知識労働の場になりつつある。
もう1つの変化はバリューチェーンが世界に広がったことだ。材料は海外、組立は国内、販売は世界。複雑化はリスクも呼び込むが、その分市場は広がり、またネットの進展などでニッチトップを狙う企業に門戸が開かれた。
さらに品質の意味が変化した。「不具合がない」は最低ラインであり、期待を越える体験、使う歓び、さらに廃棄時点の責任まで含まれるようになった。製品の寿命は買われた瞬間ではなく、回収や更新の瞬間まで続く。いわゆるライフサイクル全体で質を測るようになった。
廃棄は消費者の問題ではなく、企業の責務になりつつある。企業は製品を届けるだけではなく、使いこなしてもらう、改善の声を受け取る、価値体験を継続するという伴走役を担う。リサイクル、アップサイクル、再生材料などを組み合わせながら、製品の“終わらせ方”を考えなければならなくなった。ものづくりは「つくる」から「使われ続ける条件を整える事業」へ転換したと言える。
製品によってはアップデートが前提になっている。スマホや家電、車ですらソフトで改善される時代となった。性能は買った瞬間の完成度ではなく、時間とともに育っていく。“育つ製品”を前提にものづくりは組み立てられている。
丙午to丙午 60年のものづくり変化史
・1960s 日本的量産体制確立、QCサークル誕生
・1970s 自動化ライン導入、ジャストインタイム体系化
・1980s 世界に広がる日本製造方式
・1990s グローバル調達・中国生産へ本格展開
・2000s CAD/CAM、3D設計普及
・2010s IoT・センシング・ロボット化が現場へ/アップデート前提の設計
・2020s 多品種少量+需要予測、廃棄前提の循環設計へ
■健康・医療は「治す」から「守る」へ
健康観も変わった。昭和の健康観はシンプルだった。体調を崩せば病院へ行き、薬を飲み、治るのを待つ。しかし現在は、病気を未然に防ぐことこそが重視されるようになった。
変化の背景にあるのが生活習慣病の台頭だ。加齢や遺伝だけでなく、食事、運動、睡眠が健康を左右することが明確になったことで、自己管理が重要テーマとなった。健康は医師に任せるものではなく、本人が日々積み上げるものへと変わった。
情報の透明性が高まったことも大きな変化だ。かつて医療情報は医者側にあり、患者は専門家の判断に委ねるだけだった。しかし今、誰もが知識にアクセスできる。治療法やそのリスク、検査結果の意味など、患者が主体的に判断する前提が整っていった。
予防の考え方も広がった。検診、ワクチン、食事改善、メンタルケア。どれも「余裕がある人の余技」ではなくなった。病院に行かないために行う行動が、健康の中心になった。
さらに社会の健康に対する姿勢が変化した。禁煙、ランニング文化、健康経営、企業のウェルビーイング投資……。健康は個人の問題ではなく、社会の生産性を支える基盤として捉えるようになったのだ。
長寿よりも健康寿命。治療よりも予防。病院に行かないために行動する社会へと、60年で価値観は反転した。

変化してきた健康観のなかで、とりわけ注意が払われるようになったのがメンタルヘルスだ。かつて「心の病」という言葉は、口にすることさえ憚られた。会社を休めば「根性が足りない」と言われた時代。それがいまや、企業は産業医を配置し、学校にはカウンセラーが常駐する。「メンタル不調は誰にでも起こる」─この認識が、60年かけてようやく社会に根づいた。
心の不調は「悪」や「弱さ」ではなく人生の自然現象として受容されつつある。誰にでも起こりうることとして共有されるようになった。
企業では産業医、メンタルプログラム、休暇制度、カウンセリングが整備され、学校でもスクールカウンセラーが常設されつつある。個人的対処ではなく、環境を整える方向へ変化した。
健康は体力ではなく、心の安定とセットで捉えるものとなった。「体の健康+心の安定=人生の土台」となるのである。
丙午to丙午 60年の医療・健康の変化史
・1960s 医師中心モデル、結核など感染症対策が焦点
・1970s 薬剤・検査技術の発展
・1980s 生活習慣病が国民病に
・1990s 予防医学の提唱が始まる
・2000s 禁煙運動・健康指標普及
・2010s 健康寿命という概念が浸透
・2020s メンタルケア、睡眠、ウェルビーイングが企業戦略へ
■食生活は「生きるため」から「選ぶ理由のある食事」へ
健康を左右する食生活はどうだろう。昭和の食卓は「生きるための栄養補給」という色合いが強かった。大量生産された食材、価格競争、便利さ優先の加工食品が巷にどんどん注ぎ込まれたが、60年のあいだに驚くほど変わっている。
まず、食の目的が拡張した。「空腹を満たす」だけでなく、「心地よく生きる」「未来の自分の体を作る」へと意味が広がっていった。栄養バランス、腸内環境、脂質の質、添加物への意識。知識の裾野が広がり、食事は自分の健康を設計する行為として捉えられるようになった。
また食のアクセスが劇的に変化した。スーパーと家庭料理が標準だった時代から、冷凍食品やミールキット、惣菜の進化が家庭に時間を取り戻した。とりわけ冷凍食品の進化は凄まじく、実際の惣菜以上の食味、食感を実現するまでとなっている。またミールキットは、生協やOisixなどの宅配システムの広がりと、共働き世代の増加などから発展、子育て世代や高齢・介護、単身世帯などに浸透していった。外食も多様化し、ファストフードにファミリーレストラン、ミシュランの三つ星レストランなど価格帯やスタイルが細かに分化した。1980年代になると、その選択肢はさらに増えていく。大手のファミレスチェーンがさまざまなコンセプトの店を展開するようになり、さらに料理もさまざまな国籍、民族のものが提供されるようになった。各国料理をミックスした「無国籍」料理も登場している。

90年代になるとファミリーレストランが多ブランド化する一方で、「中食」という新しい選択肢が生まれた。その主役がコンビニエンスストアだ。深夜0時でも、早朝5時でも、温かい弁当が買える。冷凍技術の進化で、専門店顔負けの味が家庭の電子レンジで再現できるようになった。料理は「作る/作らない」の二択ではなく、「どう組み合わせるか」の問題に変わった。
さらに新たな価値軸が加わった。美味しさ、栄養、美しさだけでは選ばれない。食材の産地、育て方、農薬や肥料、動物福祉、フェアトレードといった背景が、購買の基準に加わった。食に関する「倫理感」が普及しつつある。またグローバル化によって、宗教的なタブーが日本の伝統的食生活に持ち込まれるようになり、厳格なイスラム教徒向けのハラール認証料理、厳格な菜食主義者向けのビーガン料理、菜食主義者でも魚もOKというフレキシタリアン料理などの細分化が進んだ。さらに健康意識の関連でアレルギーに対しての告知など、食の提供者に対する負荷も増えていった。
このほかフードロス削減や地産地消、地球環境への配慮など、社会全体の課題としての食も姿を見せてきた。世界の人口増加と資源制約の中で、食生活は個人の選択であると同時に社会への参加を意味するものとなった。
食とは人間が行う最も身近な意思決定であり、自分と世界の未来に対する態度表明である。私たちの皿の上には60年の価値観の変化が投影されているのである。
丙午to丙午 60年の食生活変化史
・1960s 洋食の普及、外食チェーン登場
・1970s 加工食品・インスタント文化
・1980s ファミレス全盛、栄養価より手軽さ
・1990s 安全食品ブーム、産地表示の関心増
・2000s フードマイレージ・オーガニック台頭
・2010s プラントベース(植物由来)・無添加志向
・2020s 食が価値観の表現手段に(エシカル、地産、循環)
■交通は「所有と集中」から「共有と分散」へ
この60年間での劇的な変化の1つに、移動の自由度の高まりが挙げられるだろう。1960年代は、交通の飛躍時代と言えるほどで、日本の鉄道技術の集積である新幹線の開業や、高速道路の誕生、それに伴う自家用車(マイカー)の激増が起こった。1980年代になるとマイカーはとくに地方に浸透し、一家に1台どころか、2台、3台も珍しくなくなった。地方での移動はマイカーがデフォルトとなった。また地方では空港が整備され、いまや首都圏以外は都道府県に1空港が当たり前となり、地方空港からダイレクトに海外に出国できるようにもなった。

一方で交通インフラが整備されるに伴い、都市部への人口集中が加速し、大都市の交通渋滞や通勤ラッシュが社会問題化していった。
1970年代に2度のオイルショックに見舞われると、社会全体に省エネ志向が高まり、あわせて光化学スモッグなどの原因となる工場や自動車から排出されるNOxなどの公害物質を抑える目的で自動車の環境性能が向上、燃費性能を含めて日本車の評価が世界中で高まっていった。自動車の評価軸は馬力や装備などから、CO₂排出量、静粛性、ライフサイクルの環境負荷へと広がった。こうし
た評価軸からEV、HV、燃料電池などの新技術が続々と生まれていった。こうした自動車の進化は関連産業の拡大・進化も促した。燃費性能を1mでも高めるための緻密な電子制御技術や、安全性や静粛性を高めるための新素材の開発、ロボットなどの製造機器の開発など、極めて広範な分野のシーズを掘り起こした。
一方で車そのものとの付き合い方も変化した。車は買って保有し、使いたい時に使うのが当たり前だったが、都市部では、シェアカー、カーサブスク、ライドシェアが一般化していった。
車を走らせる社会インフラの側もダイナミックに変わっている。地域交通、オンデマンドバス、自動運転の社会実験など、人口減少社会にあわせた再設計が進んでいる。
かつての消費者は“与えられる交通とエネルギー”を使っていたが、いまは、“社会全体で作り続ける交通とエネルギー”に関わる主体となりつつある。自動車はもはや移動手段のみならず、非常時の生活を支える電源の役割も担うようになった。
丙午to丙午 60年の交通変化史
・1960s 新幹線登場、自家用車時代へ
・1970s 高速道路網整備、オイルショック
・1980s 地方自動車化社会完成
・1990s 省エネ車開発加速
・2000s ハイブリッド車普及
・2010s EV、本格実用化。太陽光発電拡大
・2020s 共有型交通、自動運転実験、家庭発電+蓄電が現実に
■教育は「教える」から「自分で学ぶ力を鍛える」へ
教育とは、文字通り教え育てることだ。その場が学校である。学校で教えるのは専門の資格を持った教師だ。教師が生徒に知識を教え、生徒が覚え、試験で測る。それは効率的で公平なシステムの側面を持っていたが、生徒は常にカリキュラムに沿った内容を受け身で覚えることが中心だった。また授業の進行は「平均的」もしくは「標準的」生徒を念頭に置いていたため、「多様性」や「個人差」には対応しにくい構造だった。日本の教育は戦後、GHQの指導のもと作り変えられ、現在に至っているが、その中身は60年の間に大きな変化を遂げている。
最大の変化が、学びの主体が子ども自身へと移動したことだ。「なぜ勉強するの?」という子どもの問いに、「受験のため」と答える時代は終わった。いま、子どもたちは自分で問いを立てる。「なぜ戦争は起きるのか」「AI時代に人間の仕事は残るのか」。教科書は出発点に過ぎない。答えのない問いに挑むことこそが、学びになった。教師の役割は、知識を教えるのではなく、課題の発見やディスカッションのファシリテーターであり、アドバイザーとなった。この生徒自身が主体的に学ぶ教育の形は「アクティブラーニング」と呼ばれ、現代教育の中核を担っている。
アクティブラーニングは学びの場を多様化させている。これまで教室に閉じていた学びが社会へと広がり、地域、企業、オンライン、海外など教室の外が学びの場になった。また学校にはさまざまな専門家が関わるようになり、生徒たちの関心領域を広げている。OBやOGのみならず企業に務める社会人や、大学教員などが、小中高の学び舎で輝く瞳と向き合っている。
評価軸も変わった。答えのある問題を解く力から、問いを立てる力、仲間と協働する力、失敗から学ぶ力が問われる。社会が日々複雑に進化する現代においては、1人の才能が課題を解決することは現実的ではなくなっている。課題の解決方法も1つではないように、教育にも正解が1つである必要はなくなっているのだ。
もう1つ、学び続ける力も必要になった。昭和の日本では「学校が終われば揃った武器で人生を歩む」という暗黙の前提があった。しかしいまや知識は陳腐化し、技能は更新され続ける。学び続けなければ、社会から取り残されかねない。生涯学習が本当に必要な概念になった。
教育は、人を社会の部品に整えるシステムから、自ら航路を選べる航海士に育てるプロセスになりつつある。
丙午to丙午 60年の教育変化史
・1960s 一斉授業モデル定着
・1970s 受験競争全国化
・1980s 学校のブラックボックス化進む
・1990s ゆとり教育と課題発見型の萌芽
・2000s ICT導入、学力再定義
・2010s アクティブラーニング導入
・2020s 探究・個別最適・AI伴走型学習へ
■仕事とキャリアは「会社に預ける」から「自分で組み立てる」へ
仕事とキャリアのあり方も変わった。1960年代の日本では、会社こそ人生の安全装置だった。採用されれば定年まで勤め、年功で給料が上がり、会社が面倒を見る。仕事とは時間と労働力を提供し、報酬を得る交換契約だった。
しかし60年のあいだにその安定の基盤は変貌した。まず、企業寿命が短くなった。産業の変化スピードに会社が追いつけなくなり、個人が自分の手で生存戦略を練る必要が生じた。
そのため、キャリアの形が多様化していった。転職、副業、パラレルワーク、独立、フリーランス、地域移住。仕事のキャリアは単線ではなく、分岐が無数に存在するようになった。
さらにスキルの基準が変わった。労働時間より成果、処理能力より創造性が評価されるようになり、正しいやり方を守る人ではなく、価値を生み出せる人が重視されるようになった。AIや自動化が底辺を引き上げ、個人の強みは「人にしかできないこと」へと再定義されつつある。
また心理的安全性や働きがいが議論の中心になった。職場は命令と服従の場所ではなく、能力を発揮する舞台となる。幸福やウェルビーイングはもはや個人の主観ではなく、組織の成果と紐づく指標となった。
仕事は生活の糧を得る手段としてだけでなく、社会とつながる方法であり、自分の能力を表現する舞台である。会社に人生を預ける時代から、自分で人生を設計し、職場を選び、役割を創り続ける時代へとなった。教育現場で広がる「アクティブラーニング」の思想が働く現場にも浸透してきたとも言える。
丙午to丙午 60年の仕事・キャリアの変化史
・1960s 終身雇用・年功序列モデルが完成
・1970s 男性正社員中心の社会
・1980s 会社が生活を丸抱え
・1990s リストラ・転職が一般化へ
・2000s 非正規雇用増、副業の萌芽
・2010s 働き方改革・リモート普及
・2020s 副業・自立型キャリア、自由度が選択基準に
■コミュニケーションは「言語のやりとり」から「関係の質の設計」へ
60年の歳月はコミュニケーションのあり方も変えている。コミュニケーションは話すこと、伝えることだと考えられてきた。しかし現代では、その定義が大幅に拡張している。
まず会話の目的が変わった。過去は情報のやり取りが中心だったが、現在は理解や共創が目的になっている。議論に勝つのではなく関係を深める、意見調整ではなく相互学習へ。コミュニケーションは、記録よりもプロセスが重要になっている。

もう1つはコミュニケーション手段が爆発的に増えたことだ。メール、チャット、SNS、動画など、新たなコミュニケーション媒体は年を追うごとに増殖している。メディアの多様化に加えて求められるようになったのはスピードだ。メッセージを送って10分。返信がなければソワソワし始める。1時間経てば「既読無視された」と不安になる。かつて手紙は返事が来るまで数日待つのが当たり前だった。それがいまや、数分の沈黙が「無視」と解釈される。時間の「間合い」は蒸発し、即座の反応こそが信頼の証となった。
メディアの多様化により、コミュニケーションの舞台の階層がフラットになったことも大きな変化だ。かつては情報発信は限られた組織や個人だけが担っていたが、SNSの普及により、誰もが発信者であり、同時に受信者となった。情報は一方向から四方八方へ広がる流れに変わった。
さらに、非言語空間も同時に広がっている。文字情報に代わって、スタンプ、絵文字、動画、ショート、AIアバターが、心情や熱量などの非言語情報を伝えるようになった。
このため企業は上述したように営業やマーケティングのあり方を再構築しなければならなくなった。言葉の洪水の中でどのようなコミュニケーション戦略を執るべきか。顧客や消費者、社会との関係性を守るための工夫が求められている。もちろん企業だけではない。個人の情報が瞬時に拡散する時代では、誤解や摩擦が起きる前提で行動しなければならなくなったのだ。
丙午to丙午 60年のコミュニケーション変化史
・1960s 電話・手紙中心
・1970s 家庭固定電話普及
・1980s FAX・ポケベル登場
・1990s 携帯電話・メール普及
・2000s SNSの誕生、発信者が爆発的に増える
・2010s LINE文化、チャットが業務標準
・2020s オンライン会議、非対面型社会、関係性デザイン時代へ
■社会制度は「均質」から「多様性」へ
かつて日本社会は、同質性と画一性に支えられていた。学校、企業、家族、自治体。そのため政策や制度は“平均的日本人”を想定して設計されてきた。しかし60年の間に、その前提は静かに崩れ去った。
少子高齢化、人口減少、寿命延伸。社会はこれまで通りでは回らないことを突きつけられた。終身雇用や年功序列は徐々に形骸化し、キャリアは各自がつくり出すものへと変わった。同じ道を歩む仲間は減り、それぞれの選択肢が広がっていく。
また、ジェンダー観も劇的に変化した。男性が外、女性が内というモデルは崩れ、育児、家事、介護はどちらが担ってもよい。成人後の人生設計は、家庭、仕事、地域貢献など、個々人が組み合わせて設計する時代になった。
さらに、外国人と共に働き暮らす社会へと踏み出した。単純労働の補充ではなく、多様性の受容が必要になる。制度や文化はその多様性を織り込む方向へ動いている。
社会制度は、同じ形を押し付ける型ではなく、多様な生き方を支える柔らかい基盤へと変わりつつある。社会とはすでにつくられたものではなく、いままさに作り変えている途中である、その主体は私たち全員である。
丙午to丙午 60年の社会制度変化史
・1960s 男性稼ぎ手モデルが標準
・1970s 社会保障制度拡充
・1980s 終身雇用と企業内福祉のピーク
・1990s 少子化問題が語られ始める
・2000s 派遣・非正規拡大、社会格差議論
・2010s 女性活躍推進、外国人労働者受入
・2020s 多様性・包摂(DEI)が制度設計の基本思想に
参考
●『20世紀全記録』[講談社]●『遊べるクリップ SINCE1945[DENTSU広告景気年表]』[電通]●『昭和・平成 現代史年表』[小学館]ほか
ビジネスシンカーとは:日常生活の中で、ふと入ってきて耳や頭から離れなくなった言葉や現象、ずっと抱いてきた疑問などについて、50種以上のメディアに関わってきたライターが、多角的視点で解き明かすビジネスコラム