もしかしたら、そのマーケティング、古くないですか?知ったら目から鱗が落ちる!イマドキのマーケティング
期待を込めて出した商品が売れない。そんな時には、「販路が悪いんだ」「いやPRが足りないんだ」「いや店の販売スタイルが悪い」「いやいや価格設定が悪い」「いやいやそもそも商品設計に問題がある」と、ありとあらゆる意見が飛び交う。ちょっと待ってほしい。意見を交わすのは大事だが、みんな同じマーケティングの土俵に立っているだろうか。知識が古かったり、浅かったりしないか。つまり、それぞれが持っている知識の鮮度や濃さ、強さがバラバラなまま議論していないだろうか。基準や前提条件が違うまま議論を重ねても、有効な解決策にはつながらない。じゃあどうするか。お互いのマーケティング知識をすり合わせることが重要だ。たとえば、ダイレクトレスポンスマーケティング界隈で人気のダン・ケネディの理論を学んでみるのはどうだろう。
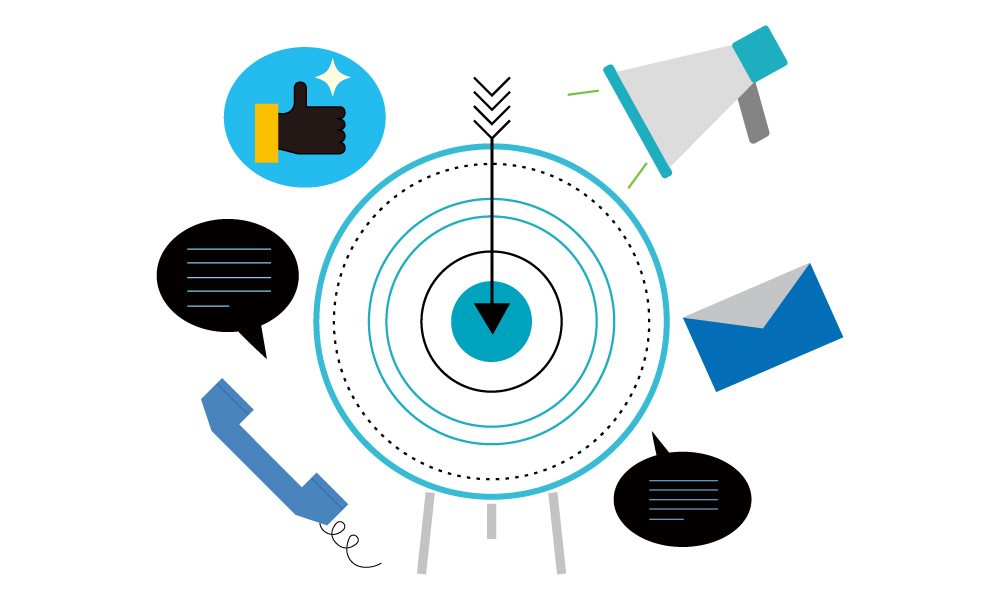
ケネディはダイレクトレスポンスマーケティング(反応型マーケティング)において、アメリカを代表する実務家だ。その主張は一貫していて、ビジネスは「認知を増やす」より先に、①誰に売るか(理想客の選別)、②何をどう提案するか(強いオファー設計)、③反応を測って改善できるか(追跡・検証)、④一度接点を持った相手を追いかけ切るか(フォローアップ)で勝負が決まるというものだ。
商品の魅力を引き出し、顧客を惹きつける広告やコピーを単に「かっこよく」「魅力的」にするだけではなく、「売上・利益」という“結果”で評価し、売上・利益アップに繋げる実践的な手法を説いてきた人物だ。ダイレクトレスポンスマーケティングという言葉は耳慣れないかもしれないが、コンシューマー向けの営業や、SNSを使った売上向上を図る上では、極めて実践的で、かなり「目から鱗が落ちる」理論が並ぶ。いくつか紹介してみたい。
目次
■①磁石のように“選ばれる側”になる設計
ケネディの中核は「見込み客を追いかけるな。追いかけなくても来る仕組みを作れ」という、マグネティック・マーケティング(Magnetic Marketing)と呼ばれるもの。闇雲に広告やプロモーションを出すより、まず理想客を定義し、その理想客が“反応せずにいられない”価値提案、オファー(提案条件)を作り、それが継続的に配信される媒体・導線を持つことで、集客を“イベント”から“システム”へ変換するのである。この考えを実務に落とすなら、まず「誰に」「何を」「どんな条件で」売るかを抽出して、ホームページや広告だけでなく、ニュースレター、DM、紹介など複数チャネルで同じUSP、つまりユニークなセールスポイントを反復し、指名買い・再購入・紹介が起きる状態を狙っていくのである。このマグネティック・マーケティングは、特に小規模事業ほど“商圏・顧客の濃度”が効く。ケネディは広く薄くではなく、狭く深い“磁力”を作るのがポイントになると言っている。
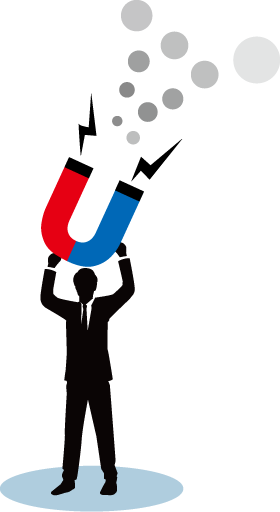
■②カッコよさより“現金が残るか”で判断する
ケネディはマーケティングを「芸術」ではなく「投資」として扱う。とかく大掛かりな広告を見ると“芸術的”といった評価が前に出がちだ。これはブランディング“だけ”で終わる活動や、測定不能な施策、自己満足だけのSNS運用などを排し、反応・成約・継続・利益に直結する行動を優先する考え方だ。実務ではまず、「その施策は、いつ・どの指標で・いくら回収できるのか」を先に定義する。たとえばキャンペーンなら、顧客獲得単価(Cost Per Acquisition/Action=CPA)ではなく顧客生涯価値(Life Time Value=LTV)まで見て、許容できる獲得単価を決める。そのうえでプロモーションの利益構造(原価・人件費・広告費)を織り込み、反応率を上げる改善(見出し、オファー(提案条件)、保証、フォローアップ)を回すのである。つまり“正しいっぽいこと”より“当たること”を残す現場主義だ。
■③未成約は“捨て金”ではなく“資産”
ケネディが繰り返し強調するのが、「フォローアップこそ最大の利益源」という点だ。いかに営業上手でも、1回の広告や1回の商談で決めるのはかなりの難易度だ。1度で諦めてしまうと、反応しなかった見込み客の獲得コストが全て死んでしまうことになる。だから未成約でもメール・DM、SNS等で継続的に接触し、比較検討のタイミングを拾えば、同じリストから売上が何度も立つ。実務では「問い合わせ後7日」「見積提出後14日」「セミナー参加後30日」など、購買の意思決定周期に合わせて接触設計をする。重要なのは“しつこさ”ではなく、理由と証拠を追加して意思決定を前に進めることだ。フォローアップの設計があるだけで、広告効率も営業効率も別物になる。
■④追跡・測定ができない広告はしない
またケネディは、広告をロマンではなく検証可能な実験として扱う。反応が取れたかどうかを“雰囲気”で語るのではなく、「媒体別」「オファー(提案条件)別」「リスト別」に結果を分解し、次の改善へ繋げるのだ。実際には相手の名前、所属、購入内容、地域、家族人数、持ち家か賃貸か、あるいはクーポンのコード、使用媒体、メール、オファーの内容など、最小単位で因果関係を見える化する。そして「勝ち要因は何か」を特定し、勝ちパターンに投資を集中させる。逆に測定不能な施策は、改善のしようがなく、資金・時間を吸い続ける。施策を“システム化”して再現することで、誤差の少ない測定になる。
■⑤独自の売り(USP)を言語化せよ
ケネディが理解を勧めるのが、見込み客の頭の中で起きている「比較検討」。結局商品を買うかどうかを決めるのは、商品が対価に見合っているかといったコスパ、この商品を買った場合、自分はどう見られるのか、思われるのかという他人との比較、すなわちメタ認知。商品は常に比較検討される存在だ。だから違いを明確化する必要がある。違いはすなわちその商品ならではの「売り」だ。この独自の売り(USP)が曖昧だと、価格競争・知名度競争になりやすいのは周知の通りだ。そこでケネディは選ばれる理由を一文で言える状態を作ることを重視する。実務では、顧客の不満(現状の代替手段の欠点)を洗い出し、そこに対して自社だけが提供できる強みを結びつけることだ。さらに、その強みを証拠(実績、第三者推薦、数字、事例)で固定する。USPが立つと、広告の反応も営業のクロージングも、フォローアップの効率も上がり、同じ努力で得られる利益が増える。
■⑥セールスレターは“構造”で勝つ
ケネディにはいくつかの著書があるが、そのなかの代表作『The Ultimate Sales Letter』が示唆するのは、セールスレターは才能ではなく構造物だ、ということだ。セールスレターは、DMなどが発達した欧米のマーケティングでは王道媒体の1つとして知られ、近年ではホームページの商品紹介ページ、案内メール、商品動画などで使われる。読者の注意を、興味→欲求→信頼→行動の順で心理を動かす設計に落とし、反論(高い、怪しい、今じゃない等)を先回りして潰し、証拠と保証でリスクを引き受けて、最後に明確な行動指示(CTA)を置く。具体的なやり方としては、いきなり本文を書かずに、ターゲットの“悩みの言葉”の収集、見出し案の大量出し、オファーと保証の骨格決め、証拠の棚卸し、FAQで反論処理、という順で設計すると再現性が出る。「書ける人」より「勝てる設計ができる人」を増やすのがケネディ流だ。
■⑦コミュニティ、教育ビジネス化を進める
TikTokやYouTube、Instagram、ULIZA、OneStreamなど動画サイトの充実によって、ネット上には会員制サロンやコミュニティが増殖中だ。実はこうした「サロン化」は欧米文化として古くからあり、ケネディ周辺でも教材・会員制・コミュニティを通じて成功事例が再生産される“場”がある。こうした場は受講者・会員の成功談が多数掲載され、単なるノウハウ提供ではなく、思考法や実行の型を継続的にインストールする仕組みとして機能している。こうした場作りは現代の顧客の囲い込みには必定となっているが、ケネディの場合は、①教材(体系)を提供し、②コミュニティで継続率と実行率を上げ、③成功事例が新規顧客獲得の証拠になる、という循環となっていることが特徴だ。自社が教育やコミュニティを事業として持たない場合でも、同じ発想で「顧客向けの学び(導入支援・活用講座・事例会)」を設計すると、解約率が下がり紹介が増え、LTVが上がっていくことがわかっている。

他にも世界中ではさまざまなマーケター、経営学者、実務家が独自の理論や実践を日々繰り返している。いくつか紹介してみたい。
■⑧合理性より「認知の価値」が売上を動かす─ロリー・サザーランド(Rory Sutherland)
ロリー・サザーランドは英国の広告・マーケティングの実務家で、グローバル広告会社のオグルヴィ(Ogilvy)の英国法人(UK)の副会長として知られる。オグルヴィは、行動科学(Behavioural Science)を広告実務に取り込む手法を得意としていてさまざまな広告・PRに実績を挙げてきた。
サザーランドによれば、購買というものは「人は合理的に買っているのではなく、“そう感じた”から買う」のだとする。よってマーケターがやりがちなのは、機能改善・価格・スペックのような“説明できる価値”に投資し続けることだが、現実には、同じ機能でも「高級に見える」「安心できる」「自分らしい」といった“意味づけ”で選好が変わるという。だから、製品開発者は製品を根本から作り直すより、たとえば見せ方(パッケージ、UI〈ユーザー・インターフェイス〉、言葉)、選択肢設計(価格やグレードの松竹梅)、ストーリー(商品開発の由来・背景・理由)を変えるだけで成果が大きく変わることが多いという。サザーランドがいうように、安定した顧客がついているロングセラー商品でも最近は商品パッケージデザインを変えるケースが増えている。背景としては、SNS映えが商品購買力を左右するようになったことが挙げられる。こうしたデザインの変更は商品開発(MD)担当者のアンテナ感度次第となり、ユーザーの声から拾うことはなかなか難しい。したがって実務としては「機能訴求の追加」より先に「解釈が変わる仕掛け」をテストし、短期間で反応を確かめる必要がある。たとえば値引きの代わりに“特典”を足す、配送を早くする代わりに“到着までのワクワク体験”を作るなど、心理価値の最適化が武器になるのだ。
■⑨「成長はロイヤルカスタマー化より、浸透率(買う人の母数)」─バイロン・シャープ(Byron Sharp)
企業が長期の安定した収益を上げていくためには、ブランディングは極めて重要な問題だ。日本ではブランディングはBtoC企業の問題として捉えがちだが、近年はBtoBの老舗企業でも積極的に企業CMを打つなど、ブランディングを意識した動きが顕著になっている。ブランディングの中心概念はいかにロイヤルな顧客を育てるか、だが、バイロン・シャープは、この考え方にメスを入れる。バイロンは南オーストラリア大学に拠点を置くアレンバーグ・バス(Ehrenberg-Bass)という研究所の所長。この研究所は、世界最大級のマーケティング研究所として知られ、彼自身はP&Gなど成功企業のブランディングに影響を与えてきた。
シャープによれば、多くの企業は「ファンを育ててロイヤル顧客を増やす」ことを中心に据えるが、ブランドの成長はたいてい「買う人の数が増える(浸透率)」によって起きやすい。つまり、ヘビーユーザーだけ見て施策を最適化すると市場が頭打ちになり、ライト層や“たまに買う層”を取りこぼしやすい、という。よって①初回購入のハードルを下げる(分かりやすいラインナップ、入口商品など)、②購入頻度が低い層にも“思い出してもらう接点”を増やす(広いリーチ)、③用途・シーンを増やして「買う理由」を増やす、ことなどが効くとする。ケネディの「濃い見込み客を狙い撃つ」と対立するようだが、彼の理論は“成長局面が変わると重心が変わる”ということを突いている。
■⑩「メンタル×フィジカルで伸びる」─バイロン・シャープ(Byron Sharp)
シャープは、またメンタル(思い出せる)とフィジカル(買える)の両輪について新しい知見を与えている。多くの会社は広告・SNSで自社製品の認知を高めようとするが、実際には「買いたい瞬間に思い出せない」「買おうと思っても手に入らない(在庫・導線・支払い・配送・店舗)」で失注することが多いという。こうした失注の対策としては、メンタル側では、カテゴリーエントリーポイント(たとえば、疲れた時、手土産、週末のご褒美)に“連想のフック”を打ち込むことが有効となる。一方フィジカル側は、販売チャネル・検索結果・棚・比較表・カート周りの摩擦を減らすことが有効だ。よって実務では、広告改善より先に「買える場所の拡張」「受発注・在庫管理における最小の管理単位(SKU)の分かりやすさ」「決済・配送の不安除去」をいじった方が伸びるケースも多い。特に中小企業は“少ない広告費で勝つ”ために、フィジカル側の改善が費用対効果の高い武器になる。
■⑪「顧客は商品を“雇う”」─クレイトン・クリステンセン(Clayton Christensen)
ハーバード大学ビジネススクールの教授のクレイトン・クリステンセン(Clayton Christensen)はJobs to Be Done(JTBD)という理論を打ち出した。ペルソナや属性より“進歩の欲求”に焦点を当てる理論で、顧客は「商品が欲しい」のではなく、「ある状況から別の状況へ進みたい」から商品を“雇う”のだとする。JTBDでは有名なミルクシェイクの話がある。朝の通勤で退屈を紛らわせたいなら、ミルクシェイクの競合はバナナやドーナツだけでなく、ポッドキャストやガムにもなる。つまり競合は同じカテゴリではなく、その進歩を満たす代替手段すべてになる、というものだ。これは、進化の激しい時代では誰もが納得する話だ。腕時計はアップルウォッチやガーミンに代替されてきたし、オートバイの競合はスマホやパソコンになっている。じゃあどうするか…。顧客の消費心理の変化を感度を高くして感じ取るしかない。具体的には商品改善の優先順位が変わる(本当に解決したい不便を優先していく)こと、新市場が見える(誰が・いつ・なぜ雇うか)ことを意識することが重要になる。難しいが、手はないわけではない。たとえば競合相手の施策としては、購入直前の状況インタビューから、商品の「雇用理由」をセールスページの見出しに埋め込むだけでも反応が変わるはずだ。

■⑫「広めたいなら“尖れ”。無難は忘れられる」─セス・ゴーディン(Seth Godin)
アメリカのマーケターで著述家のセス・ゴーディン(Seth Godin)は「Purple Cow(紫の牛)を売れ」という。商品があふれる時代では、平均点を狙うと、誰にも嫌われない代わりに誰にも語られない。市場で語られるのは常に「驚き」「共感」「賛否」など、何かしらの“引っかかり”があるものだ。だから「紫の牛」くらい尖ったものにしないと話題にならないという。この話も以前から言われてきた。だがマーケティング担当者は「説明が通る改善」を好むものだ。アップルがiPadを出して、世界中のPC関係者の口を開けたままにさせた時、日本の電子機器メーカーから聞こえてきたのは、「あんなものは、ウチが何年も前に考えていた」という声だ。だが市場には出てこなかった。無難で安全を求める企業のトップが、「ボタンがないではないか。スイッチがわからない」「取っ手がないではないか。落としたらどうする」といった指摘を繰り返した結果、ボタンや取っ手やカバーがつけられ、重く無骨で無難で高価なものになって、とても消費者に受け入れられるものにならなかったのだ。イマドキの商品の拡散や指名買いの起点は、しばしば“説明しづらい魅力”だったりする。だからまず誰に刺さるかを先に決める。もちろん全員は狙わない。尖りを1点に集約して、あれもこれもと言わないことだ。そしてその尖りを“商品・体験・サービスの一部”に埋め込む(広告で誇張しない)のだ。一方、尖りはリスクでもあるので、最初は小さなオファーや限定版で反応を見るのが安全だ。
■⑬「バズりは運ではなく設計できる」─ジョナ・バーガー(Jonah Berger)
アメリカのペンシルバニア大学の教授、ジョナ・バーガーは、アイデアや製品が口コミで広がる(伝染する)ための6つの原則をまとめたフレームワーク「STEPPS」という理論を打ち立てた。口コミが「なぜ広がるか」を要素分解し、再現性を上げるフレームである。その要素は、Social Currency(語ると自分の価値が上がる)、Triggers(思い出すきっかけ)、Emotion(感情)、Public(見える化)、Practical Value(役に立つ)、Stories(物語)の6つ。拡散は“面白いから”だけではなく、「思い出される構造」「共有したくなる動機」「見えやすい導線」が揃って初めて起きるのだとする。実践的にはSNS投稿を増やす前に、トリガー(毎週金曜=これ、雨の日=これ)と、人に見える形(ステッカー、プロフィール、成果物)を設計して、その上で実用価値をテンプレ化(チェックリスト、台本、無料ツール)する。口コミは丁寧な“拡散装置”の設計が効くのだ。
■⑭「説得はセンスではなく“原理”」─ロバート・チャルディーニ(Robert Cialdini)
アリゾナ州立大学の教授で心理学とマーケティングの権威であるロバート・チャルディーニはその名著「影響力の武器」で知られる。彼は営業の世界において人間の行動が人にどのような影響を与えるかを深く追究した。その理論によれば、人が知らず知らずに商品を買ってしまうのは、返報性(一度もらうと返したくなる)、一貫性(言ったことを守りたくなる)、社会的証明(みんながやっている)、好意(好きな人から買う)、権威(専門家・資格)、希少性(残りわずか)などの要素によるものだとする。目から鱗なのは、説得を「上手い言い回し」ではなく「人間の自動反応を引き出す部品」として扱える点だ。商品紹介ページのランディングページに原理を“盛る”より、顧客の不安に合わせて「どの原理が不足しているか」を診断して足すことが効く。たとえばBtoBで権威が弱いと感じたなら監修者や実績者、第三者評価を足す。高額商材で一貫性が弱いと思ったなら、無料診断→提案→小さなコミット(お試しや期間限定使用)の順で段階設計する、などだ。
■⑮「人は“得”より“損”を強く感じる」─ダニエル・カーネマン(Daniel Kahneman)
ダニエル・カーネマンは、行動心理学・経済学の第一線で活躍する学者で、「プロスペクト理論」、「ピークエンドの法則」、「認知バイアス」など、いまやマーケティングや経済学の教科書に不可欠の理論を続々と打ち立てた。その功績から2002年にノーベル経済学賞も受賞している。そのなかで特にマーケティングに効くのが損失回避の理論だ。人は同じ金額でも「得する喜び」より「失う痛み」を大きく感じるというものである。よって訴求するときは、“ベネフィット列挙”だけにすると弱く、放置したときの不利益(機会損失、時間損、健康損、信用損)を適切に見せると反応が上がることがある。ただし、煽りすぎると反発・不信につながる。ポイントは「現実的で、回避可能な損」を示し、解決策として商品を置くこと。具体的には、比較表で“選ばない損”を可視化したり、保証や返金で“失う不安”を減らすこと。期限は“希少性”より“損失回避”(今やらないとこうなる)で設計することが効く。
■⑯「100万人より“1000人の熱狂”を作れ」─ケヴィン・ケリー(Kevin Kelly)
ケヴィン・ケリーはアメリカの著述家、編集者でアメリカの代表的テクノロジー雑誌の『WIRED』の初代編集者である。テクノロジーが拓く未来についての著作が多いが、刻々と進化・変化するテック事情を反映した著作・発言も多い。なかでも有名なものが『1000人の真のファン』である。クリエイターは、100万人がいる不特定市場より、1000人の熱狂的ファンを獲得すれば、安定した収益が出せるというものだ。イラスレーターや作家、写真家などにとって極めて説得力のある理論だ。いまの言葉でいう「太客」である。これは同様に中小零細企業にとっても成り立つ。広い市場で薄利多売をするのではなく、深く支持してくれるファンが一定数いれば、安定した収益基盤になる。そのためにはマーケティングを“拡散”より“関係”として捉え直すことが重要になる。実際には高頻度で買う人を特定し、その人が価値を感じる“継続体験”を設計し(会員、定期、コミュニティ、限定コンテンツ)、紹介や再購入が自然に起きる導線を作るのだ。すると商品や企業自身のライフタイムバリューが上がり、ブランド力がついて価格競争からも離れることができ、BtoBでも応用できる。

いかがだろうか。時代や社会の複雑化に伴い、マーケティングの理論も変化していく。手持ちのマーケティング知識が少しでもアップデートされ、さらには目から鱗が落ちる発見があれば嬉しい。
参考
【書籍】●『ダン・S・ケネディの世界一ずる賢い価格戦略』ダン・S・ケネディ/ジェイソン・マーズ[ダイレクト出版] ●『影響力の武器 なぜ、人は動かされるのか』ロバート・B・チャルディーニ/社会行動研究会[誠信書房]●『人の心を操作するブラックマーケティング』芳川充/木下裕司[総合法令出版] ●『マーケティング論 100の常識』山本久義[白桃書房]
【WEB】● magneticmarketing.com ● HubSpot Accademy(動画)● Talks at google(動画) ● TED(動画) ● influenceatwork.com●Brand Master Academy(動画) ●The Welcome Conference(動画) ● Tim Ferriss(動画) ほか
POINT
①磁石のように“選ばれる側”になる設計
②カッコよさより“現金が残るか”で判断する
③未成約は“捨て金”ではなく“資産”
④追跡・測定ができない広告はしない
⑤独自の売り(USP)を言語化せよ
⑥セールスレターは“構造”で勝つ
⑦コミュニティ、教育ビジネス化を進める
⑧合理性より「認知の価値」が売上を動かす
⑨成長はロイヤルカスタマー化より、浸透率(買う人の母数)
⑩「メンタル×フィジカルで伸びる」
⑪「顧客は商品を“雇う”」
⑫「広めたいなら“尖れ”。無難は忘れられる
⑬「バズりは運ではなく設計できる」
⑭「説得はセンスではなく“原理”」
⑮「人は“得”より“損”を強く感じる」
⑯「100万人より“1000人の熱狂”を作れ
ビジネスシンカーとは:日常生活の中で、ふと入ってきて耳や頭から離れなくなった言葉や現象、ずっと抱いてきた疑問などについて、50種以上のメディアに関わってきたライターが、多角的視点で解き明かすビジネスコラム