
書店業界の大転換か?!“本を売らない書店”が示す新たな生き残り戦略
■倒産激減の背景に何が?書店業界に吹く「変革の風」 202……

■倒産激減の背景に何が?書店業界に吹く「変革の風」 202……

「なぜ、あの店は商品が雑然と積まれているのに客が絶えないのか?」「なぜ、香り……

2024年、ある数値が話題となった。日本企業の実践的人材育成の要、「OJT」……

ビジネス現場で便利に使われる「人間力」。しかし、これほど曖昧で、明確に説明さ……
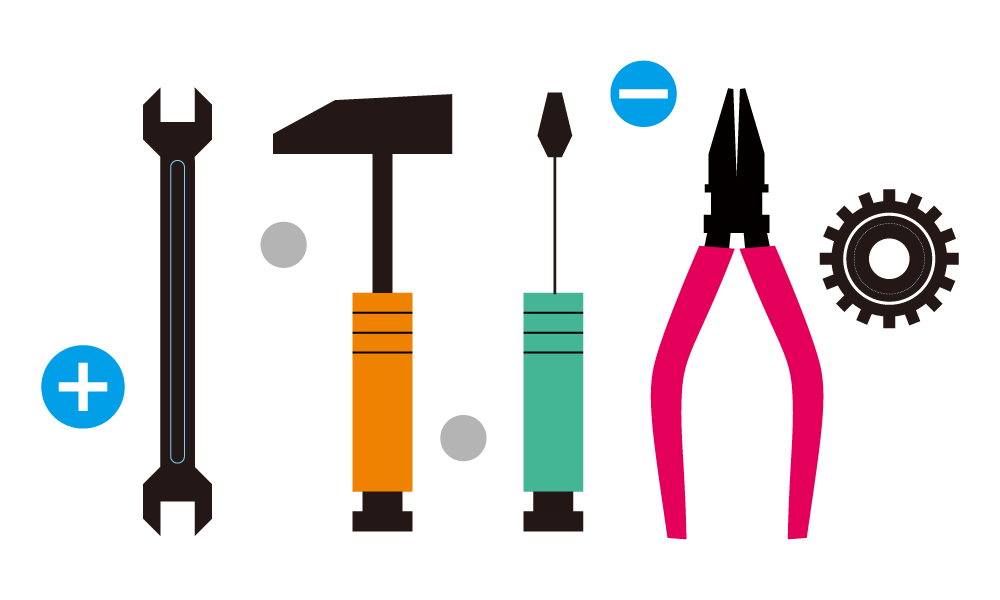
スマートフォンのバッテリーが劣化しても自分で交換できない。農機具が故障しても……

なぜGoogleやAppleは、社員が偶然出会い「雑談」する空間の設計に巨額……

■コロナ禍で人の接触が減って「リトリート」ニーズが高まった ……
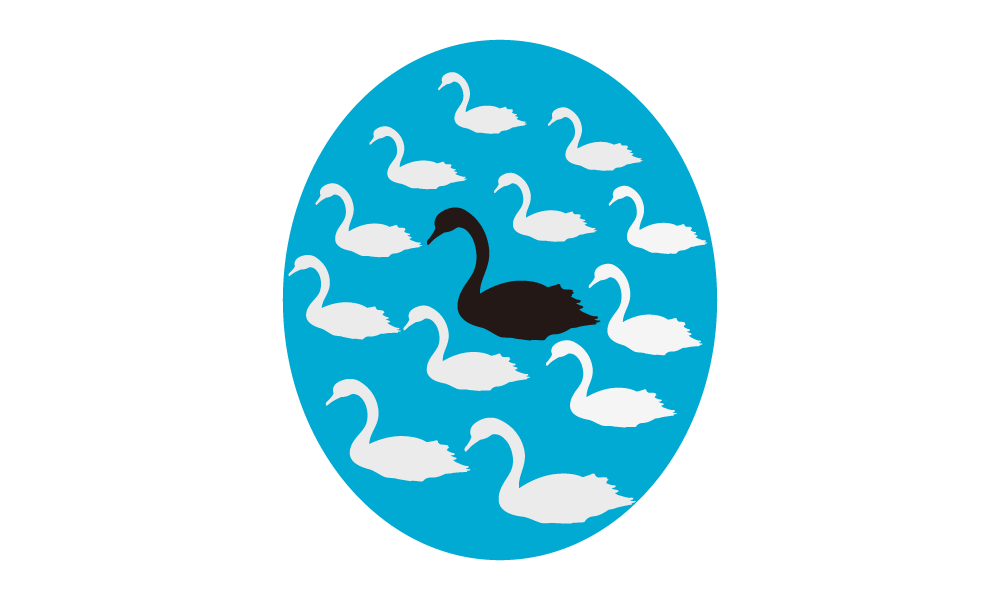
「なぜ専門家の株価予測は、当たらないのか?」「なぜあれほど盤石に見えた大企業……

とかく現代日本のビジネスの世界で求められるのは1にも2にも「イノベーション」……
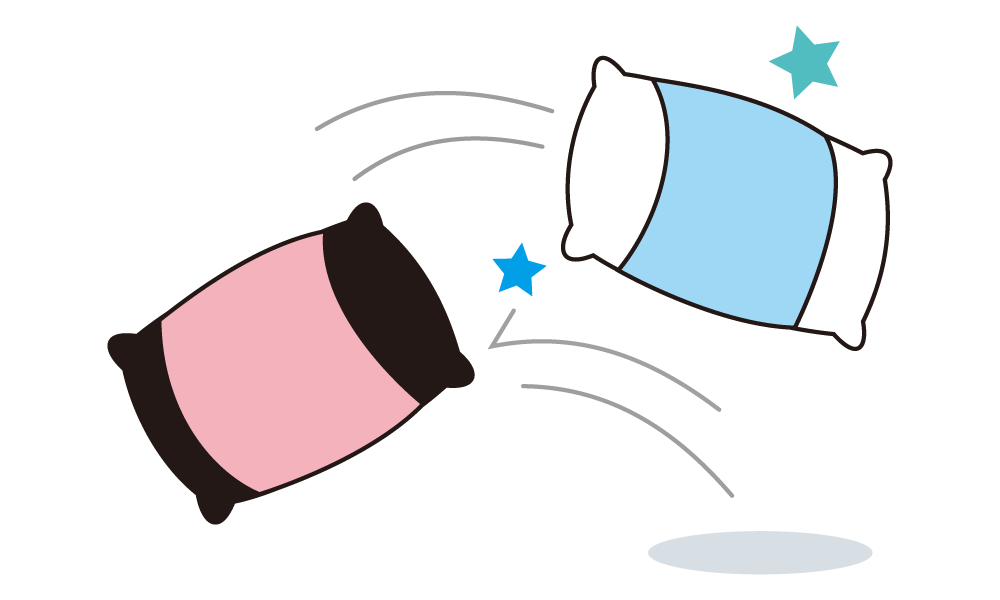
■修学旅行の定番「枕投げ」を競技化。高校生が温泉街に若者を呼び込む……
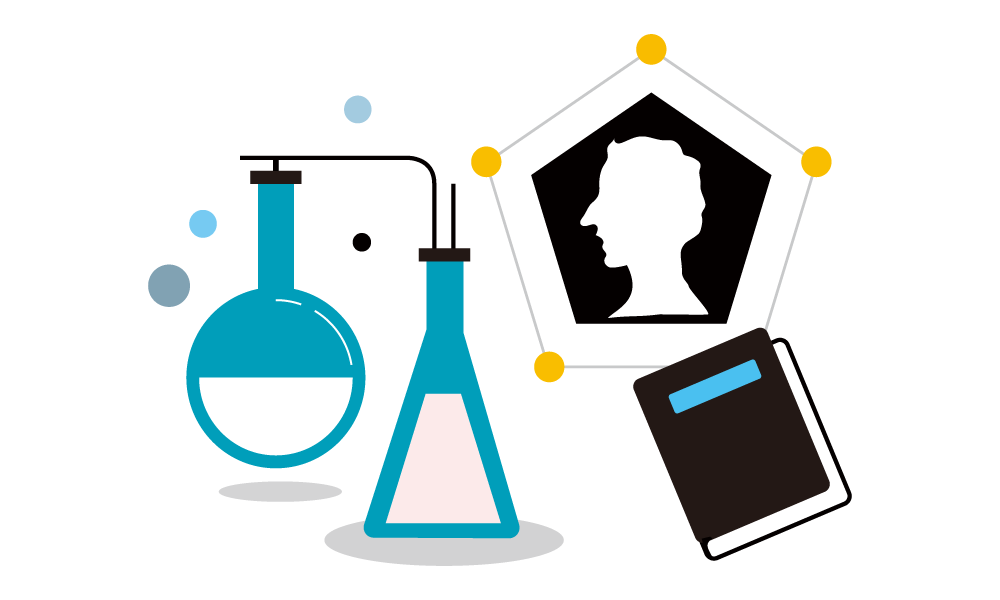
時代が下るにつれ、社会が複雑化し、高度化し、専門化するのは文明の必然だ。しか……
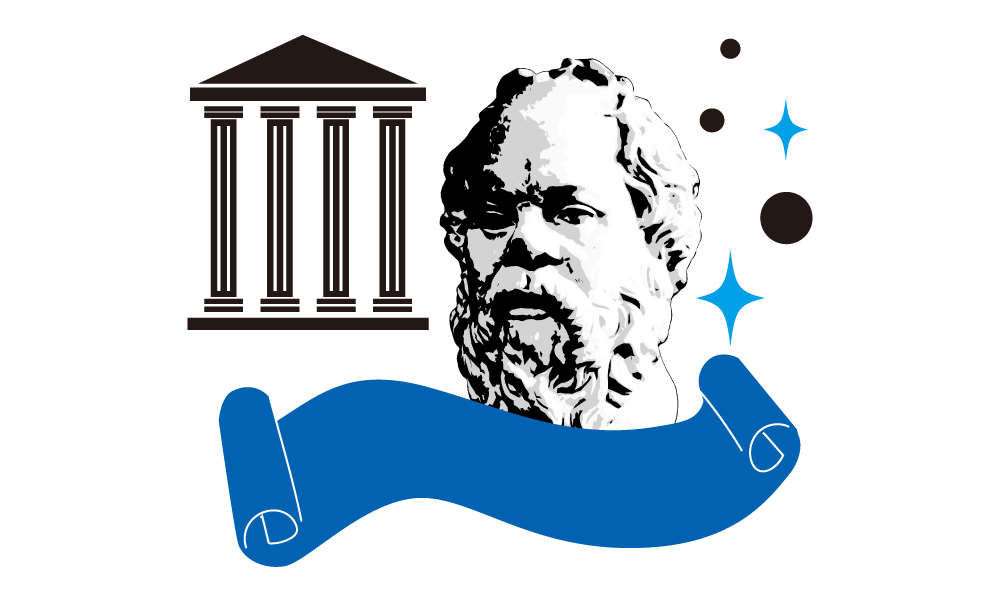
ビジネスパーソンに限らず、私たちは日々新たな課題に直面し、未来への舵取りに心……