できる大人の「シン教養」!その学問は誰が創り出した??学問の宇宙に輝く「創始者」たちの思考からビジネスの未来を学ぶ 1
ビジネスパーソンに限らず、私たちは日々新たな課題に直面し、未来への舵取りに心を砕いている。そのためには新たな知識を得て、試行錯誤を重ねながら課題解決の糸口を見出し、知恵として未来を創造していく必要がある。
そうした私たちの歩みを導く灯台こそが、学問である。好き嫌いに関わらず、学問は社会の根幹を支えており、その進化こそが、より精度の高い社会の構築につながってきたのだ。現在、私たちの社会を支える学問は100以上あるとも言われ、それぞれに「創始者」が存在する。
今回は、学問という広大な宇宙の中で光を放つ彼らの思考と足跡に光を当てたい。彼らが何に疑問を持ち、何を体系化しようとしたのか。未来にどんなビジョンを描いていたのか。そこにこそ、現代を生きる私たちへの貴重な示唆があるはずだ。
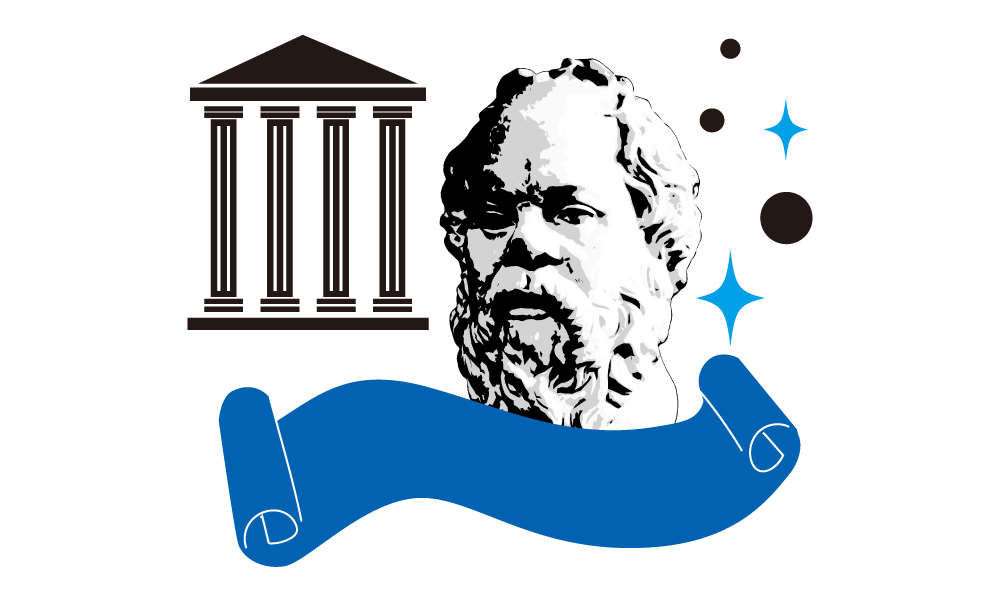
1.哲学と思想の巨人たち
いつの時代も、世界の見方そのものを変えてきたのは哲学と思想だった。彼らのラディカルな思考は、現代の企業倫理、リーダーシップ論、そしてマーケティングの深層にまで影響を与えている。
【哲学】ソクラテス(紀元前469年頃−紀元前399年)
「問い」こそが、人を育て、組織を強くする

あらゆる学問の源流とされるのが哲学だ。その哲学とセットで語られる代表的人物がソクラテスだ。ソクラテスはギリシャ哲学、こんにちの西洋哲学の創始者として知られる。ソクラテスの前にはタレスやピタゴラスなど、自然哲学や数学、倫理学などを探求した哲学者たちがいたが、彼は真理を探求する哲学的手法を確立したとされる。その革新性は、知識の量ではなく「問いを発する力」を重視した点にある。「我が知っているのは、我が何も知らないということだけである」という彼の有名な言葉は、「無知の知」として知られる。答えを与えるのではなく、相手にひたすら問いを投げかける「対話法(問答法)」として学問を展開するうえでの基本フォーマットとなった。大学をはじめとする学問の場で、単に知識を得るだけでなく既知を問い直すという精神の源流には、ソクラテスの思想が大きく影響している。ソクラテスはこの対話法によって人々の思考を深め、自発的な気づきを促した。
無論この対話法は現代にも多大な影響を与えている。対話法は現代のマネジメントで重視されるコーチングや1on1ミーティングの原点といえ、自分の無知を自覚し、常に学び続ける姿勢につなげることは「学習する組織」の基盤となる。彼は、現代のビジネスリーダーが学ぶべき「真のリーダーシップ」の原型を示した人物といえる。また、真の知識が倫理的な行動に繋がるという彼の思想は、現代のESG経営の理念にも通じる。部下に答えを教えるのではなく、良質な問いによって考えさせること。ソクラテスの姿勢は、現代のリーダーシップと組織開発の本質を私たちに教えている。
【哲学】アリストテレス(紀元前384年−紀元前322年)
「実践知」と「中庸」に学ぶ、変革期の意思決定

悠久の歴史を持ち、さまざまな学問を生み出してきた哲学は、ソクラテス以外にも大哲学者を生み出し、新たな知を創出してきた。ソクラテスの孫弟子にあたるアリストテレスもその1人。彼は多様に分化した現在の学問の創始者として知られ、「万学の祖」、「諸学の父」と称される。彼は哲学のほか、「論理学」「生物学」「倫理学」「自然学」「政治学」を創出した。哲学では、「四原因説」を提唱し、存在論や認識論に影響を与えている。彼の革新性は、単なる知識(エピステーメー)だけでなく、それを具体的な状況に応じて応用する「実践的知恵(フロネシス)」を重視した点にある。これは、マニュアル通りの対応が通用しない現代のビジネスにおいて、リーダーに求められる「状況判断力」や「実行力」そのものだ。経営学大学院(MBA)でケーススタディが重視されるのも、まさにこの実践知を鍛えるためといえる。また、アリストテレスは「中庸の徳」を説いた。これは、極端を避けて最適なバランスを見出す知恵を意味し、現代のリスク管理の原点となっている。短期的な利益と長期的な成長、効率化と従業員のエンゲージメントなど、常にトレードオフのなかで意思決定を迫られる経営者にとって、アリストテレスの思考法は、組織を持続的な成長に導くための羅針盤となる。
【近代政治学】ニッコロ・マキャヴェリ(1469年−1527年)
理想と現実の狭間で舵を取る、戦略的思考の本質

「君はマキャヴェリストだな」と言われたらどんな感情を抱くだろうか。冷徹で権謀術数に長けた身勝手な人物と言われたようで、決していい気分にはならないかもしれない。実際マキャヴェリが放った「人々にとって、君主は愛されるよりも恐れられるほうが安全である」という言葉はその証左とも言える表現で、統治者として「親しまれ、敬愛される」従来の君主観を変えた。しかし、彼がその主著『君主論』で示したのは、単なる非情な手段ではなく、理想を掲げるだけでは組織を守れないという、リーダーの孤独と覚悟だった。マキャヴェリの主張の目的は、政治の理念ではなく、リアリストとしての政治だった。彼が近代政治学の祖とされるのは、政治を道徳や理想から切り離し、権力をいかに獲得し、維持するかという現実的な観点で分析することの重要性を説いたからだった。
リアリストの彼はこんな言葉を残している。「運命(フォルトゥナ)は激流のようなものである。堤防がなければ、田畑も家も破壊される。しかし、人間があらかじめ備えをしておけば、被害は小さくなる」。つまり、運命は予測不能であるが、人間の行為によってある程度コントロール可能であることを示しているのである。悲劇や災害が起ころうとしているときに、ただ神に祈るのではなく、現実を見て行動し、回避せよと訴えたのである。彼の思想は、現代の競争戦略やリスク管理においても全く通用する。彼の思想はしばしば『目的は手段を正当化する』という言葉で要約されるが、この考え方は現代のコンプライアンス経営では許容されない。けれども経営者やリーダーは理想の実現のために、時には非情とも思える現実的な判断を下さなければならないという本質を、マキャヴェリは鋭く突きつけているのである。
【心理学】ジークムント・フロイト(1856年−1939年)
「無意識」の力を読み解き、人の心を動かす
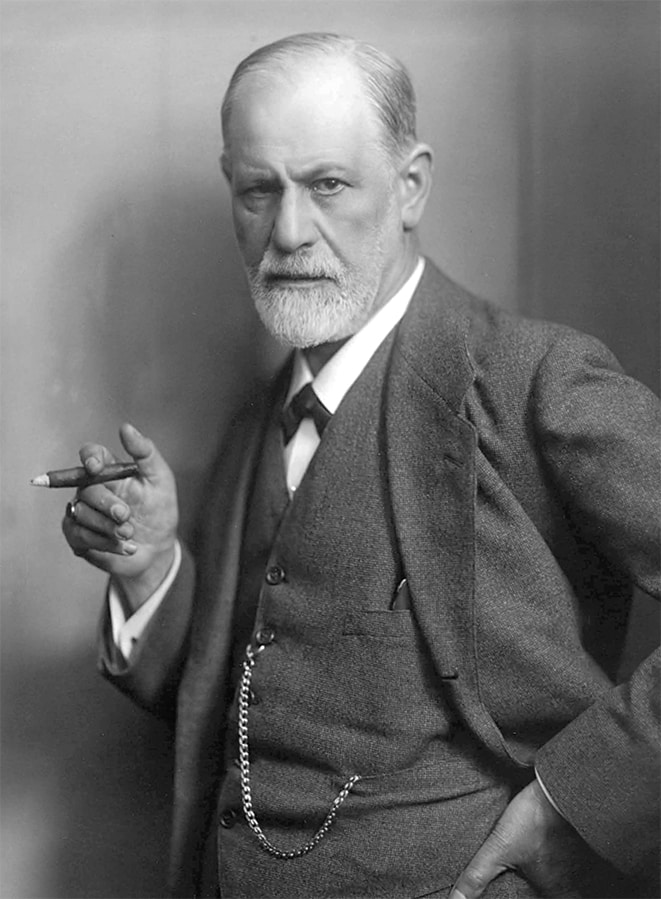
生成AIが人間の持つ知識を凌駕しつつあるなか、人間が人間であるための能力と価値が問われている。注目されているのが人間特有の心の動きである。心理学はその人間の心の“暗黒の森”に光を当て続けてきた学問である。きっかけをつくったのが、オーストリアの精神科医ジークムント・フロイトだ。彼は「無意識」という巨大な領域の存在を提唱し、人間の行動原理に関する我々の理解を一変させた。
フロイトの革新性は、人の心の奥底にある、本人さえ気づいていない欲求や葛藤が、日々の行動や選択に大きな影響を与えていることを突き止めた点にある。これは、現代のマーケティングや消費者行動分析の中核をなす考え方であり、顧客が語るニーズの裏にある、言葉にならない「インサイト」を引き出すことの重要性は、フロイトの理論から学ぶことができる。また、職場での人間関係の葛藤や、変革に対する抵抗といった現象を、フロイトが提唱した「防衛機制」などの概念で読み解くことも可能だ。なぜあの人は頑なに変化を拒むのか。その背景にある心理的なメカニズムを理解することは、組織開発やチームビルディングを進める上で強力な武器となる。
【教育学】ジャン・ジャック・ルソー(1712年−1778年)
「子どもは、小さな大人ではない」
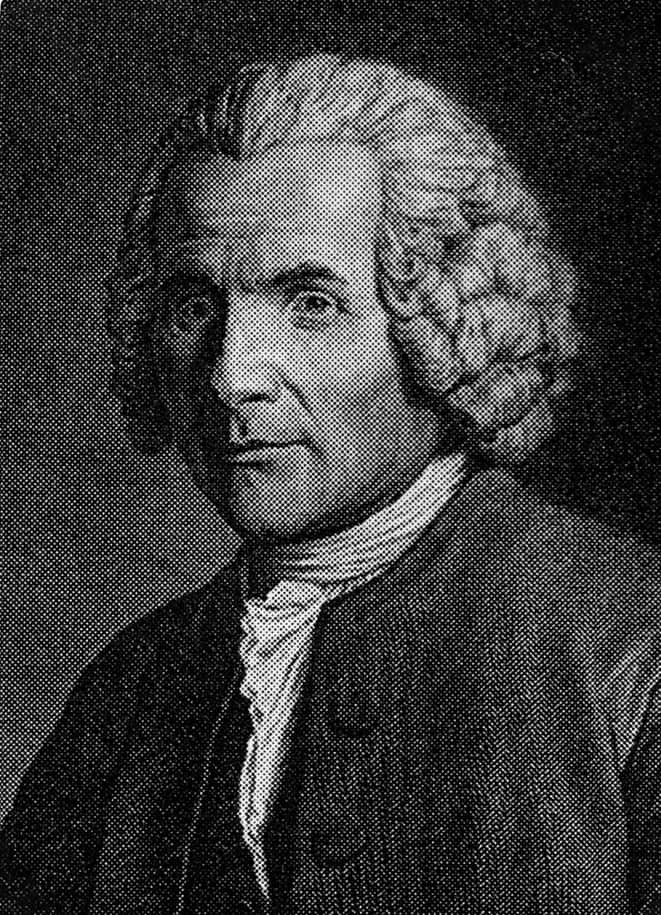
ジャン・ジャック・ルソーと言えば、「国民主権」や「一般意思」などの新しい概念で近代民主主義の基礎を築き、フランス革命やアメリカ合衆国誕生に大きな影響を与えた社会思想家として名高いが、彼は教育にも高い関心を寄せており、1962年に著した『エミール、または教育について』では「人は生まれながらにして善である」という人間観を示し、従来の子ども観を覆した。ルソーの時代の子どもは「小さな大人」としてみなされ、早くから大人の規範を押し付けられていた。ルソーはこれに反対し、「子どもは子どもとして固有の世界を持っている」と主張したのだ。子どもの内なる自然な善性を信頼し、社会の悪習から守るために、教師は知識を詰め込むのではなく、子どもが自らの経験を通して学ぶ手助けに徹するべきだと考えたのである。この考えは近代教育思想の出発点となり、現代の「人間中心経営」や「エンパワーメント」の理論的基盤を築いていった。彼の革新性は、知識を詰め込むのではなく、個人の内なる可能性を信頼し、自発的な成長を促す「自然教育」を提唱した点にある。この考え方は組織においては、トップダウンで指示を与えるのではなく、従業員一人ひとりの潜在能力を信じ、挑戦と成長の機会を提供する現代の人材育成論に直結する。ルソーはまた子どもの「発達段階」に応じた教育の重要性も説いている。企業においては新入社員、中堅、管理職といった各階層で求められるスキルやマインドセットが異なるのは当然であり、それぞれのステージに最適化された育成プログラムやキャリアパスを設計することの重要性を、ルソーは250年以上も前から示唆していたのである。
【現代倫理学】イマヌエル・カント(1724年−1804年)
普遍的な「道徳法則」に学ぶ、揺るぎない企業倫理の基盤

倫理学も哲学と並走する形で西欧の学問体系の幹をなしてきた1つだが、その倫理学の根幹を大きく分岐させた人物が、18世紀のドイツの哲学者イマヌエル・カントである。彼は「認識は、感性(感覚)と悟性(思考)の協働で成り立つ」と主張し、「認識が対象に従うのではなく、対象が認識の枠組みに従う」といういわば従来の常識に対立するコペルニクス的転回の学説を説き、哲学の流れを変えた。そして生み出したのが「定言命法(categorical imperative)」という倫理原理だった。カントは、道徳を個人の感情やその場の利害から切り離し、いかなる状況でも従うべき理性的な法則として打ち立てた。カントによれば道徳は「義務」の問題であり、自律的な理性に基づくものとした。これは、現代においては「この国では許される」といった言い訳を許さず、グローバルで通用する普遍的な行動規範を企業に求めることに通じる。さらに彼は、「人間を単なる手段としてではなく、目的として扱え」と説いた。これは、従業員をコストやリソースとして見るのではなく、一人ひとりの尊厳や成長を尊重する「人間中心の経営」の理念そのものである。目先の利益にとらわれず、長期的かつ普遍的な視点から正しい意思決定を下すための揺るぎない哲学的基盤を、カントは与えている。
2.社会と組織を見つめたパイオニアたち
組織とは、社会とは、そして人間とは何か。この本質的な問いを探求した思想家たちの視点は、現代の組織論やマーケティング、D&I経営の根幹をなしている。
【看護学】フローレンス・ナイチンゲール(1820年−1910年)
データに基づき組織を変革。品質管理の母

まだ看護師が看護婦と呼ばれていた時代では、看護婦は「白衣の天使」というイメージで語られることが多かった。その「白衣の天使」のイメージをつくったのが看護学の創始者フローレンス・ナイチンゲールということに異論はないだろう。看護の仕事は当時からあったが、看護学に高めたのは彼女の功績だ。彼女の活躍は現在のロシアが実効支配するクリミア半島で勃発したクリミア戦争で知られるが、そこで行った看護改革は、臨床の細かな改革もさることながら、データ分析に基づく現場改革の実践であった。彼女は統計データを用いて問題のボトルネックを可視化した。例えば、兵士の死亡率を円グラフで分析し、戦闘による死者よりも劣悪な衛生環境による死者が圧倒的に多いことを証明した。彼女の明確なデータにより、上司も動かざるを得なかったのである。彼女の手法はKPIを用いて現状を分析し、改善策を打つ現代のデータに基づく経営手法の先駆けといえる。さらに、彼女は看護教育を制度化し、専門性を標準化することで、サービスの品質向上と組織の持続的発展を実現している。また科学的根拠に基づいた人材育成システムは、現代企業の能力開発プログラムの原型となった。組織の問題をデータで明らかにし、人材育成によって品質を担保するナイチンゲールの手法は、150年以上たった今もなお、すべての組織にとって重要な示唆を与える。
【女性学】ベティ・フリーダン(1921年−2006年)
「ダイバーシティ経営」の理論的基盤を築く

ダイバーシティ、女性学といった言葉がマスメディアに載らない日はない時代になったが、ベティ・フリーダンという人物の名が載ることは、めったにない。彼女は、ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)の理論的基盤を築いたパイオニアであり、女性学の創始者として知られる。フリーダンの功績は、女性が家庭や社会で感じる漠然とした息苦しさを「名前のない問題」と名付け、それを個人の資質ではなく社会構造の問題として喝破したことにある。そこから彼女は、女性の能力発揮を阻む社会的要因を分析し、教育や雇用の改革を提言。自ら雇用機会均等法の実施、妊娠中絶の権利の擁護、女性の政治参加の促進などを目的に全米女性機構(NOW:National Organization for Women)を設立した。NOWは個人の意識改革と制度改革を両輪で進める組織変革モデルの原型であり、現代企業がD&Iを推進する上で、多くのことを学べる事例となっている。彼女が推進したD&Iは、多様な人材がその能力を最大限に発揮できる組織づくりを目指す、現代の人材活用戦略そのものとなっている。
【家政学】エレン・スワロウ・リチャーズ(1842年−1911年)
家庭は“ミニ社会”。生活を科学し、働き方改革の原点を築く
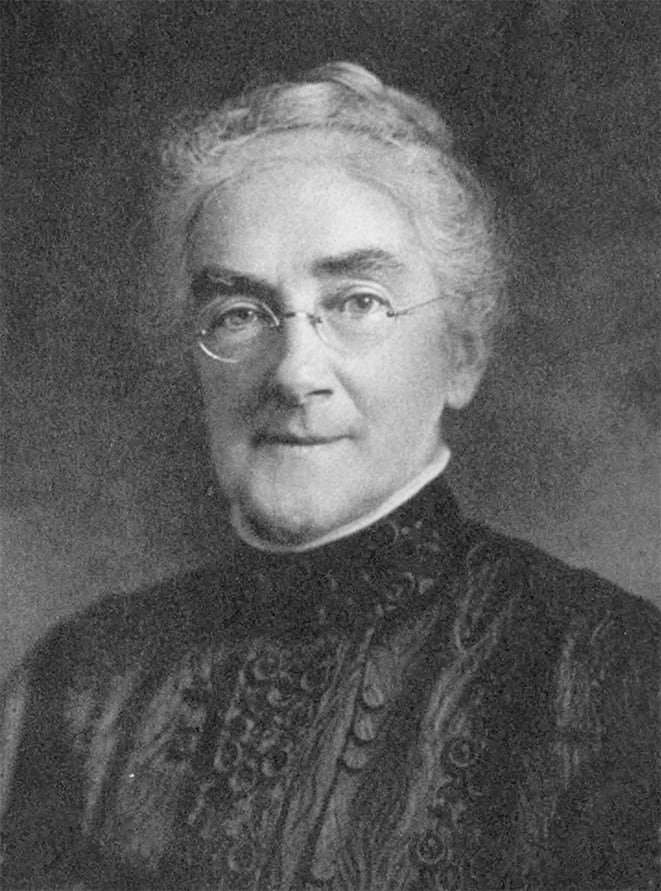
男女平等社会の実現に向けたさまざまな社会情勢の変化を受け、女子大学の共学化が進んでいる。女子大の共学化は日本のみならず、世界的潮流で、いずれ女子大という存在がなくなってしまうことが懸念されている。その女子大の学部編成の中で中核的役割を果たしてきたのが「家政学」である。家政学(home economics)は、衣・食・住・育児・家庭経済・消費・福祉など、家庭生活に関わるさまざまな分野を統合的に研究する学問である。だが家政学というイメージが戦前の「良妻賢母」育成のイメージを引きずっているためか、かねてより家政学の呼称を止め「生活科学部」「人間生活学部」「生活デザ
イン学部」などに変更する大学が増えている。しかしながら、家政学は上述のように、家庭全般のマネジメントに関わる学問であり、とくに近年は、生活科学・生活支援・生活設計・ジェンダー論まで幅広い分野をカバーすることから、じわじわと注目されてきた。男性の研究者も増えてきている。とりわけ新型コロナのパンデミックをきっかけに、世界的にもその再評価がなされている。ステイホームの時間が増えたことで、家庭内における男女の役割や行動に対する、新しい家政学のあり方が求められるようになったのである。また家庭内だけでなく、厚生行政全体や災害分野、ICT、AIなどを視野に入れた統合的、学際的な家政学の構築が期待されつつある。家政学は新たな地平を拓き始めているのだ。
マサチューセッツ工科大学(MIT)初の女性卒業生であるエレン・スワロウ・リチャーズは、家政学を科学的な学問分野へと昇華させた偉大なパイオニアとして知られる。リチャーズは環境学者、化学者でもあった。彼女は家庭を“ミニ社会”として捉え、それまで経験や慣習に頼っていた家庭運営という領域に、化学や物理学、栄養学といった“科学”を持ち込み、栄養、食品衛生、衣類管理、家庭管理、住居設計などを対象とした研究を展開した。リチャーズは「生活の質の向上」を学術的に追求し、家庭という最小単位の組織を科学的に運営することで、社会全体の生産性向上を目指したのである。
その視点は、従業員のウェルビーイングやワークライフバランスを重視する現代の「働き方改革」に通じる先見性を持っていた。また食品の栄養分析や家計管理の数値化といった彼女の試みは、現代の食品産業やフィンテック分野の基礎とも言えるものだった。リチャーズの思想は、「科学を特権的な知識にせず、誰もがより良く生きるための道具とする」という実用と倫理が融合したビジョンが支えていた。
【社会福祉学】ジェーン・アダムズ(1860年−1935年)
社会課題解決型ビジネス(CSV)の原型を築いた活動家

社会福祉学は、人々の生活上の困難を軽減し、社会的な公正と福祉を実現するための理論と実践を探求する学問である。現代の福祉という概念とその発展はヨーロッパにおける、キリスト教の慈善活動に始まる。中世のヨーロッパで慈善活動は教会の役割で、具体的には救済院や慈善団体などが担ってきた。しかしながらその思想には「施しを受ける側に道徳的な欠陥がある」との考えが根底にあり、現在の人間として平等の権利としての福祉とは一線を画している。産業革命以後、世界中で都市に人口が集中するようになると都市部の貧困層が問題となっていた。19世紀末のシカゴの荒れた状況に心を痛めていたアメリカ人のジェーン・アダムズは、1889年に「ハル・ハウス」を設立した。アダムズは、貧困や移民といった問題を個人の責任ではなく社会構造の問題として捉え、包括的な解決策を打ち出した。ハル・ハウスは単なる慈善施設ではなかった。教育、職業訓練、保育、文化活動までを提供する複合的なコミュニティとして存在した。彼女の取った解決策は従来の「一方的な救済」ではなく、「ともに暮らし、ともに成長する」という思想で展開され、「セツルメント運動」と呼ばれた。
また、彼女は社会調査で得たデータに基づき政策提言を行い、さらにその相手も移民、住民、知識人、政治家、企業家といった多様な人々を巻き込む形で、解決策を実現していったのである。彼女が取った活動は、従来の福祉を「社会福祉学」に引き上げた。とくにデータやエビデンスを提示するこんにちの「エビデンスベース」の手法は、社会的インパクトを可視化する上で、現代のNPOやソーシャルビジネスが学ぶべき社会課題解決型ビジネス(CSV)の原型的な要素が多い。
【文化人類学】フランツ・ボアズ(1858年−1942年)
「文化相対主義」が拓く、真のダイバーシティ経営
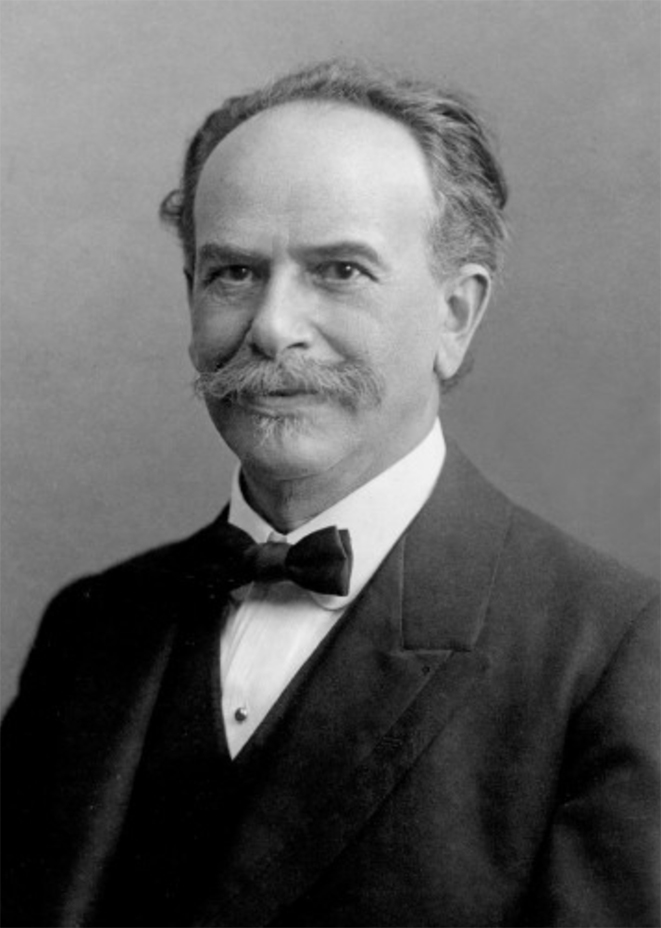
人間の文化や社会の在り方を比較しながら研究する学問である文化人類学。人類学(anthropology)の一分野であり、言語・宗教・習慣・価値観・儀礼・家族・経済・政治など、人々の生活様式を幅広く調査・分析したことで知られる。人類学というととかく未踏のジャングルや山岳地帯に分け入り、長期間にわたるフィールドワークを伴うイメージが強く、どこか現代社会と隔絶した、学問のための学問の印象があるかもしれない。だが文化人類学の知見は、グローバル化が進む現代において、極めて大きな役割と意義を持つようになっている。例えば、マーケティングの手法として知られるようになった「エスノグラフィ・マーケティング」はその1つ。これは、アンケート調査などの定量データだけでは見えてこない顧客の深層心理やインサイトを探る現代のマーケティング手法として定番化している。この手法の元を開発したのがアメリカの人類学者のフランツ・ボアズである。ボアズはそれまで主流だった西欧中心的な「未開→文明」という発展段階説の考え方を批判。「全ての文化はそれぞれに独自の価値を持つ対等な存在である」とする「文化相対主義」を唱え、「ある文化を評価するには、その文化の内側から理解しなければならない」と、先住民と長期にわたって接触し現地語での記録を実施する「参与観察」の手法を確立した。この手法は、文化人類学におけるフィールドワークのスタンダードとなっただけでなく、上述したエスノグラフィ・マーケティングのように他分野に多大な影響を与えた。
ボアズが拓いた文化人類学の理論は、企業においては、自社のやり方や価値観を絶対とせず、各国の市場や文化に合わせて戦略を最適化する「ローカライゼーション」や、多様な価値観を尊重する「D&I」経営の根幹をなす思想である。多様性を単なるスローガンではなく、競争優位の源泉へと昇華させるために、ボアズの視点は不可欠な知恵といえる。
【児童学】ジャン・ピアジェ(1896年−1980年)
「発達段階理論」に学ぶ、組織と個人の学習メカニズム
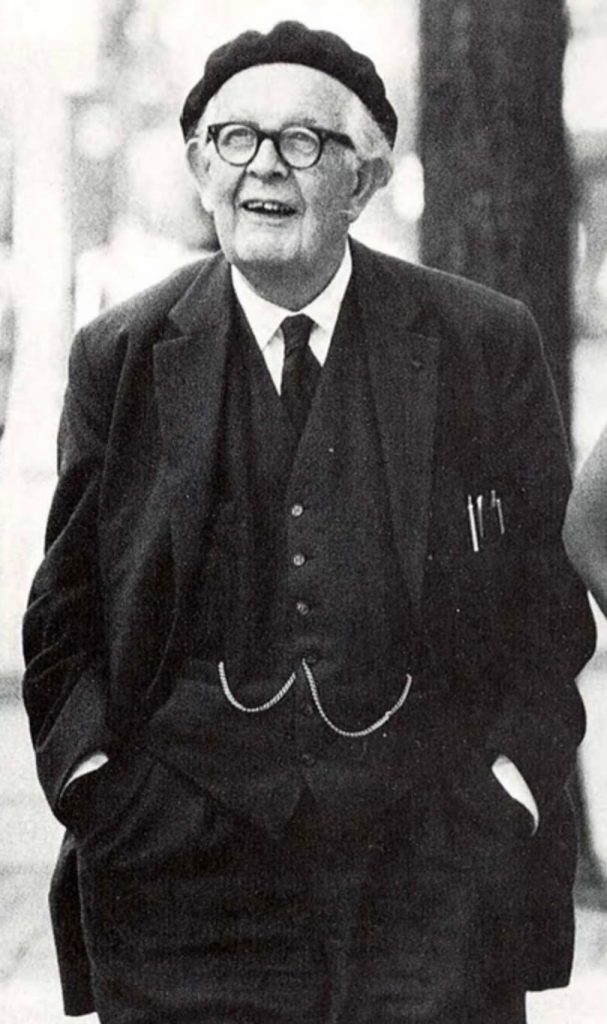
「子どもは小さな大人ではない」と喝破したのはジャン・ジャック・ルソーだったが、それをさらに分解し、段階的に発展するとして理論化したのが、スイスの心理学者で児童学の祖と言われるジャン・ピアジェである。彼は「子どもがどのように世界を理解し、どのようにして大人のような思考へと発達していくのか」を次の4つの段階で展開した。すなわち五感と運動によって世界を理解し、対象の永続性を獲得する0〜2歳の「感覚運動期」。言語が発達するものの自己中心的な思考をし、論理的な操作はまだ難しい2〜7歳の「前操作期」。論理的思考ができるようになり数や量、因果関係を理解するが、抽象概念の扱いはまだ苦手な7〜11歳の「具体的操作期」。そして抽象的思考、仮説演繹的推論が可能になって未来や道徳、科学的問題を論理的に考えられる、12歳〜成人の「形式的操作期」である。
ピアジェは、この「認知発達理論」のほか、子どもが自らの経験を通じて知識を「構成」するという「構成主義」を確立した。この考えは、現在、小中学校で採用されている「アクティブ・ラーニング」や「探究型学習」の基本になっている。ピアジェの子どもの認知発達に関する理論は、単なる児童心理学にとどまらず、組織における人材育成や学習のメカニズムを解き明かす鍵となった。人の認知能力が、生まれつき決まっているのではなく、世界との相互作用を通じて、決まった順序の「発達段階」を経て構築されることを明らかにしたのである。彼の理論は、企業組織においては、社員を画一的に扱うのではなく、新入社員、若手、リーダー、経営層といったそれぞれの段階に応じた学習機会や権限委譲が必要であるという、現代の「段階的能力開発」の理論的基盤となっている。ピアジェはまた、人が新しい知識を学ぶ際、既存の知識の枠組みに当てはめる「同化」と、その枠組み自体を修正する「調節」というプロセスを経る「スキーマ理論」を提唱した。人間はこの2つの繰り返しで「均衡化(equilibration)」が起こり、認知の発達が進むとした。このスキーマ理論は、企業が新しい市場環境や技術に適応していく「組織学習」のプロセスそのものだ。既存の成功体験に固執するだけでは真の変革は生まれない。時には痛みを伴う自己変革こそが、組織を次のステージへと押し上げるのである。ピアジェの拓いた児童学は、児童だけではなく、企業組織の発達に応用できる極めて汎用性の高い理論で構成されているのである。
3.科学と技術で世界を変えた革新者たち
一つの発見、一つの発明が、世界を一変させることがある。不可能を可能にし、現代社会の基盤を築いたイノベーターたちの思考法は、企業のR&D戦略やイノベーション経営のヒントに満ちている。
【経済学】アダム・スミス(1723年−1790年)
「見えざる手」と「共感」で読み解く、持続可能な資本主義
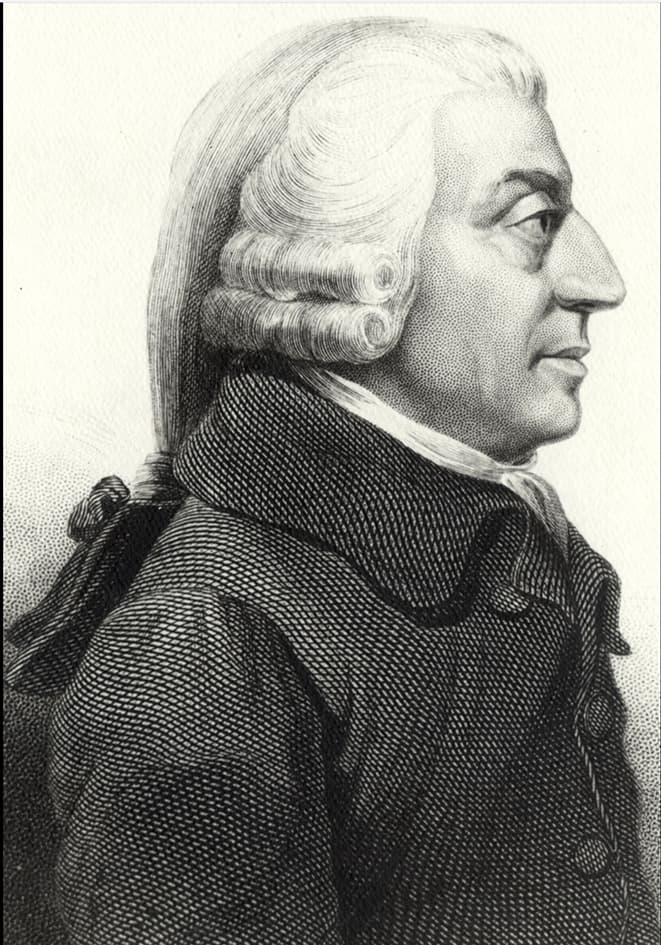
いま多くの国家が採用している経済システム、「資本主義」という構造が歴史のなかに登場したのがいつ頃かは正確にはわかっていない。主に2つの主張がなされている。1つは15〜17世紀、スペインやポルトガル、オランダ、イギリスが植民地貿易を推進し、貴金属や香辛料の貿易を通じて台頭した商業資本をベースに発展した「商業資本主義」、別名「重商主義」である。この重商主義の進展により、資本の蓄積、労働の賃金化、国家による保護貿易などが進んでいった。もう1つがイギリスで起こった産業革命による新興資本家の勃興である。産業革命によって機械制大工業が登場するなど、生産体制は大規模化。従来の製品が安価に生産できるようになり、社会全体のニーズが高まった。そのニーズに応えるべく、工場主が続々と生まれ、新興資本家として、工場で働く者は賃金労働者として固定化していき、資本主義の階級構造が本格的に成立していった。資本を持つ者たちによる生産手段の所有・利潤追求が社会の中心的な原理となっていった。
この資本主義の勃興と発展と沿うように発展したのが経済学だ。その祖とされるのが「神の見えざる手」という言葉で、自由市場経済の原理を説明したアダム・スミスである。彼の、個人の利己的な利益追求が結果として社会全体の利益につながるという市場メカニズムの理論は、現代の自由市場経済の基本原理となり、いまなお多くの学者、専門家がこの原理を支持している。経済学の祖、経済学の父と称されるスミスだが、彼自身は「経済学」という言葉を用いていない。彼は自らの研究分野を「political economy(政治経済学)」と呼んでいた。経済学という言葉を使ったのは、同じイギリスの学者であるアルフレッド・マーシャルが1890年に著した『経済学原理』においてである。スミスが経済学の祖、経済学の父とされるのは、彼が経済を「神学・道徳・政治」から切り離し、独自の分析対象としたからである。中世〜近世の時代、経済行動は主に「道徳」や「宗教(キリスト教的利子観)」の領域で論じられていた。彼は1776年に発表したその主著『諸国民の富の性質と原因の研究(国富論)』で、人間の利己心に基づく経済活動が、社会全体の利益に資する仕組み、すなわち「神の見えざる手」によって誰もが納得する合理的な経済活動に落ち着くと考えたのである。つまりスミスが経済学の父として評価されたのは、「経済現象を独立した因果関係として捉える近代的思考の出発点」となったからである。ちなみに資本主義という言葉も、資本主義制度の推進者からは生まれていない。資本主義という言葉を最初に使ったのはあのカール・マルクスである。
またスミスが活躍したのは産業革命の台頭期であるが、スミスの国富論は、産業革命の勃興期にそれ以前の農業・手工業・商業が中心の産業革命前の前資本主義的経済構造を分析して著したものだった。スミスの問いの中心は、「なぜある国は豊かで、ある国はそうでないのか?」であり、それを説明する手段として「分業」や「市場競争」「労働価値」「見えざる手」などの概念を提示したのだった。
スミスが最も評価されたのは、経済効率と道徳的配慮を統合しようとした点にある。彼は『国富論』に先立って『道徳感情論』という書を著している。このなかで彼は人間の道徳の基盤は他者への「共感」にあると説いた。経済モデルでは「合理的経済人」を前提とするが、現代経済学では、そもそも合理的経済人など現実には存在しないことがわかっている。実際の経済行動は自己の利益を合理的に優先して行動する人ばかりで行われるわけではない。スミスのいう神の手が作用する市場経済とは、キリスト教的道徳心を持つ他者への共感を共有する人々によって営まれる活動を前提としていた。したがって自己利益の強欲な追求のみによって資本を蓄積させる資本家を良しとしなかった。
単なる利益追求が企業の持続的な成長を保証しないことは、現在の多くの経営者が実感しているはずだ。社会からの「共感」を得て、社会全体の利益に貢献する企業こそが、真の競争優位を築くことができる。その意味でも250年以上前のスミスの思想は、現代の経営哲学に通じる慧眼であり、重要な示唆を与え続けているのだ。
【機械工学】ジェームズ・ワット(1736年−1819年)
「効率化」を追求し、産業革命を加速させた改良者
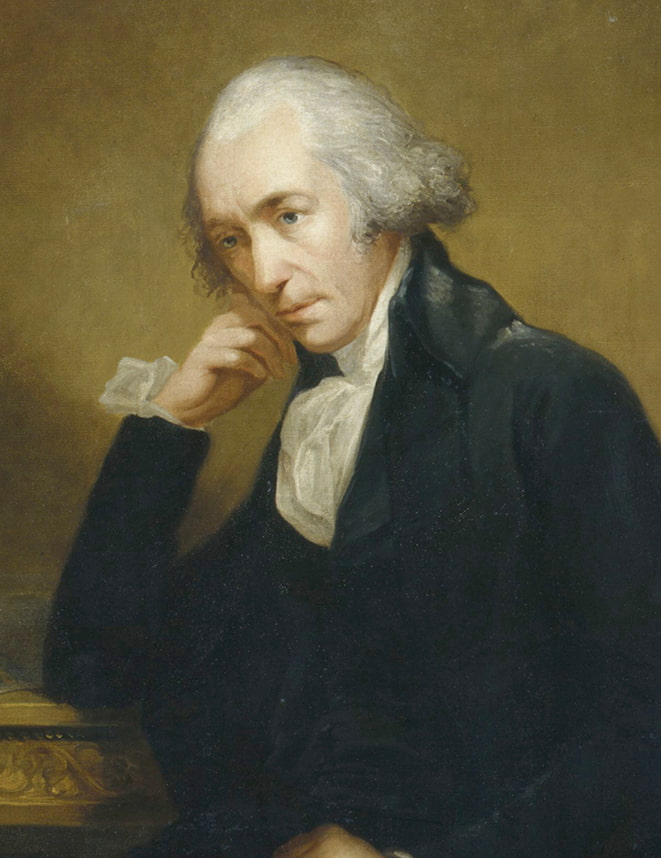
資本主義発展の契機となったイギリスの産業革命。その立役者として挙がるのがジェームズ・ワットである。彼は蒸気機関というエネルギーのイノベーションを起こし、イギリスの産業革命のまさに原動力に仕立てた。彼は蒸気機関の大発明者と捉えられる部分があるが、正確には、既存の蒸気機関の効率を飛躍的に高めた「改良者」である。彼の功績の本質は、発明そのものよりも、既存技術を改良し、事業として成立させ、社会実装した点にあり、現代に至る「効率性の追求」と「持続的イノベーション」の原点を築いたところにある。
ワットは、既存の蒸気機関の本質的な問題、すなわち熱効率の悪さを見抜き、さまざまな改良と発明を行ったのである。「復水器」という分離装置を追加することで燃料効率を劇的に向上させ、また並列運動装置を開発し、蒸気機関を工場の回転機械と直接連動できるようにした。ほかにもピストンを改良し、上下両方で蒸気の力で昇降両用を受けられるようにした。この改良により、出力は倍となった。また太陽歯車を改良し、往復運動を回転運動に変換し、産業用途に最適化している。スピードが出やすい機械では、その速度を制御するために遠心調速機を開発し、速度の安定化が図れるようにした。
ワットの取り組みは、なにかを発明して“終わり”ではなく、ユーザー視点と現場視点からその機械や製品の機能を常にアップデートさせるという、エンジニアとしてのあり方を示している。それは最小限の変更で最大限の効果を得ようとする「プロセス改善」の連続であり、現代のカイゼンやリーンマネジメントの思想と通じる。
彼は優れた技術者であると同時に、パートナーと共に製造から販売、メンテナンスまでを手がけるビジネスモデルを構築した事業家でもあった。さらに、特許戦略を効果的に活用して得た利益を次の技術開発に投資するという循環も創り出している。技術革新、事業戦略、知財戦略を統合した彼のアプローチは、現代のテクノロジー企業経営における最高の教科書といえる。
【電子工学】
ウィリアム・ショックレー(1910年−1989年)
ジョン・バーディーン(1908年−1991年)
ウォルター・ブラッテン(1902年−1987年)
デジタル時代を開いた「共同発明」
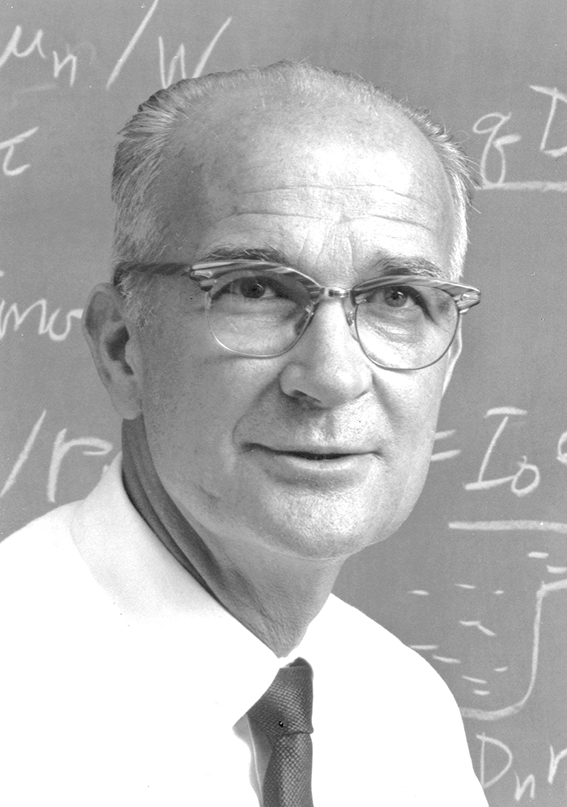
©Chuck Painter
Stanford News Service


技術や製造に関わる人にとってイノベーションという言葉は、自らをドライブさせる原動力となる一方で、大きなプレッシャーとなってのしかかることもある。競争と変化の激しい分野においてはプレッシャーがかかってくる。そういった激しい競争が展開される学問分野の1つが電子工学だろう。こうした分野においては、個人の能力もさることながら、良いメンバーと協業で、学問のフロンティアを切り拓いていくことが求められる。
1956年、アメリカ「ベル研究所」のウィリアム・ショックレー、ジョン・バーディーン、ウォルター・ブラッテンの3名はノーベル物理学賞を共同受賞した。彼らは現代のあらゆるデジタル機器の心臓部であるトランジスタを発明した功績で、研究者として最高の栄誉にあずかることができたのである。彼らは巨大で非効率な真空管に代わる、小型で高効率な半導体素子を創出し、コンピュータから通信機器まで、いうまでもなくあらゆる産業を一変させ、世界の人々の生活を飛躍的に向上させた。既存の技術を根底から覆す「破壊的イノベーション」の典型例であると同時に、電子工学が世界に認知されたのである。
彼らの業績は、研究開発のあり方をも変えた。彼らが所属したベル研究所は、物理学者や化学者といった異分野の専門家が結集し、基礎研究から応用開発までを一貫して行う組織体制を持つ。当時のベル研究所は、世界最高峰の異能の研究者が集まり、あのビル・ゲイツが「もしタイム・スリップできるとしたら、最初に出掛けるのは1947年12月のベル研究所だ」と言わしめたほど、研究者にとって刺激的な場所だった。
トランジスタという歴史的なブレークスルーを生んだのが、ベル研究所という組織的な研究開発環境であったことは、極めて重要であり、意義深いことだった。つまり現代のオープンイノベーションや産学連携の重要性を何よりも雄弁に物語っているからだ。
もっとも、3人はノーベル賞受賞を巡っては、かなり揉めている。実際に受賞の対象となる「点接触型トランジスタ」を完成させたのは、ジョン・バーディーン、ウォルター・ブラッテンであり、ショックレーは2人の上司であった。ベル研究所は当初2人の名前で特許を申請したが、これに対してショックレーが猛抗議した。2人が「点接触型トランジスタ」を開発できたのは、ショックレーから半導体の熱伝導に関するアドバイスを貰ったおかげだというのがその理由だった。怒り心頭となったショックレーは、3日間ホテルに籠もって、「点接触型トランジスタ」の弱点を突いた新たなトランジスタを思いつく。「接合型トランジスタ」である。特定の半導体を反対極の半導体が挟み込む構造になっている「サンドイッチ型トランジスタ」で、製造方法からしても利用方法からしても、圧倒的に「点接触型トランジスタ」より優れていた。ショックレーはこのとき、「製造方法からしても利用方法からしても、圧倒的に『点接触型トランジスタ』より優れている」と公言した。実際その通りで、彼のトランジスタは、20世紀後半の電子機器すべてに応用されて、世界に革命を起こしたのである。
快哉を上げたショックレーだったが、再び怒髪天の事態に見舞われる。ベル研究所はショックレーの名前で特許申請を行ったにもかかわらず、当時の雇用契約では特許料が研究者に支払われないことになっていたからだ。
こうした事態を知っていたのか、トランジスタが世界中に与えた影響を高く評価したノーベル賞委員会は、異例のスピードで3人にノーベル物理学賞を与えることを決めている。功績名は「点接触型トランジスタの発明と改良」である。
3人はその後も和解することなく、ノーベル賞授賞式の晩餐会では一言も言葉を交わさなかったという。ショックレーはその後も2人に対して陰湿ないじめを与えたとされ、耐えられなくなったバーディーンはイリノイ大学教授に就任し、その後「超伝導」の研究を進め、1972年にその業績によりノーベル物理学賞を受賞している。いまのところバーディーンは、ノーベル物理学賞を2度受賞した唯一の人物である。またブラッテンも、ショックレーの下で研究するのは無理だとして、ベル研究所内で転属している。
【環境学】レイチェル・カーソン(1907年−1964年)
『沈黙の春』でESG経営の扉を開いた科学者

もし地球上にレイチェル・カーソンが生まれておらず、『沈黙の春(Silent Spring)』を書かなかったら、地球の温暖化はもっと進んでいたかもしれない。逆に彼女がもっと早く誕生し、『沈黙の春』を書いていれば、地球の温暖化はもう少し穏やかなものになっていたかもしれないと考えるのは、筆者だけではないだろう。
アメリカ魚類野生生物局に勤めていた海洋生物学者のカーソンは、1950年代後半、とくにDDT(ジクロロ・ジフェニル・トリクロロエタン)やその他の化学農薬が生態系に及ぼす影響に気づき、調査を開始した。きっかけは1通の手紙だった。マサチューセッツ州に住む主婦、オルガ・オーエンズ・ハギンズからカーソン宛に、『ボストン・ヘラルド』紙にハギンズが投稿し、掲載された記事のコピーが届いたのだ。内容は「自宅の庭に航空散布された殺虫剤によって、鳥や魚、ペットが死んだ」というものだった。
カーソンは、すでに海洋学者として『Under the Sea Wind』、『The Sea Around Us』、『The Edge of the Sea』という海洋生物についての3部作を出版していた。科学を背景にした確固たるエビデンスを持った彼女の美しい文章は、高い人気を誇っていた。
カーソン自身は、手紙を受け取ったときには、化学物質の環境への影響に関心を持っており、化学物質は食物連鎖を通じて生物に蓄積(生物濃縮)されるということを知っていた。学者としての使命に駆られた彼女は、この手紙によって「今書かなければ、誰も書かない」という決意を持ったのだった。
当然、化学業界からは激しい反発や中傷を受けたが、DDTなどの化学農薬が鳥や魚を通じて、人体にまで悪影響を及ぼすことを、膨大なデータと科学的分析によって証明したことが、世論を動かした。カーソンの訴求力が高かったのは、科学者でありながら詩的で美しい文章力を持ち、声が美しく、人々に届きやすかったこともある。『沈黙の春』は最終的にケネディ政権を動かし、ケネディは大統領諮問機関に科学的調査を命じている。
一つの化学物質が、食物連鎖を通じて生態系全体に予期せぬ影響を及ぼすという彼女の指摘は、いまでは常識となっており、現代企業、とりわけ化学メーカーにおいては厳しい環境基準が設けられ、化学物質の危険性・有害性および取扱いに関する情報を網羅したSDS(Safety Data Sheet) などに反映されている。
彼女は1964年に56歳で乳がんで他界するが、彼女の遺志を継いだ人たちによって環境運動は高まり、「環境防衛基金(EDF)」の設立、アメリカ環境保護庁(EPA)の設立、そしてDDTの禁止などに繋がっている。私たちは私たちを囲む環境―人間関係を含めて―にもっと慎重に優しく向き合う必要があるではないだろうか。
2に続く
参考
【書籍】●『アリストテレス』山本光雄[岩波新書]●『フロイト』小此木啓吾[講談社学術文庫]●『ルソー』今野一雄[岩波新書]●『マキアヴェリ』佐々木毅[岩波新書]●『ソクラテス問題』納富信留[岩波新書]●『アダム・スミス』堂目卓生[中公新書]●『日本大百科全書』[小学館]●朝日新聞デジタル●東洋経済オンライン ほか
【WEB】● PHP オンライン●「学問のすべて」朱雀 SUZAQUE
【動画】●『ゆっくり解説 哲学から現代科学まで2500 年の歩み』[YouTube] ほか
ビジネスシンカーとは:日常生活の中で、ふと入ってきて耳や頭から離れなくなった言葉や現象、ずっと抱いてきた疑問などについて、50種以上のメディアに関わってきたライターが、多角的視点で解き明かすビジネスコラム